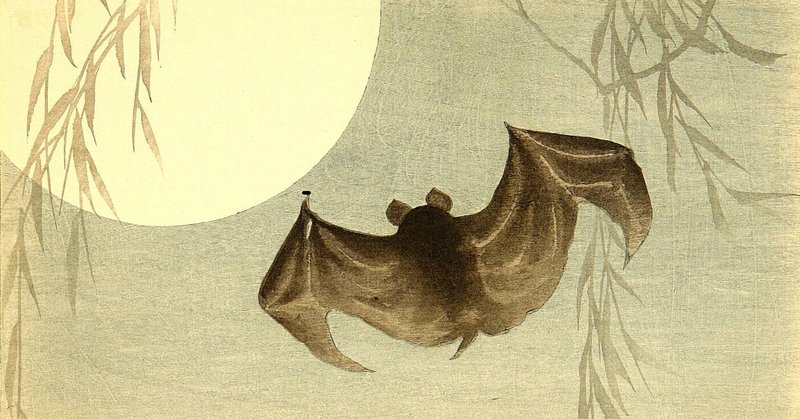
20090416 コウモリとドップラー効果
コウモリはドップラー効果を使って飛んでいる餌の動きを察知$${^{*1}}$$したりするらしい。初めて聞いた。コウモリが自分の鳴き声を使って闇夜の中でも障害物に衝突することなく飛ぶ$${^{*2}}$$ことが出来ると言うことは聞いたことがある。しかしドップラー効果も使うと言うのを聞くのは初めてだ。
ドップラー効果$${^{*3}}$$とは、観測者や音源が動いていると元の音より高く聞こえたり低く聞こえたりする現象$${^{*4}}$$である。一番よく観測できるのは走っている救急車のサイレンの音である。救急車が自分に近づいてくる時は、そのサイレン音は高く聞こえ自分から遠ざかる時は低く聞こえる。実際には救急車から鳴っているサイレンの音色は一定だが、救急車が自分に近づく時は音の波が押されて縮まるので高い音に聞こえ、遠ざかる時は音の波が引き伸ばされるので低く聞こえる。コウモリはこのことを知っているらしい。
本当だろうか。自分の鳴き声が反射するかしないかで、障害物を検知することはできそうだ。進化の過程で障害物からの反射音を聞き取れないコウモリは闇夜の中で木や岩に激突して淘汰されたに違いない。また狭い場所で飛び交っている時に相手の声が聞こえ難い個体同士は衝突してこれまた淘汰されていったのだろう。
鳴き声を高くすることにより更に細かい障害物を避けられる様になり、暗い洞窟の中でも暮らせるため天敵を避けることができて種が保たれた。
このため耳は相当発達している$${^{*5}}$$筈で、虫の羽音など簡単に察知して捕食できるようになったのであろう。人間でも暗闇の中で蚊の羽音を頼りに鬱陶しい蚊を退治することができる。とは言え、かなり苦労する場合が多い。コウモリは鳴き声を発しながら闇の中を餌を探しに飛んでいく。虫の羽音を聞けばそちらの方に飛んでいって捕食するのだろう。その途中で自分の鳴き声の反射音が聞こえたら障害物があることなので翻えるだろう。
こう考えるとコウモリ$${^{*6}}$$がドップラー効果を知る必要はない様な気がしてくる。そもそもどうやってドップラー効果を知ったのだろう。近づく物体からの反射音は高くなり、その逆は低くなるという物理現象を利用した行動を、進化の過程でどのように獲得するのだろうか。想像がつかない。
ある個体がその能力を突然獲得したとする。音の高さを比較するのは脳による情報処理だろうから、次世代にその能力を継承するには親と子との間で情報のやり取りがないと駄目だろう。そんな高度なことがコウモリにできるのだろうか。
*1 コウモリと蛾
*2 コウモリ初級編
*3 20010706 速度違反
*4 ドップラー
*5 NHK高校講座 | ライブラリー | 生物 | 第24回 第4部 動物の受容と反応 刺激の受容と反応
*6 About Bats こうもりのページ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
