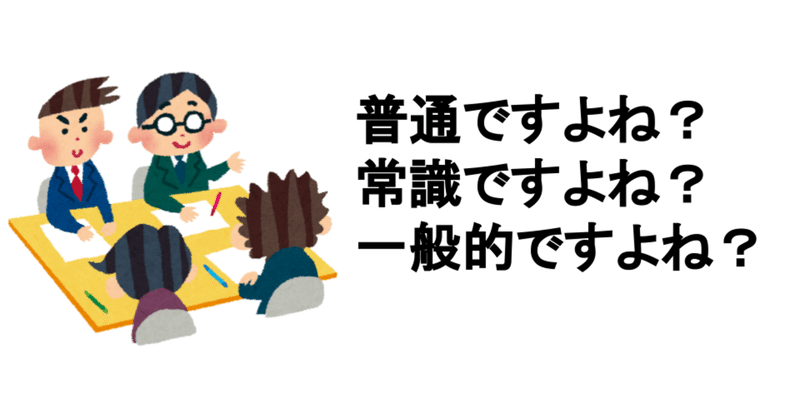
私が一緒に仕事したくない人(6) 「普通」「常識」という言葉を多用する人
私はフリーランスなので、クライアントから求められるのはスキルマッチ(私のスキルが要件を満たすかどうか)であり、ビジョンマッチやカルチャーマッチではありません。
とはいえ、仕事の進め方や考え方に乖離がありすぎると、仕事していて互いにストレスが溜まるものです。なので、「私は○○という考え方なので、××という考え方の人とは相性が悪い」と事前に説明しておくのが重要だと考えます。それを把握していれば、クライアントにとっては、発注後に相性が悪いと判明するリスクを減らせるからです。
※誤解が無いように補足しますが、こういう人はダメだという批判ではありません。こういう人と相性の良い人もいらっしゃるでしょうが、私は相性が良くないので、仕事をしてもwin-winにならないでしょう。
※「私が一緒に仕事したくない人」の記事一覧は下記。
その人の「普通」「常識」に振り回される
仕事をする上で、説明コストが少なく済むのは互いに楽なものです。例えば、私はBtoBマーケティングをしていますが、「BtoBマーケティングで困っています」という企業と、「BtoBマーケティングって何ですか?」という企業の場合、前者のほうが説明コストは少なく済みます。それは、前者の企業と私では「BtoBマーケティング」という「常識」を共有できているからです。
一方で、すべての「普通」「常識」を共有している関係などありえませんから、多少の説明は必要になります(説明コストを0にすることは不可能)。ところが、「普通」「常識」という言葉を多用する人と付き合うと、「普通」「常識」という言葉に逃げて説明コストを払おうとしないのが厄介です。「AはBですよね?」という問いに対し、「それはなぜですか?」と聞くと、「いや、それが常識ですよ」「なぜといわれても……」「上手く説明できません」などといわれ、それ以上話が進みません。言い方が悪いですが、その人の「普通」「常識」に振り回されるのですね。
具体例を出しましょう。
・某スタートアップ企業との業務委託で、マーケティング担当者の採用支援をするという案件があった
・採用要件をヒアリングするために、「そのポジションのミッションは何ですか?」「具体的な業務は何がありますか?」「どういうスキルを求めますか?」などヒアリングしたのですが、「スタートアップによくいる普通のマーケターです」という回答だけで、これ以上話が出てこない。
↑採用をやっている方ならお分かりの通り、人材要件は業界、組織に応じてバラバラなので、「普通」などという人材は存在しません。私では手伝うのは難しいと感じ、この案件は見送りました。
・私の前職で、トライアルで裁量労働制を導入することになった
・それまでは10:30が出社時間であったが、「10:30までに出社しなくてもOKですよね?」とSlackで質問し、イエスという回答を貰ったので、10:30までに出社しないことが増えた(もちろん、会議などで必要な場合は出社)
・導入から1ヶ月後の振り返りで、裁量労働制の発案者が「10:30までに出社しないときに事前連絡をしてこない人がいる」と発言した
・色々聞いた結果、どうやら発案者は「裁量労働制であっても出社時間という概念はある」「出社時間より遅刻する日はSlackで事前連絡をする」ことが「普通」だと思っていた(ので、裁量労働制を導入する際に説明しなかった)
↑もちろん、裁量労働制には「出社時間」「遅刻」などという概念は無いわけで、「それ裁量労働制ではないですよね?」という議論で揉めたのを記憶していますが、発案者は最後まで「裁量労働制であっても事前連絡するのが普通でしょ」と言い張っていました。
私がその人たちの家族や恋人であれば、その「普通」「常識」を尊重し、寄り添ってあげるのが愛情かもしれませんが、残念ながら私は家族でも恋人でもないので、極力付き合いたくないのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
