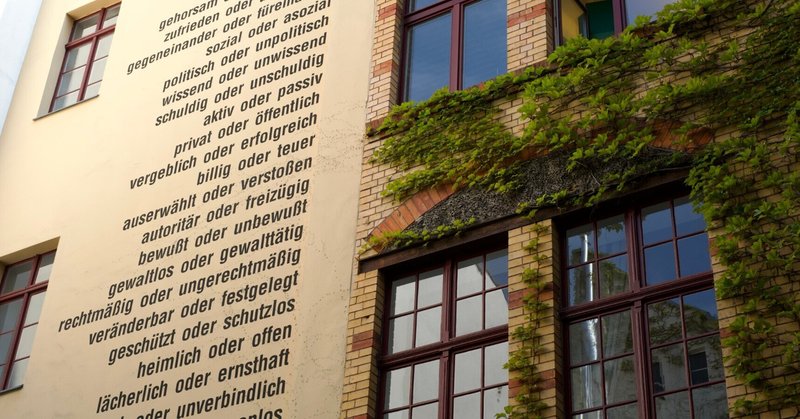
作文の宿題を一緒にやってみた
日本語の補習校の宿題は大体以下のような内容になっているんだけれど、一番難しいのはどうやら「作文」であるらしい。
・教科書音読
・視写
・漢字テスト
・読解プリント
・作文「今日、こんなことがあった」
現地校4年生、補習校が5年生の息子。書くのは苦手だが、自分で今日あったできごとを話すことはできるので、インタビュー形式で作文をすることにしている。要は何を書きたいかを聞いて、どんなことがあったのかを少しずつ質問していくわけだ。
そっか、公園で友達とサッカーしたんだね。二人でしたの?友達が小さな子にやろうって言ったのか。で、最後には何人くらいになったのかな?みんなでやってみてどうだった?
ざっくりこのくらい聞いて、それをできるだけ簡単で短い文にしてあげる。そして、それを読んでもらって内容を確認させる。「初めは」とか「最後には」といった便利な言い回しなどがあれば、使い方を説明する。
友達の〇〇と公園でサッカーをしました。初めは二人でしていましたが、〇〇が小さな子に「一緒にやろう」と声をかけました。最後にはみんなで十一人くらいになりました。
みんなでサッカーができて楽しかったです。
こんな短い文でも、まだまだ自分一人では組み立てることができない。日本の小学校5年生の日本語能力には到底届かないだろう。このくらいの文であれば小学校低学年でも書けるレベルなのではないかな。
オンライン授業だった2年間のブランクがかなり大きい。現地校の家庭学習に疲れてしまい、補習校の宿題を途中から放棄したためだ。結果、息子の日本語学習は3年生くらいの状態で止まってしまったような気がする。
それでも、一生懸命日本語で伝えようとしてくれる気持ちを汲み取って、書き方や伝え方を少しでも教えてあげられればいいな。そんな気持ちでやっている。
結局、言葉は「自分の言いたいことをできるだけ相手にわかりやすく伝える」という目的のために使われることがほとんどだ。たかが作文、されど作文。わかりやすく伝える練習は、おそらくドイツ語にも役立つはずである。
バイリンガルの子どもを見ていると、ドイツ語が得意な子は日本語も得意な場合が多い。読書量もかなり言語力に影響する。コミュニケーション能力の高い子も言語学習が得意だ。
日本語学習のモチベーションはなんといっても「一時帰国」。今年こそ帰れるといいんだけど。子どもたちもそのために頑張っているように思うから。
サポートは今後の取材費や本の制作費などに当てさせて頂きたいと思います。よろしくお願いします!
