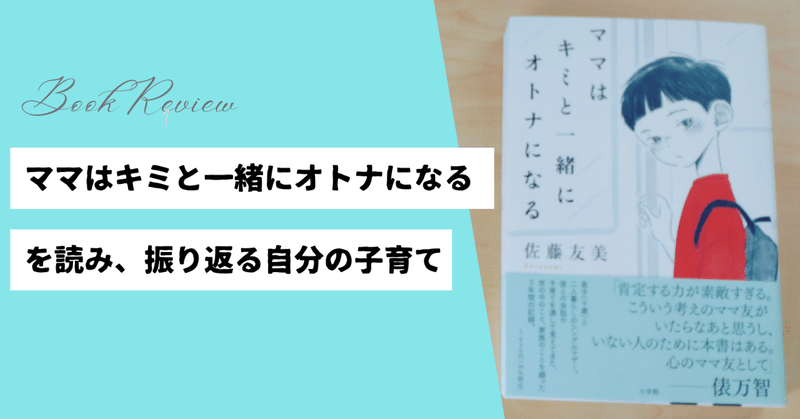
「ママはキミと一緒にオトナになる」を読み、振り返る自分の子育て
先日、さとゆみさんのイベントでサインをもらってきた本を、私はなかなか読めませんでした。
1つは、サイン本だからもったいないと思ってしまったこと。
もう1つの理由は、一般的な子育て本がある時から苦手になってしまったから。
子どもが自宅療養が長い病気や不登校になるという経験を経て、一般的な子育てをするお母さんと話が合わなくなってしまいました。
例えば高校受験で「あの成績で志望校を受けられるかしら、うちの子」と心配するところを、当時の私は「高校に行けるだろうか」と、心配しないといけなかったから。
もちろん、もっと大変な状況のご家庭もあるということはわかっているし、実際まわりにも言われたこともあります。
でも、誰しも自分が体験していることが一番大変であるのも事実。誰かの大変は自分の大変にはなり得ません。
だから、どうしても本のページを開けずにいました。
その瞬間は突然訪れる
ちょっと落ち込んだことがあったある日。なぜか禁断の「ママキミ」を気がついたら、手に取っていました。
読み進めると、帯の俵万智さんの言葉通り「心のママ友」がそこにはいました。もっと早く読めばよかった、と後悔。
先日友人から、「大きなトラブルなく子育てを終えた人でも、子育てって正解がないことだから、自分との葛藤や振り返ればあぁすればよかったとかはあると思う」と、LINEをもらいました。
この時に、自分の悩みは実は特殊な悩みではなく、意外と一般的な子育ての悩みなのかもと今更ながらに気づくことに。
なんだ、誰にも共感されない話ではなかったんだと、ちょっと笑ってしまいました。
子育ては一生ベテランにはなれない
子育てって、初めての子どもが0歳の時に自分がママ0歳。特殊な事情がなければ、18歳くらいでおおむね終了。それ以上のベテランになる人はいません。
子どもの人数が多ければ、上の子の子育てで予備知識は豊富にあります。でも、兄弟でも同じように育てられません。そう考えると、形は変わりつつも一生終わらないプロジェクトのようなもの。
実は子育てに向いていないと思い、今までの子育て期間中、ずっと自己肯定感が下がりっぱなしでした。そのとどめが、子どもの病気と不登校。心のどこかで、ずっと自分を責め続けていた私。
「きっと私みたいな子育てに向いていない母が、この子たちの親だからこんな風になってしまったんだ」
と、子どもが寝静まった夜中に泣き続けたことも数知れず。暗闇の中で、世間に誰も味方はいないという孤独感は半端なくて。
溢れる気持ちの行き場はどこにもありませんでした。このままではおかしくなってしまうと、スマホでポチポチとブログを始めて。数々のミラクルが起こり、やっぱり書くことに携わりたいと今があります。
「ママキミ」の中にあったのは、シングルマザーのさとゆみさんと息子さんの日常。私も子どもが小さい頃から、子育て日記でもいいから文章に残しておけばよかったと激しく後悔しました。
自己肯定感低めな育児期間を過ごしたとしても、きっと楽しかった瞬間もあったはず。もったいないことをしたな、と。
例えば「赤ちゃんが静かにしていると思っていたら、お尻拭きを全部出していた」みたいな話はよく聞きますよね。これを文章で残していたらその時は後始末が大変で笑えなくても、後で見るとかわいすぎるエピソードに爆笑できそう。
きっと子育てって、そういう瞬間の積み重ねだと思います。
前半は泣きっぱなし
子育てエッセイでこんなに泣くことがあるのかというくらい、泣きました。
とくにこの辺りが実感を持って、染みた部分。
子どもができて初めて知ったのだけれど、出産や子育てをめぐるシーンには、多くの「すべき」が満ちていた。
(中略)
そう思った私は、ひとつ、ルールを決めた。それは、あらゆる判断を「自分(たち)のために、する」ということだ。
私は気づくのが遅くて、たくさんの「すべき」に苦しめられてきました。結果、心が疲れていた時期もあります。多くのお母さんが早い時期にこれに気づくと、気持ちがラクになるはず。
子育ての方針を決めるのは、まわりじゃないです。誰にも正解がわからないから、育てている人が自分軸で選んでいくしかありません。
小説の言葉で心が守られることもある
全部を書いていたら書き切れないので、もうひとつだけ紹介します。
ではその瞬間、私の心をぷるんと包んで守ってくれたのは何だったかというと、これははっきり覚えているけど、小説だ。
(中略)
誰かも分からない人の言葉に傷つくことは、自分を大切にしてくれる人に対して失礼にあたるんだな。これは衝撃的だった。
このエッセイの中では作品名が書かれていないですが、私も同じ作品が大好きで何回も読んだので、他でこの話を見た時にピンときました。
カミソリレターをもらったさとゆみさんは、新井素子さんの「星へゆく船」シリーズのワンシーンを思い出し、自分の心を守ります。
同じシーンが印象に残りながらも、私はそこまで思えてなかったので、学生の頃の私に耳打ちしたくなりました。
幸せは日常の些細な出来事の中にある
子育てに向いてなさすぎて、必死で、子育てを楽しめたとは言えません。
子どもたちが大きくなった今、もっと小さい頃に子育てを楽しめていたらなぁ、と。
「中学生になったら、グッと楽になるわよ」
と先輩ママさんに言われていた私は、そこまでは自分のことは全部後回しで我慢する期間だと思っていました。
ある意味、忍耐の子育て。早く大きくならないかな~と。
私なりに必死で子育てに取り組み、さぁ、もっと働こうと思っていたら訪れた思わぬ試練。
ただ、その予想外の試練が思わぬことを運んできてくれたことも事実。もう忘れようと思い、心に蓋をしかけていたけれど、自分の人生の転機となった出来事でもあります。
「人間万事塞翁が馬」という言葉にもあるように、幸せか不幸かはその時にはわかりません。不幸だと思った出来事が、幸せに転じることもあるということ。
悲喜こもごもの子育て、楽しんでいけたらいいですね。
そしてこの本は、俵万智さんの言葉にもあるように「心のママ友」として、そっと寄り添ってくれる本だと思います。
もっと早くに出逢えていたら、ネガティブママ全開だった頃の私が救われていたかもしれません。
昔の私と同じように、思い悩むママに届きますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
