
予算1万なのに2万円のリュックを買わされてしまった心理を考察してみた
もう何ヵ月も前の話になるのですが、ある百貨店で「得をして損」をしました。
このヘンテコな出来事は、あらゆる人々の日常生活から仕事の現場でも起きうることで、にも関わらずほとんどの人が意識して認識できていないことです。だからここで書き記しておくことにしました。
まだ何のことを言っているのか意味不明だと思うので、まずは「得をして損した話」を聞いてください。
■2万円のリュックが急に……

この日、僕はプライベートで使うリュックを買いに百貨店へ行きました。
普段づかいで、そんなに良いものを買いに行ったわけではなかったので、予算はだいたい「1万円」で考えていました。
いろいろお店を回った後、実際に背負ってみてしっくりくるものが一つ見付かりました。
しかし、値札を見るとなんと「2万円」
普段づかいで適当に使えるものを探していたので、予算の倍を払ってまで買おうとはならなかったので、棚にリュックを戻し、渋々お店を去ろうとしたその時です!
そばで見ていた店員さんが近くに寄ってきて
「ちなみに、いくらなら即決できますか?」
と聞いてきました。
少し、ん……?と思ったのですが、言われるがままに
「そうですねぇ、15000円くらいですかねぇ」
と答えました。
すると店員さんは小さく頷き、「ちなみに、今、おいくつですか?」と再び尋ねてきました。
「29です」と僕が1歳サバを読んで答えると、また小さく頷き、「わかりました。レシートは出せないのですが……15000円でいいですよ」と、驚くべきことに僕の言い値で本当に5000円も値下げしてくれたのです!
そのお店は個人経営みたいなところでは一切なく、わりとしっかりしてる百貨店の中に入っているお店で。しかもその人は店長でもないですし、セール品だったわけでもこれからセールになる商品でもありませんでした。
このいきなりの対応にびっくりして、なぜ値引きしてくれたのか聞いてみたら、
「自分も若い頃、セールでもないのにいきなり値引きしてもらったことがあったからなんです。お金がなかっただけに私はそれがすごく嬉しかった。おかげで欲しい服が買えたんです。もちろんいつもはやっていないし、一度だけですけど、人を見てたまにやることにしてるんです」
「ちなみに年齢を聞いて、自分より年上だったら値引きしてなかったですよ、ははは」
と店員さんは優しく答えてくれました。
僕は最も手っ取り早く、かつ効果的にコミュ力を上げる方法は「人にされて嬉しかったことや感動したことを、自分の色を加えて、他の人にしてあげること」だと思っているのですが、
この人の行為はまさにそれにあたるもので、欲しいリュックが手に入っただけでなく、自分のコミュニケーションで大事にしていることと通ずるということもあり、すごく気持ちが高ぶったのでした。
(もちろん勝手に値引きすることはお店的にはかなりアウトなことだと思うので、倫理的観点はここでは置いておいておきます)
さて、そろそろ問題の核心に近付いてまいりました。
__________

僕ずっとちょっともやもやしてたんですよ。でも、なぜもやもやしてるのかもわかっていなくて。それがやっと最近になってわかったので今これを書いてるわけなのですが、
それは
「なぜ僕は「1万円」と言わなかったのだろう?」
ということです。
どういうことかと言うと、冒頭にも書きましたが、予算はだいたい「1万円」のつもりでした。
それくらいのリュックがあればいいなぁと思って百貨店へ行き、実際に買ったリュックとは別の第一候補として挙がっていたのは11000円くらいのものでした。
それなのに店員さんに「いくらなら即決できますか?」と言われて、「15000円ですかね」と即答していたのです。
もともと考えていた1万円と、店員さんに言った金額との間に「5000円」も開きがあったのです!
これ、おかしいの伝わりますかね?
つまり、これは、
「最初に提示するものが、次に提示するものへの相手の受け止め方を変えてしまう」
ということだったのです。
まだちょっとわかりにくいと思うので、詳しく説明します。「ミシシッピ川を長くしてしまった」実験があるんです。
■ミシシッピ川を長くする方法

大学生を対象にしたある実験で、実験参加者を2つのグループに分けて、片方のグループには紙に長い線を3本描かせ、別のグループには短い線3本を描かせました。
その直後にミシシッピ川の長さを尋ねたところ、なんと長い線を書いたグループの方が川の全長をより長く答えたのです!
初めて聞いた方はこの実験結果を信じられないかもしれませんが、
「最初に提示された数字や条件が基準となって、その後の判断が無意識に左右されてしまう心理」のことを行動経済学では「アンカリング」と言います。
このような驚くべき研究結果は他にもたくさんあります。
例えば、夕食に払ってもよいと思う金額は、店の名前が「スタジオ97」だと「スタジオ17」のときよりも高くなります。
また、行動経済学の第一人者であるダン・アリエリー教授は、社会保障番号というなんでもない数字がアンカーとして働くのかどうかを検証しました。
学生たちに自分の社会保障番号の下二桁を書いてもらい、その後、コードレスのキーボードにいくら払ってもいいかと尋ねたところ、下二桁の数字が大きい(80~99)学生の回答金額は高く、下二桁の数字が小さい(1~20)学生の回答金額は低かったのです!
社会保障番号というまったく無関係な数字ですらアンカーとして働いてしまっていたのでした。
もちろん、この実験に参加した人々は、社会保障番号の下二桁を書いたことが最終的な回答金額に影響を与えたと思うかと尋ねると、ありえないとあっさり一蹴していました。
しかし、恐ろしいことに現実は大きく異なり、最初に提示するものが、次に提示するものへの相手の受け止め方をいとも容易く変えてしまうのです。
■「1万円」と言わなかった理由とは

もやもやしたものが、やっと輪郭を帯びて現れてきました。
「なぜ僕は「1万円」と言わなかったのか?」
それは、
言わなかったのではなく、言えなかった
のです。
最初に提示された「2万円」という数字がアンカーとなってしまい、そこを基準に考えてしまっていたからです。
もし値札を見ていなかったら、言い値でと言われていたら、「1万円で」と答えていたはずですし、元からリュックの値段が「15000円」だったとして、いくらなら即決できますか?と言われていたら「1万円」と答えられたはずです。
ですが、今回「2万円」という数字がアンカーとなっていたため、そこから半額じゃないと買わないとはさすがに言いにくいですし5000円も安くなったらかなりお得じゃんと無意識で考えてしまい、「15000円くらいなら即決できますかね」と答えてしまっていたのでした。
冒頭でこれは何ヵ月も前の話だと書きましたが、なぜそんな前の話を今書いたかと言うと「あぁこれは行動経済学のアンカリング効果のせいだったのか!!!」とふと最近やっと気が付いたからです。
たまたま僕は知っていたから気付けただけで、社会保障番号が最終的な回答金額に影響を与えたと誰もが思わなかったように、知らないと気付くことはできません。
これを読んでいるあなたも今まで必ず何度も気付かないうちにアンカリングされた経験があるはずです。
(思い当たらないという方は気付いていないだけです。「これもアンカリングだったのか!」という具体例は本記事の最後に紹介しています)
なので、もし悪用されたくないと思う方は、何らかの数字が示されたら、それが「どんなものでもアンカリング効果を及ぼすのだ」と肝に銘じてください。
こんな恐ろしいこと悪用禁止で……
……と言いたいところですが、もし興味がある方は営業やビジネスの交渉の場で、一度、活用してみてください。
(例えば、まずありえないくらい高い金額を提示してみたりと、、悪用はいけませんが!)
うまくいけば驚くほど効果があることを実感でき、人間とはこうも不合理な生き物なのかと人間理解が深まるはずです。
すみません、人間理解がライフワークなもので。あー人間理解って楽しい!
今日も思考を整頓し、"もやもやしたもの"に輪郭をあたえていく。
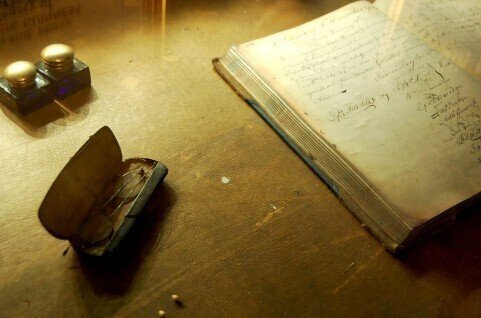
=====================
📖ここからは〝森井書店〟のお時間です📖
✏記事の内容に合った「10年後もあなたの本棚に残る名著」を3分でさくっと紹介するコーナーです✏(vol.2)
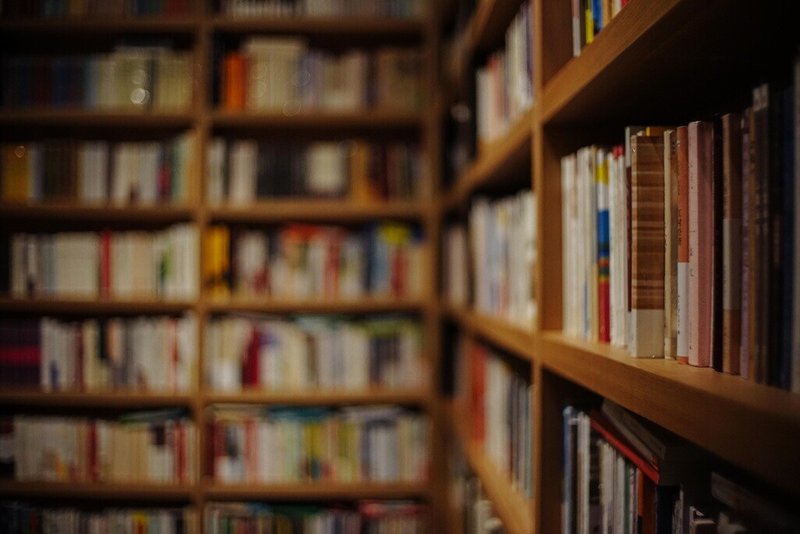
今回のテーマは「アンカリング」
アンカリングは「行動経済学」の主要テーマです。行動経済学の名著を一冊だけ読むとするならば……
やはりダン・アリエリー教授の『予想どおりに不合理』でしょう。わかりやすいのに深い、行動経済学の入門書にして決定版でもあるのが本書です!
自己啓発・ビジネス書にはどのジャンルにも、そのジャンルでNo.1の本があります。
例えば、「コミュニケーション」ならカーネギーの『人を動かす』、「強み」なら『さあ、才能に目覚めよう』、社会心理学なら『影響力の武器』、アドラー心理学なら『嫌われる勇気』といったように、何年も何十年も読まれ続けている奇跡のような名著が存在しています。
そして、発売から12年経ってなお、未だにこの行動経済学という分野で一番であり続けているのが、『予想どおりに不合理』です!
本コーナーである〝森井書店〟のコンセプトは、「記事の内容に合った、10年後もあなたの本棚に残る名著を紹介する」ですが、すでに10年以上残っているという意味でもばっちり合った一冊です。
_________

今回のテーマである「アンカリング」について、すでに本文で説明しましたが、ここでは「これもアンカリングだったのか!」という例をご紹介します。
大学の同じゼミに〝ナオト君〟というとても時間に厳しい友達がいました。
友達ですが、僕も一度遅刻したら怒られたことがあったくらいで、卒論のテーマも「時間」について書いていたくらいでした。
ある時、18時集合で待ち合わせをしていたら、あの時間に厳しいナオト君から「ごめんちょっと遅れる!」とLINEがきました。
「ナオトも遅れることあるんやなぁ」と、10~15分どこかで時間潰そうかなと思っていたら、遅れると言いながらもなんと「18時ジャスト」に到着したのでした。
「ナオトってほんまに時間厳守なんやな、すごいな」と言った記憶がありますが、
この僕の驚きも「アンカリング効果」によるものです。
18時15分くらいに到着するということがアンカーになっていたため、集合時間の18時ジャストに到着しただけで少し感動してしまっていたのでした。
同じ18時到着でも、アンカリングによってここまで評価が変わるのです。
_________
さて、もし行動経済学の本を読んだことがない人で、マンガから入りたい人は佐藤雅彦さんの『ヘンテコノミクス』がオススメです。
ちょっと余談なんですが、僕にとって行動経済学はかなり思い入れの強い分野でして。
というのも、浪人時代(2009年)、ちょうどnote代表・加藤貞顕さんの編集した『スタバではグランデを買え! ―価格と生活の経済学』の著者である吉本佳生さんが出演されていた「出社が楽しい経済学」というNHK番組を毎週楽しみに見ていたからです!
(見ていた方いますかね?)
「こんなに面白い学問があるのか!!!早く大学に入って勉強がしたい!!!」
と奮い立ち、頑張って受験勉強をしていたのでした。
行動経済学は、ダニエル・カーネマン教授が2002年にノーベル経済学賞を受賞したのをきっかけに一気に認知されていきます。
『予想どおりに不合理』が出たのは2009年とかで、2010年に僕が大学に入学してすぐ受けた心理学の授業で最初に紹介された本も『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』といった行動経済学の本でした。
また、ダニエル・カーネマンの名著『ファスト&スロー』が出たのは2012年で、この数年間、世間的にも行動経済学がとても盛り上がっていました。
それだけに『ヘンテコノミクス』が出版された時、「2017年にもなって今更なんで行動経済学?佐藤雅彦さんほどのあろう者がこすりにこすられたテーマいったな?」と正直思ってしまいました。(えらそうにごめんなさい!)
そしてもっと驚いたのがこの『ヘンテコノミクス』かなり売れたんですよ。10万部クラスのベストセラーです。
えー!と、今更このテーマで驚き、しかも売れてるのもびっくりして、すぐに読んでみました。
もうね、少しでも疑ってしまった自分が恥ずかしい。佐藤雅彦さんの良いところがこれでもかとふんだんに出ていました。
僕にとって佐藤雅彦さんは最も影響を受けたクリエイターの一人で語り出すととまらないのですが、
もともと佐藤雅彦さんは20年以上前に『経済ってそういうことだったのか会議』という竹中平蔵さんとの共著を出されているくらいで経済に興味があったのでしょう。
そしてもとは電通の超一流CMプランナーだったこともあり、人間の「認知」を知り尽くした鬼なんですよ。
例えば、マンガの名前の『ヘンテコノミクス』が素晴らしいですよね。
日本人ならアベノミクスを聞いたことがない人はいないと思うので、「~ノミクス」と聞くと、すぐに「経済が関係している」と想像できます。
そして「ノミクス」の前に「ヘンテコ」と付くことで、「人間のヘンテコな経済行動について書かれた本なのかな」と、瞬間的に認知することができます。
しかも語呂的にも聞いたらどこかちょっとワクワクして記憶に残って離れません。思わず読んでみたくなります。
『ヘンテコノミクス』というたった8文字だけで、これだけのことを瞬時に読者に認知させるこのネーミングセンス。さすが、認知の鬼!
ところで、僕は石川善樹さんという予防医学研究者の方もすごく好きでリスペクトしていまして、その方が去年から「しあわせとは、喜怒哀楽の調和である」をコンセプトにした『幸せの重心』というマンガの連載を始めたんですね。
いわば、行動経済学ではなくポジティブ心理学のマンガですね。
面白いので僕も読ませてもらっていますが、コンセプトは新しくて素晴らしいですが、ネーミング(と認知)という観点からいくと、
ヘンテコノミクス
幸せの重心
どっちが読みたくなるか、どちらが記憶に残るか、思わず手に取ってしまいたくなるかは一目瞭然なのではないでしょうか?
そして、それでいて、
「作り方を作る」
という現在の佐藤雅彦さんが掲げている使命。(ここでは、行動経済学を新しい表現方法に結びつけること)
普通の人が行動経済学をマンガにしたらこんな表現方法には絶対にできなかったであろう演出がいくつも出てきます!
「経済×認知×新しい表現方法」
という佐藤雅彦さんの最も強いところであるこの3点がうまく合わさってできたのが『ヘンテコノミクス』だったのです!!そらぁ、いい本になりますし売れますよ!!
ちなみに、『ヘンテコノミクス』の出版直前に偶然にもリチャード・セイラー教授が行動経済学でノーベル経済学賞を受賞したのでその追い風もあったのでしょうが、
ビジネス書業界では「読者は7年周期で入れ替わる」なんて言われています。
おそらく2009年に発売された『予想どおりに不合理』を知らない読者が2017年にはたくさん生まれていたというのがヒットの背景としてあったのではないでしょうか。
読者が入れ替わっていたのです。
昔から知っている僕にとってはこすられすぎているテーマでしたが、まだまだ馴染みの薄い層が新たに生まれていたのでした。
(もちろん内容が抜群に面白くて本に力があったからこそベストセラーになったはずですが!)
________
以上、2冊の書籍(と著者)を紹介させていただきました。
もう『予想どおりに不合理』読んだことがあるよって方は、続編の『不合理だからすべてがうまくいく』、そして『ずる:嘘とごまかしの行動経済学』もぜひ読んでみてください。
本書にはもっと詳細かつ多彩な実験内容が載っていて、相変わらずわかりやすくて、読みやすくて、深い!
続編では、ゴキブリを使った面白い実験があって……
……おっと、もう時間がきてしまいました。3分を余裕で過ぎてしまっていたので今日はこのへんでお開きとさせていただきます。森井書店が開けるのは3分間だけなのです。それではまた次回お会いしましょう。
無知から未知へ、いってらっしゃいませ!
=====================
■関連記事
「風俗嬢は彼氏にただでセックスさせるのか」
はてなブログの時に書いたものですが、当時かなりバズったやつです。行動経済学の話はやはりキャッチーで興味ある人が多いですね!
大学生の頃、初めて便箋7枚ものブログのファンレターをもらった時のことを今でもよく覚えています。自分の文章が誰かの世界を救ったのかととても嬉しかった。その原体験で今もやらせてもらっています。 "優しくて易しい社会科学"を目指して、感動しながら学べるものを作っていきたいです。

