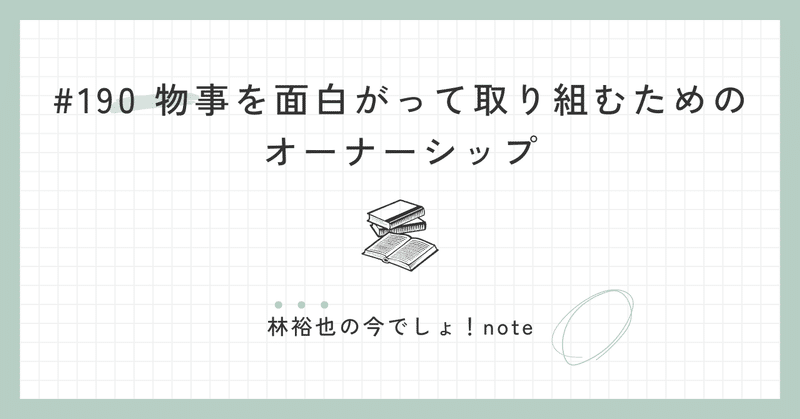
#190 物事を面白がって取り組むためのオーナーシップ
いかがお過ごしでしょうか。林でございます。
現在、木下斉さんとのコラボ新企画「ジブン株式会社RADIO」の検討を進めています。詳しくは以下記事でご紹介していますが、note記事で発信を続けている音声配信プラットフォームのリスナー同士で特定記事をテーマに1対1の対談放送を収録し、それをラジオ番組として提供してみよう!という企画です。
昨日、こちらの企画書に基づいて、今後の具体的な進め方について、木下さんとディスカッションする機会を持ちましたが、率直な感想としては「楽しかった!」というのがあります。
直後に頭の整理がてら木下さんと対談した時の学びを収録して配信していますが、今日は木下さんと共同で仕事をしていて、一定の緊張感を感じながらも「楽しい!」と感じる理由を深掘りしたいと思います。
この「一定の緊張感」と「楽しさ」の共存した感覚は、普段の生活や仕事の中でも感じることがあります。キーワードは「オーナーシップ」。会社のプロジェクトでも、やはりオーナーシップを持った人と物事を進める時に、同じような感覚を覚えます。
それらの経験とも掛け合わせながら「物事を楽しんで前向きに取り組み、成長するための根源には、常にオーナーシップ(当事者意識)が必要」という話を進めていきます。
ストレスない議論の秘訣は「テンポ」
昨日の木下さんとのやり取りもそうだったのですが、職場等でオーナーシップがある人との議論は、とにかくテンポが心地良いです。
逆に混乱させそうで申し訳ない例えですが、KinKi Kidsさんの「ジェットコースターロマンス」(なみは〜ジェットコースターの歌)を友達とカラオケで歌っている感覚に近いです。
堂本光一さんと堂本剛さんのパートが、あらかじめ青と緑の歌詞で一旦は分担されていて、基本的にはそれぞれの役割を全うするんだけど、時々重ねたりするような感覚。
もちろん、議論の台本があるわけではないのですが、自分が提示した論点に対して「それはこうしたらどうか?」と即答が返ってきたり、逆に相手から論点を示してくれたことが自分にとっての新たな気付きとなり、話を発展させる、という一連のコミュニケーションを、ポンポンとラリーできる感じです。
皆さんの生活や仕事を振り返ると「テンポが心地良い議論」がどれだけ溢れているでしょうか?
私の場合、もちろん全てがそうではなく「テンポが良くない議論や打ち合わせ」に遭遇することもままあります。
お客さんや職場の上司からあるお題が降ってきて「これに回答するためにどうしたら良いか」ということで、とりあえず関係しそうな人を一箇所に集める。そこでオーダーに対して1から説明して10分くらい経過。その後も、特に打ち合わせをセットした人自身のアイデアがあるわけではないので、いくつか論点が提示されるものの「こうしたらどうか?」と言い切れず、何となく煮え切らない。
呼ばれた側も、その打ち合わせの中で「自分が何を求められているのか」あまり理解しておらず、「その場で決定」することをせずに何となく誰も痛みがないよう
「この点は継続検討ですね」と決定を先送りにする・・・。
このような打ち合わせの成果は、「ある問題に対する関係者間で共有ができた」というくらいで、具体的なアクションプランが明確になっていないのであれば、わざわざ集まる必要はなかったようなものです。
集まってすぐに行われる問題に対する全文読み上げの説明部分も不要だと思います。
私の意見では、「読まれた文章を聞く」よりも「書いてある文章を読む」方がスピードが速いです。だから、仮にその場で初のアジェンダとなる人がいたとしても、説明者が資料の内容を一言一句読み上げるのをただ聞いているよりも、それぞれが文章を読み込んだ方が早い。
Amazon社内の会議で、冒頭5分間は出席者全員でペーパーの黙読に当てられる話は有名ですね。読めばわかることをわざわざ聞いているだけの時間は苦行だし、会議のパフォーマンス面でもマイナスが多いと考えます。
テンポアップに必要なのは事前準備
では、心地良いテンポを生み出すために何が必要なのか?と言うとやはり準備が全てだと思います。「短期的な準備」と「中長期的な準備」に分解して説明します。
短期的な準備
こちらは、特に会議のファシリテーター側に求められますが、事前に課題と具体的なアクションについてテキストにまとめ、関係者に展開しておくことです。ここで重要なのは、具体的なアクション部分を「要検討」などと言って逃げないこと。「要検討」は、厳しい言い方をすると、自分で検討・決定することを放棄しているということです。
自分で持ち出したアジェンダなのに、決定はお任せします!と他人に投げてしまう姿勢からは、オーナーシップは感じられませんね。その決定に関する決裁者が自分でなくとも「自分はこうしたい、こうするのがいいと考えている」の意思表示をすることが、オーナーシップを持ち、決裁者ではない人が発揮できるリーダーシップです。
日々の小さな意思決定の場面から、これをやる癖を付けないと最終的に困るのは自分だと思います。なぜなら、普段から「自分で決めて、その判断理由を言語化して他人に伝える」トレーニングをしていないと、ある特定の分野で自分が決裁者となった時に決められないからです。
本来「決める」役割にある人が「決められない」となると、マネジメントは崩壊します。
これは間違った意見を言うことより、はるかに致命的です。間違っていてもいいから、自分の意見とその理由を言語化する。脳に負担をかけるので「要検討」で逃げたくなる気持ちはよく分かりますが、「自分の頭で考える」ことに向き合わないと永遠に成長はありません。
中長期的な準備
打ち合わせのアジェンダについてどんなに用意をしてきても、カバーできない論点に話が及ぶこともあるでしょう。また、昨日の木下さんのファシリテーションのように、ある観点をより深掘りするための新たな議題の提示は、その場で即興でできるわけではありません。
ここで重要なのは、日々の知識や考え方のストックです。昨日の対談の中でも話に上がった通り、「いいね、コメント(=リアクションして一言自分の意見を述べる)」は、「あなたはどう考えますか」を日々インタビューされているのと同じですよね。
あるトピックについて「瞬発的に言語化して返す」能力は、正確に言えば「過去に自分の頭の中で言語化したことがある情報を脳内インデックスを検索して引っ張ってくる」ことだと思います。
そのために、普段から様々なテーマに対して「自分なりの意見」を言語化してストックしておくのが大事です。
全てはオーナーシップが根底にある
ここまで述べてきた話は、あらゆる物事を面白おかしく取り組み、会社名や役職ではなく「一人の人間としての看板」で生きていくための秘訣だと考えます。
そして、これらを実行するためには「オーナーシップ」を持つこと。
オーナーシップ持って物事に取り組むのは、そうした方が周囲への価値貢献が大きくなるという面もありますし、何より自分自身が人生をより楽しめるようになることが、最も大きな恩恵だと考えてます。
私もオーナーシップを持った発信活動を通じて、より人生を楽しくしていけるよう邁進してまいります!
それでは、今日もよい1日をお過ごしください。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
もし面白いと感じていただけましたら、ぜひサポートをお願いします!いただいたサポートで僕も違う記事をサポートして勉強して、より面白いコンテンツを作ってまいります!
