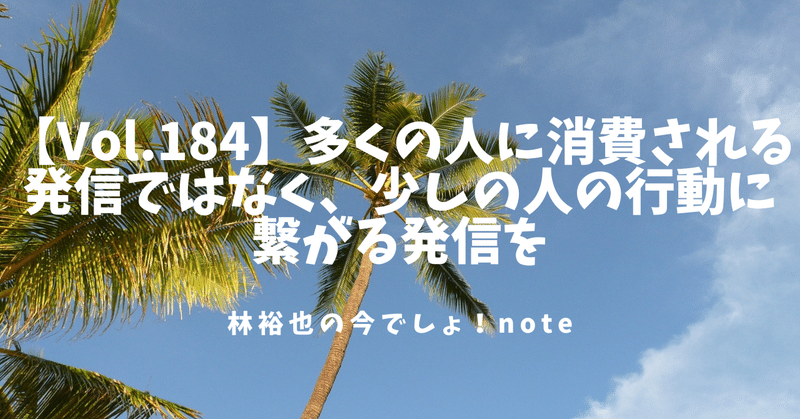
#184 多くの人に消費される発信ではなく、少しの人の行動に繋がる発信を
いかがお過ごしでしょうか。林でございます。
※本記事は、音声でも解説しています。
5/10(日)のYahoo!ニュースで取り上げられていた記事に対して、木下斉さんが「エモい記事に流されるな!」という趣旨の話をされていました。
取り上げられていた記事はこちらになりますが、「財政非常事態宣言」を発出するに至った町で、地元企業や高校生が地域活性化のために頑張っています!という趣旨の記事です。
これに対して、日本大学危機管理学部教授の西田亮介さんが「PV稼ぎの寄り添い型の記事にどれほど意味があるのか?」という趣旨のコメントをされていて、本当にその通りだと共感しました。
一見美談だが、「収入が減少することはわかっていながら、支出削減は全く取り組めていない結果の財政非常事態宣言」であるというとき、民間における活性化の独自の取り組みは問題解決にいったいどの程度寄与しているのだろうか。また公共施設などの大規模閉鎖等の「大胆な歳出削減」は新規の転入者誘致という点ではマイナスに働くのではないかなど、この手の記事はよく読むと疑問が少なくない。最近は「寄り添い」型の記事がpvを稼げるナラティブ型記事やエモ記事などとともに持て囃されがちだが、メディアは原点にあたる批判的視線も忘れないでほしい。
これは一例に過ぎず、このような「エモい記事」は日常に溢れています。地域の個別の活動を取り上げて、それが実際にどのような効果に繋がっているのか、ハテナが浮かぶ情報です。
多くの予算が割り当てられ、関係者は盛り上がっているかもしれないけれど、地域活性化の根底にある経済活動の活性化・成長にどれだけ寄与しているのか不明な事業。このような事業は、効果が測定されにくい分、良いともダメとも言えないという性質があります。
発信者側としては、PVが稼げるから、いいね!が稼げるからと、多くの人にストレスなく受け入れられる情報に寄せてしまいがちです。
私のように個人で発信している人にとっても、常に気をつけていないと、すぐに「読みやすいが、何も言っていない発信」に陥る危険性があります。文章を書くことの本来の目的を見失ってしまうのが怖いので、自身の見解をまとめておきます。
PVばかりに着目しているのは、売上至上主義と同じ
強く思うのですが、PVやいいね!の数というのは、情報発信の一つの側面からの結果に過ぎないです。
大事なのはやはりコンテンツの独自性とオピニオンで、「その人ならではの発信か?」、「その人の発信を受けて、共感して行動する人がいるか?」だと思います。
「その人ならではの発信を通じて、共感し行動する人が増えた結果として、PVも伸びる」であれば良いのですが、物事の順番というのは非常に重要です。
手前の目的が、PVという「広く見られること」に置かれた瞬間に、そこに至る手段が「広く見られるためにはどうすれば良いか?」に置き換わってしまい、独自性の要素が無視されてしまいます。
私は、企業にとっての「売上」は、「目標」にはなり得ても「目的」になることはないと考えています。実際、「売上目標」という言葉はありますが、「売上目的」とは言わないですよね。
外の人から見て、どれだけの価値を提供できたか。事業を通じて、その事業からの利益を享受するユーザーがどれだけ喜び、社会や地球環境にとってどれだけのベネフィットをもたらしたか。ここに企業の存在意義があります。
「売上」は、世の中から企業の存在意義や事業内容が評価された結果として付いてくるもので、「売上」そのものを目的化してしまうと「売上」を上げるためには何をしても良いとなってしまい、本末転倒になるのです。だから順番が大事。
PVも同じだと思っていて、コンテンツが持つ「独自性あるオピニオン」に共感する人がいて結果として伸びてくるもので、はじめから「どうPVを稼ぐか」が目的化してしまうと、「PV稼げれば何やってもいい」となる。だから、PVやいいね!の数ばかりに着目すると、表面上の数字は伸びているものの、より本質的なところにある「その人と一緒に何かやってみたい、協力したい」という信頼は何も積み上がらないということになってしまいます。
「消費」ではなく「行動」や「変化」に繋がる発信を
私も「にゃんこ大戦争」や「Candy Crash」などのようなスマホゲームにかなり夢中になっていた時期があるので分かるのですが、疲れていたりすると脳が考えなくても済む「消費」するコンテンツを選びがちです。そして、少しでも空き時間があると、手が勝手にスマホゲームを選択してしまうくらい、中毒性がある。
でも、せっかく時間を作って日々発信をしているのであれば、自分のオピニオンを盛り込み、自分がこういうことを伝えたい、という想いを軸に発信したいです。
多くの人にただ「消費」される情報ではなく、読んでくれる人は一握りかもしれないけれど、「強く刺さり、その人の行動を前向きにして、小さくても何らかの変化をもたらす」情報に拘りたいと考えています。
私の場合は、やはり「人生=なんとなく時間を消費しながら過ごすもの」、「仕事=我慢料としてお金を受け取るもの」、「管理職=罰ゲーム」というポジティブとは言えない雰囲気を、せめて自分の身近な環境だけは変えたいという気持ちで書いています。
だから、30代子育て現役世代が考える、人生を豊かにするための考え方や行動、自分がマネジメントに携わって感じているリアルをコンテンツの軸に置いています。
私は、誰とも知らない1000人にただ消費される発信よりも、1人の強く共感してくれるファンがいてくれる方が嬉しいと感じます。
アウトプットすることで、様々な物事に対する構造的な考え方を鍛え、インプットの質を高める。毎日書いているとつい忘れがちですが、文章を書くと決めた当初の目的を見失わないようにしたいです。
受信側リテラシーも大切
山口周さんの「劣化するオッサンの処方箋」に、以下のような趣旨の話が出てきます。
二流は、自分が二流であり、誰が一流か知っている。
一流は、人を格付けしたり、人を押しのけて権力を握ることに興味がないので、そもそも自分や他人が何流か考えない。
三流は、周囲にいる二流を一流と勘違いして、自分も、今は二流だが頑張ればああなれると考え、二流をヨイショ、周囲をウロチョロする。本物の一流はよく分からない人たちと考えている。
世の中は、三流が数としては圧倒的な多数派。そのため、構造的に最初に大きな権力を得るのは、大量な三流に支持される二流。「数の勝負」に勝とうと思えば、三流に受けないとダメ。資本主義が不毛な文化しか生み出せていない決定的な理由はここにある。
かなり厳しい指摘で、耳が痛いです。
でもこういった本質的な指摘に向き合わないといけないのだと思います。
今日の話に当てはめると「エモい情報、PV稼ぎの煽り情報を選びとっているのは、多くの三流である」という話になるのかなと。
私も情報の受信側として、気を付けないといけないところです。発信する側の意識だけでなく、情報を選ぶ側のリテラシーが重要。
多少難しくても噛みごたえのある「骨のある情報」を選び取っていくこと。
自分自身が情報を選ぶ立場においても、「易きに流されず」のスタンスが大切なのだと考えます。
それでは、今日もよい1日をお過ごしください。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
もし面白いと感じていただけましたら、ぜひサポートをお願いします!いただいたサポートで僕も違う記事をサポートして勉強して、より面白いコンテンツを作ってまいります!
