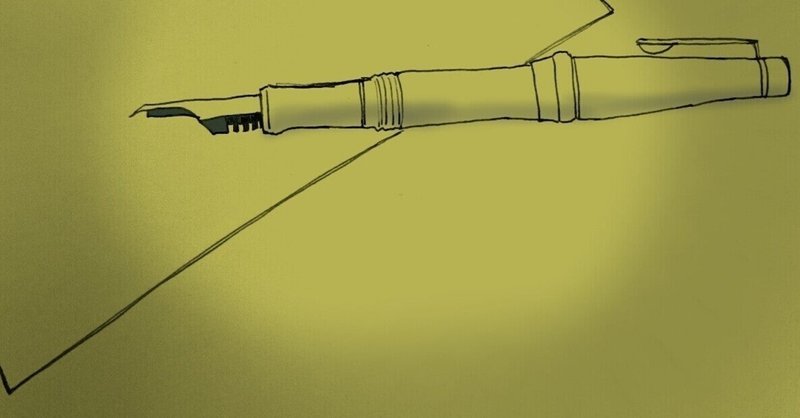
自分が言いたいことを短くまとめて、インパクトを出す手法について
昔、勤めていたコンサルティング会社では、自分が読んだ本を発表するという場があった。
その時、一番むずかしいな、と思ったのが、「その本を読んだことのない人に、どうやってその本の内容を端的に伝えればよいのか」だった。
読書会などであれば、基本的には参加者がその本を読んできているので、意見を述べるときに、自分の感想から入っても問題はない。
あるいは、webで書評などを書くときであれば、その本がどのようなものなのか、ネットで調べればすぐにわかる。
ところが「発表」という場では、そういうわけにはいかない。
時間は5分程度と限られているし、その本について、あるいはその本が扱うテーマについて、まったく無知の人もいる。
その場で「ネットを見てください」というわけにもいかない。
だから、「本の内容を一言で説明すること」に心を砕かなければならなかった。
最初の1ページで説明する
コンサルティング会社で働く前は、大学の論文やレポート同様、報告書や調査書などは、さぞかし部厚いものが好まれるのだろうと思っていた。
だが、実際は全く逆で、分厚いものは敬遠された。
というより、文が長い、話の長いヤツは無能とみなされた。
とにかく端的に、結論を、短く、だが、過不足のない説明を求められた。
それと同様に、提案書や企画書なども、「最初の1ページ」で、短く説明することが求められた。
企業経営者は忙しい上に、短気な人も多く、冗長な説明は好まれない。
したがって、要点だけをかいつまんでプレゼンテーションし、YES/NOを素早く判断してもらわねばならなかった。
これらは、場合によっては大変なストレスだった。
というのも、「言いたいことを一言で」は、想像以上に難しい行為だったからだ。
「あらすじ」と「言いたいことを短くまとめてインパクトを出す」は似て非なるもの
このように言うと、例えば本では「あらすじでしょ?簡単だよ」と言われる方もいる。
あるいは、報告書や論文も「要旨(=アブストラクト)」を書くようなものでしょう?と仰る方がいる。
だが、それは見当違いだ。
「言いたいことを短くまとめる」と、「あらすじ」や「要旨」は似て非なるものだ。
一体何が違うのか。
それは「あらすじ」や「要旨」が、主として「内容の理解」を優先したものであることに対し、「一言にまとめる」は、「行動させる」「感動させる」を目的としたものである点だ。
目的が「内容の理解」ではないが故に、「言いたいことを一言でまとめる」技術は、要約の技術ではない。
行動させたり、感動させたりするためには、「全体を説明する」のではなく、「インパクトを出す」ことに主眼が置かれる。
そのための技術が、「一言でまとめる」だった。
「行動させる」「感動させる」表現の例
だから、理解を目的とした表現と、行動や感動を目的とした表現は、まったく異なる。
例えば「本」の紹介をするときに、「あらすじ」を説明することと、「その本を読みたくなる」ように仕向けるときでは、まったくやるべきことが異なる。
あらすじは、物語の要点を、本の前から順を追って紹介しなければならない。
だが、それに対して「読みたくなるような紹介」は、聴衆のニーズに合わせて、順序も要点も変化する。
例えば「ビブリオバトル」をご存知だろうか。
ビブリオバトルとは、書評を述べ合い、一番「読みたくなる紹介」をした人物が勝つというゲームだ。
<ビブリオバトルとは>
「ビブリオ」は書物などを意味するラテン語由来の言葉で, 「ビブリオバトル」とは,立命館大学情報理工学部の谷口忠大教授が考案した,ゲーム感覚を取り入れた新しいスタイルの「書評合戦」です.ビブリオバトラー(発表者)たちがおすすめ本を持ち合い,1人5分の持ち時間で書評した後,バトラーと観客が一番読みたくなった本,「チャンプ本」を決定します.
ポイントはそのルールにある。
ビブリオバトルは、レジュメや資料などを配布できず、5分のプレゼンテーションのみで、紹介する本の面白さを伝えねばならない。
<ビブリオバトルのルール>
ルールはとてもシンプルです.
ビブリオバトラー(発表者)はそれぞれお気に入りの本を持ち寄ります.
ビブリオバトラーは読んだ本について、スライドやレジュメは一切使わず,自分たちの言葉で5分のプレゼンテーションを行い,本の面白さを伝えます.
プレゼンテーション終了後は2~3分間,他のバトラーや観客から質問を受け、本の内容や発表者の思いについて理解を深めます.最後に会場にいるバトラー,観客全員で「どの本が読んでみたくなったか?」を基準に多数決 し,一番読みたくなった「チャンプ本」を決定します.
これはなかなか難しい注文である。
本の「面白さ」を伝えきるのに、5分はあまりにも短いからだ。
無論、あらすじを追いかける時間はない。
では、どうやって本をプレゼンテーションするのか。
ここから先は

生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書
ビジネスマガジン「Books&Apps」の創設者兼ライターの安達裕哉が、生成AIの利用、webメディア運営、マーケティング、SNS利活用の…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
