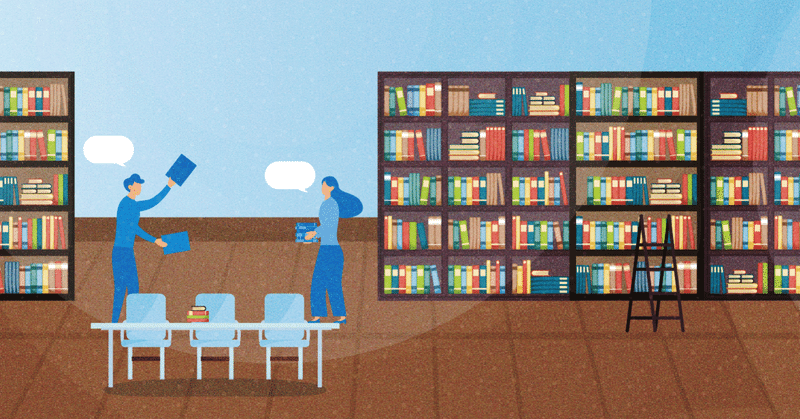
育児書のマネをしたら息子が予想外の行動をした
「勉強しろと言ったことないのに子どもがよく勉強する」そんな体験談を見聞きし、目指したいなーとぼんやりと思いながら、3人の子どもと過ごしてきました。子育て本も数多く読み、良い部分は取り入れ、取り入れようとして失敗したり、また本を読んだり‥。
そんななか、数年前にギフテッド認定を受けカナダの大学に14歳で入学した大川翔さんのことを知りました。こういう子はどう育ったんだろう?と興味がわき、お母さんの大川栄美子さんが書いた著書を読みました。そこから実践したことを紹介します。
教科書を全学年揃える!?
「とにかくたくさん本の読み聞かせ」
「外国人のシッターを雇い、遊んでもらいながら英語の本の読み聞かせ」
など実体験が数多く紹介されていましたが、読んですぐに真似をしたことがありました。
「小学校の教科書を全学年分揃える」
これです。大川さんは、今後子どもがどんなことを学ぶのか、見通しを立てるために揃えたと書かれていました。私は結局それほど読み込むことはありませんでしたが、教科書を家の本棚に並べていました。
トリックアートブームの息子たち
長男が小学2年生、次男が年長の頃「トリックアート」にハマっていました。トリックアートは、だまし絵のこと。折り紙を繋げて作る「メビウスの輪」など、数学的要素があるんですよね。算数の教科書の表紙にトリックアートのような絵が描いてあるのをたまたま見て、「トリックアートだーーー!!」と小2、年長男の息子たちが熱狂。
「おお、本当だ。トリックアートだ!!」私は多くは語らず、驚いてみせます。そこから算数の教科書をパラパラ眺めていた長男。
私は赤ちゃんだった末っ子と寝落ち‥。
翌朝起きると…
「単位換算尺」ができあがっていました。
小6の教科書に載っていたものを、小2が作っていたのです。これには驚きでした。長男は教科書を見て面白そうと思い、工作をする感覚で作り上げたようです。使い方もバッチリ。学校へ持参して、色々なものを測って楽しんでいました。
長男は数字が好き
教科書を置いたらみんながみんなこの行動を取るんだ!というわけではないと思います。ただ、たまたまトリックアートが好きで、たまたま工作が好きだった。子どもがすぐ工作できるように、工作用紙、画用紙、工具などを手に届く場所に置いていた。
そして長男は昔から数字が好きで「算数図鑑」などを眺めるのも好き。こういう点と点がつながっての出来事でした。
子どもを観察して環境を整える
「あれしなさい、これやりなよ」と押し付けないで、環境を用意しておく。「あ、あれやりたいな」と思ったときにできるように揃えておく。10年の子育てでなるべく心がけようとしてきたことです。(工作グッズなどあふれて整頓できていないのが悩みではありますが‥クリエイティブだ!と言い聞かせています)
振り返れば、長男は1歳で鉄道にハマり、3歳になると鉄道絵本や図鑑を見て文字を読み始めました。幼稚園での作品は全て鉄道がらみ。小2の終わりで転校したときにクラスメイトからもらったメッセージ集にはめくれどもめくれども鉄道のイラストが。
とまあ、こんな感じで長男が特にわかりやすかったのも大きいかもしれません。子どもの好きなものを一緒に楽しむと、親子ともに思わぬ発見があります。もし今、鉄道や昆虫、お姫さまなど、その子が夢中になっているものがあったら、その世界にどっぷりつかってみると、新しい世界が見えてくるのかもしれません。
さいごに
『電車が好きな子はかしこくなる』弘田陽介 交通新聞社
こちらの本も読みました。電車が好きな子は、社名や車両の違いなどの知識を覚える『認知能力』を伸ばしながら、イベントを企画したり、路線図を見ながら計画を立てたりして『非認知能力』も育む、といったことが具体例も交えながら紹介されています。
電車好きに限らず、子どもが何かにハマったらどう一緒に楽しむか、という視点をもらえる本です。
育児本を色々読みましたが、実践できたり、できなかったり。近ごろは漫画とマイクラに夢中な息子たちですが、たまにはこういうおおっと思う出来事があるものですね。なるべく、夢中な姿を見守りたいなあと思いながら、今日も「部屋がきたない!」など、ブツクサ小言をつぶやいてしまうのでした。
サポートとても嬉しいです!!子どもたちとの体験や書籍など執筆に活かせる体験に使えればと思います。シェアやコメントもすごくすごく励みになります!
