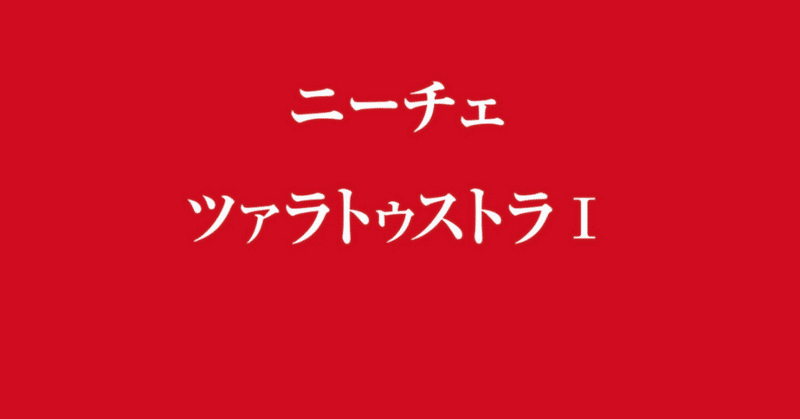
ニーチェ「極限的な肯定」
ニーチェは、苦悩や罪、過去にあった一切のことに対して「肯定」します。彼はその肯定を「巨大な無際限の肯定」「到達しうるかぎりの最高の肯定」「極限的な肯定」と表現しています。さらに、「永遠の然り」「何一つ無用なものはない」とも述べています。しかし、ニーチェの「肯定の哲学」は、すべてのものを肯定するわけではありません。彼は、「よろず満足家」ではなく、選り好みの強い人間です。また、自分自身および自分の行為を 「よい」と感じる「高貴な人間」なので、「然り」と「否」、そして「私は」という意志をはっきりと示します。
───────────
流れる雲が、私には憎たらしい。こっそり忍び寄るこの泥棒ネコめが。やつらはあなたと私から、私たちに共通するものを盗む。──途轍もない無際限の肯定(ヤー)と承諾(アーメン)の発話を。
森一郎訳「日の出前」
───────────
自分があらゆる事物に対する永遠の然りであり、「巨大な無際限の肯定と承認」であるということの根拠を、どうしてそこに見いだしているのか、という問題である・・・・・・ツァラトゥストラは言っている。「どんな深淵の中へも、わたしは、わたしの祝福する然りのことばを運ぶ」と・・・・・・。 しかしこれもまたディオニュソスの概念そのものなのである。
『この人を見よ』「ツァラトゥストラ」
───────────
さていよいよ『ツァラトゥストラ』の歴史を物語ることになる。この作品の根本着想、すなわち永劫回帰思想、およそ到達しうるかぎりの最高のこの肯定の方式は──
『この人を見よ』「ツァラトゥストラ」
───────────
あふれる豊かさから生まれたあの最高の肯定の方式、つまり、苦悩や罪、生存におけるあらゆるいかがわしいものや異様なものに対してさえ留保なしに「然り」という態度、この二つのものの対立である・・・・・・こうした窮極的な、この上なく喜びにあふれた、過剰なまでに意気盛んな生命肯定は、単に最高の洞察であるばかりでなく、これはまた、最深の洞察、真理と学問によって最も厳正に是認され、支持されている洞察なのである。およそ存在するものであるかぎり、何一つ排除してよいものはなく、何一つ無用なものはない──
『この人を見よ』「悲劇の誕生」
───────────
過去に存在したものたちを救済し、いっさいの『そうであった』を『わたしはそう欲したのだ』に造り変えること──これこそはじめて救済の名にあたいしよう。
手塚富雄訳「救済」
───────────
ところが『悲劇の誕生』が承認する唯一の価値は美的価値なのだ。キリスト者は、もっとも深い意味でニヒリスティックである。それに反して、この書においてはディオニュソスという象徴によって、極限的な肯定が達成されたのだ。
『この人を見よ』「悲劇の誕生」
───────────
『曙光』は肯定の書である。深い、しかし同時に明るくて、寛大である。同じことはもう一度、しかも最高の程度において、『たのしい知識』について言える。この書の中のセンテンスのほとんどどれを取ってみても、そこには深い思いと茶目っ気とがねんごろに手をとりあっている。
『この人を見よ』「たのしい知識」
───────────
ツァラトゥストラはある箇所で厳密に彼の使命──それはまたわたしの使命だ──を規定している、だれもその意味を取りちがえることがないためにだ。すなわち、彼は、過去にあった一切のことまでも是認し、救済するほどに、肯定的なのだ。
『この人を見よ』「ツァラトゥストラ」
───────────
私は、どんなものでも善いと言い、この世界を最善の世界だとすら言い募る者たちも、好きではない。そういう連中を私は、よろず満足屋と呼ぶ。
何でもおいしくいただくことのできるよろず満足嗜好は、最高の趣味などではない。私が敬意を払うのは、「私は」と言い、「然り」と「否」を言うことをおぼえた、強情っぱりで、選り好みの強い舌と胃である。
森一郎訳「重さの地霊」
まことにわたしは、すべてのことをよしと言い、さらにはこの世界を最善のものと言う者たちをも好まない、この種の人間をわたしは、総体満足家と呼ぶ。
あらゆるものの美味がわかる総体満足、それは最善の味覚ではない。わたしは、強情で、気むずかしい舌と胃をたっとぶ。それらの舌と胃は、「わたし」と「然り」と「否」ということばを言うことを習得しているのである。
手塚富雄訳「重さの霊」
そうだ、わたしは好まない。何もかもがそれぞれに良いと言う者を、さらにこの世界が最善だという者を。わたしはこういう者を、何でも満足屋と呼ぶ。
何でも安易に満足するのだから、何でも美味しく食べることができる。これは最高の味覚ではない。わたしは従順ではない、選り好みがつよい舌と胃を尊ぶ。「このわたし」と「諾(ヤー)」と「否(ナイン)」を言うことを心得ている舌と胃を。
佐々木中訳「重さの霊について」
───────────
同時にこの書(『善悪の彼岸』)は、可能なかぎり近代的でない対立的典型を指し示している、すなわち高貴な、肯定的なタイプの人間を。この後者の意味において、この書は貴族の学校である。
『この人を見よ』「善悪の彼岸」
───────────
すなわち、「よい」という判断は「よいこと」を示される人々の側から生じるのではないのだ!却って、「よい」のは「よい人間」自身だった。換言すれば、高貴な人々、強力な人々、高位の人々、高邁な人々が、自分たち自身および自分たちの行為を 「よい」と感じ、つまり第一級のものと決めて、これをすべての低級なもの、卑賤なもの、卑俗なもの、賎民的なものに対置したのだ。
『道徳の系譜』「第一論文」
───────────
【引用】
手塚富雄訳『ツァラトゥストラ』(中公クラシックス)Kindle版
森一郎訳『ツァラトゥストラはこう言った』(講談社学術文庫)Kindle版
佐々木中訳『ツァラトゥストラかく語りき』(河出文庫)Kindle版
木場深定訳『道徳の系譜』(岩波文庫)
手塚富雄訳『この人を見よ』(岩波文庫)Kindle版
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
