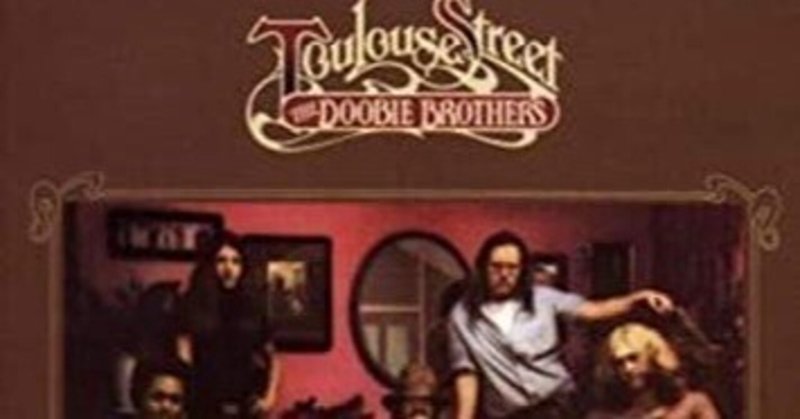
The Doobie Brothers「Toulouse Street」(1972)
いよいよ明後日にせまってきたドゥービー・ブラザーズの東京公演。日本ツアーは今日から、盛岡からスタートですね。先週行われたオーストラリア公演のセトリを見ると、全25曲、トム・ジョンストン時代からマイケル・マクドナルド時代まで、かなりバランスの取れた選曲のようです。ドゥービーの中心人物だったトム(前期)とマイケル(後期)が揃って来日するのは初めてらしい。というか最初で最後でしょうね…。個人的にはゴスペルから影響を受けたと云われている「Takin' It To The Street」が、今の下のアップした映像で演奏されるのか、凄く楽しみです(エンディングにかけてのグルーヴ感が半端ない)。
ということで今回はドゥービーの大ヒットしたセカンド・アルバムをチョイス。マイケル・ホザックが加入してツインドラムとなったドゥービー。それから忘れてならないのは、このアルバムの製作途中から加入したベースのタイラン・ポーター。ドゥービーの腰の据わったリズムは、タイランのベースが効いていたと思います。

セカンドアルバムにて名盤、このジャケットも有名ですね。プロデュースはお馴染みテッド・テンプルマン。
オープニングの超名曲にしてドゥービーの代表曲でもある①「Listen to the Music」から心を掴まれます。
トム・ジョンストンとパット・シモンズの軽快なギターワーク。豪快なコーラスとリズム隊。アップした映像には怪しげなギタリスト、ジェフ・バクスターが映ってますね。彼は次作の「The Captain And Me」からアディショナル・メンバーとして参加し、1975年発表の「Stampede」から正式メンバーとして加入してます。
①よりも大好きな②「Rockin' Down the Highway」。こちらもトム・ジョンストンの名曲。このスタジオ録音バージョンはツインドラムながらも、なんか軽い感じがするんですよね。それに比べてアップしたライブ映像、2018年の演奏ですが、よりシャープでタイトな演奏になっているような気がします。トムの声も変わらないし、凄く厚みのある演奏で、グルーヴ感がいいですね~。ジョン・マクフィーも加わったトリプル・ギターだからでもありますね。今回のライブでも演奏される筈ですが、この演奏にマイケル・マクドナルドが加わると想像するだけでワクワクしてきます。
アルバムタイトル曲でもあるパットのフォーキーな④「Toulouse Street」。かなり地味な楽曲ながらも味わいある楽曲です。トムとパットのタイプの異なる楽曲の組み合わせが初期ドゥービーの大きな魅力でした。この路線の延長線上に、後にドゥービー初の全米No.1ヒットとなったパット作の「Black Water」があります。
2018年のライブ映像をアップしておきましがが、チェロがいい味出してます。そしてそのチェロを弾いているのはなんとジョン・マクフィー。ジョンはドゥービーには1979年に加入したメンバーですが、日本では矢沢永吉をプロデュースした人物としても知られてますね。今回の来日公演にも参加してますが、実に多彩なミュージシャンです。
シールズ&クロフツのセカンドアルバム「Down Home」に収録されていた⑤「Cotton Mouth」。こちらをドゥービーが本来持っていたファンキーな要素をベースに大胆にアレンジしたもの。
シールズ&クロフツのオリジナルバージョンは、かなり怪しげな雰囲気の地味なナンバーです。このオリジナルを聴くと、ドゥービーの解釈はなかなか凄いなあと感じます。このオリジナルから、よく陽気なファンクナンバーに仕立てるという発想が沸いたなあと感心させられます。トム・ジョンストンのアイデアでしょう。あとドゥービーがシールズ&クロフツの楽曲をカバーしていた事実はちょっと意外。同じウエストコースト出身で、交流もあったのでしょうかね。
⑦「Jesus Is Just Alright」をドゥービーのオリジナルの曲を勘違いしている方も多いかもしれません。実はこの曲、The Art Reynolds Singersが1966年に発表したものがオリジナルです。当時はゴスペルタッチな曲として発表されました。
これを1969年にバーズがサイケロックとしてアレンジ。こちらは「Ballad of Easy Rider」に収録されてます。更にそれをドゥービーが発展させていったという流れなんです。間奏のバラード調に転換するところなんかは、ドゥービーらしさが溢れてます。完全にドゥービーのオリジナルって感じですよね。これもライブで見れそうなので楽しみです。
ファーストこそ地味な印象のドゥービーでしたが、このセカンドではトムとパットのそれぞれの個性が発揮された楽曲のバランスが良く、またカバーも絶妙なアレンジで、バンドとしての個性が結実。以降、大活躍していくドゥービーなのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
