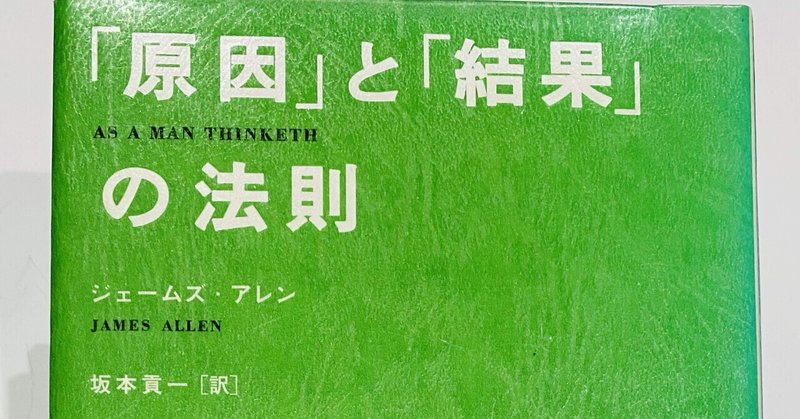
#8『「原因」と「結果」の法則』を読んだ感想
もし思考が極端な人がこれを読んだなら、ムカついたり、自分を責めたり、あるいは自分を恥じて頑張りすぎて心や人間味を失う気がします……。😅少なくとも、病期になる前の私が手にしていたなら、とても読んではいられない本だったと思います。笑
とても面白い本でしたよ✨
この本は、120年以上前にジェームズ・アレンという方により書かれた本です。自己啓発本の先駆けのようなものでしょうか。冒頭にこんな言葉が置かれていました。

あなたの置かれている状況は、あなたが作り出したものなのですよと、そのようなことが書かれています。今幸せに包まれて生活を送る人にはますます豊かな感情を与えるでしょう。ですが、今どうしようもない状況に置かれ苦しんでいる人がいたならどうでしょうか。それが自分のせいではないなら尚更です。この言葉に拒否反応があるのではないかと思います。実際、虐待される役を引き受けていた私のパーツは怒っています。到底受け入れられない言葉ですね😅私のせいではないのですから。
本の内容としては、とても単純でした。先の言葉の意味について、繰り返し、繰り返し様々な角度から書かれていました。あなたが心から思えば、それがあなたを変えるきっかけとなりますよと、それは変えられぬ、決められた法則であり、これは真理なのですよと、ただひたすら説いていました。ただ単に読むのは簡単だけど、理解するのが難しかったです。
面白かったのは、“この真理が分かる人間と分からない人間の違い”をあまりにも爽々と独自に書いてあるところでした。本当のことは口にしてはいけないなどと言いますが、そんな感じで、ほとんど悪口みたいで、清々しいほどはっきり書くので、そういうギャグみたいで面白かったです。笑
私の中に、この本を淡々と読むパーツと、ギャグに見えてしまって面白がるパーツと、素直に理解しようとするパーツと、拒否反応を起こすパーツがいました。拒否反応を起こすのは、自分が悪く言われていると勘違いしているからです。それは何故かなと深堀して考えていました。
人生では、アドバイスをもらった時に、それができるならとっくにやってるよという事とか、自分の力不足を感じる事などがありますし、そもそもそんなに自分優先にばかりは考えられないですよね。不器用に、でも懸命に考えて生きているというか。私は、そういうところの不器用さに人間味があるんじゃないかなと思うんです。何もかもうまくやろうなんて、むしろ傲慢ですからね。
でもこうも思います。今の境遇の全てが環境のせいではなく自分で作り出した物なのだよというメッセージ、今起こっていることはそういう法則に元付いているのだよというそのメッセージは、全く理解できない訳ではありません。
私は私に『自分のなすことは自分で決めて行いたい』そう言い聞かせていますが、それと同じ事を言っているのだと思ったのです。
私は私の行動を、好きなものを、嫌いなものを、自分で決めていいと知ったのは、病気になってからでした。ずっと母の洗脳下にあって、私が私ではない心で生きていたことを、前は悔しかったです。でも今は嬉しいです。自由になったことが理解できたのですから。もう私は、やりたいことも、やりたくないことも、自分で決めていいのです。やりたくないけどやらなくてはならないことも、私が決めていいのです。他人が決めたことだと思うと、何故かうまくいきません。不思議なものです(この不思議のことを、原因と結果の法則が働いたからだと説いているのですね)。私は今、この生活をすることを自分で決めています。やむを得ず起こることにはただそっと寄り添います。抗っても、誰かのせいにしても、なにもうまくはいかないのです。逆に、自分でそれに付き合うと決めたならば、うまくいかないと思っても、実は少しずつ求めるものに近づいていると感じるのです。だから、目先のことに囚われなくてよくて、やはり自分で決めたことは、長い目で見た時に、プラスにしかなっていないと思うのです。
話は変わりますが、私は無宗教ですが仏教や禅の教えが面白くて好きです。だからと言って仏教徒になろうとは思わなくて、思うのはこのやり方良さそうだしパクっちゃお、という感じのことです。一つの方法として自分のものにしちゃおうみたいな。都合よく使っちゃおうみたいな。私はこの本も同じだと思いました。
仏教の教えって、邪念を捨てていったら生きやすく幸せなるよみたいな感じだと思うのですけど、お坊さんたちってそれを修行するんですよね。それで、昔のお坊さんは山籠りして本当にそのまま仏様になったりして。仏教の教えの果ては、仏になることで、それってつまり人間じゃなくなることだと思うんですよね。だから仏教徒がもし本気で仏教の教えを究極まで突き詰めていったら人間じゃなくなるということだと思うのです。あるいはそれは、命を終えた時です。仏教徒が生きている間に全員仏になりたいですかって多分違うと思います。死ににいくみたいになっちゃいますから。それって仏になりたい人はやればいいけど、別に仏になりたくない人にとってはそこまでする必要ないというか。つまり教えは、こんな方法で心を幸せにすることもできるよねっていう一つの方法でしかないというか。死んだ後の世界のことはさておき、生きてる間はこんな幸せの方法あるよねって、参考になるねって、都合よく使えばいいというか。
この本も同じなんだなと。そう思いました。一つの考え方と思って読んで、私の引き出しの中身がまたひとつ増えたなって、そんな感じです。
私はこの本を読んで、ああ、この人はこんなふうに120年前を生きたのだなあと思いました。哲学に生きた人なのだなあと。本って面白いです。
ゆー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
