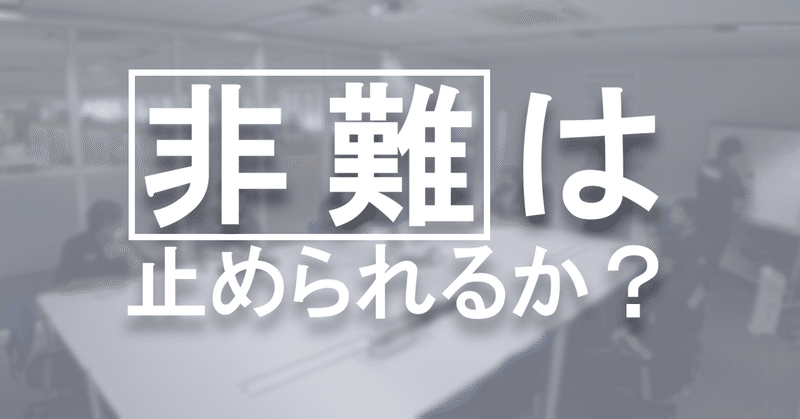
非難は止められるか?
"2007年、ロンドン北部のハリンゲイで、ピーター・コネリーという17か月の男の子が亡くなった[中略]マスコミの怒りの矛先は、当時ピーターを保護する責任があった人々、特にピーターを直接担当していたソーシャルワーカーのマリア・ウォードと、地区児童安全保障委員会(LSCB)委員長のシャロン・シュースミスに向けられた。[中略]非難の的となった人々にとって、この時の経験はまさに「セイラムの魔女裁判」(米マサチューセッツ州セイラム村で無実の人々が魔女として処刑・拷問された事件)を思わせた。破滅的な非難合戦だ。
しかしここまで大騒ぎになれば、その後はソーシャルワーカーの仕事ぶりが改善されるだろう、と人々は確信していた。いわば「たとえ懲罰が度を越していても、それによって相手は姿勢を正し、けじめをつけるだろう」という考え方だ。「これで彼らは仕事に専念できるようになる」とある識者は言った。
ではその結果どうなったのか。ソーシャルワーカーは、以前より責任を持って働くようになったのか?子どもたちはしっかりと守られるようになったのか?"
『失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織』
株式会社ディスカバー・トウェンティワン Kindle版
Kindleの位置 No.3134-3156
どんなに複雑な事象でも「これはあいつの責任だ。」と直感的な結論を付けたがる。過度の単純化と呼ばれる現象で、人間の脳にはこのような強い認知的処理の衝動があるようです。
昨今のパワハラ防止意識が浸透していることもあり、ミスをした部下を直接頭ごなしに叱責するようなことは少なくなったようには感じます。しかし、何かミスが発生した場合、「担当者の不注意のせいだ。」と心で思ってしまうことは人間の性で避けられません。最終的に、個人に責任を集中させてはならぬと、「その部署の教育体制が悪い。」「上司の監督不行き届きのせいだ。」と“柔和な非難”が口を出る。会社の上層部でこういう議論が行われることはあるのではないでしょうか。先入観により、複雑な物事を単純化し非難で完結させてしまう。本質は変わらないと考えます。さて、本能の赴くままに非難を行えば、組織は本当に改善に向かうのでしょうか?
往々にして、ビジネス上のミスというのは不注意だけでなく、当事者の心理状態も含め複雑な条件によって引き起こされます。そしてその背景を詳細に分析することで、問題の真の原因を理解し、再発を防ぐことが出来るはずです。
パイロットの世界は個人の失敗を開示し組織で学習する文化が根付いていると最近知りました。レバーの押し間違い程度のミスでも、開示が奨励され、第三者機関が深く分析し対策を施す。この例では、パイロットにプレッシャーがかかる状況下だと、似た形状のレバーを図らずも操作してしまうことが調査の結果分かったそうです。結果的にレバーのグリップ形状変更で、誤操作は根絶されました。
ミスが発生したら、当事者が即時に報告、第三者による調査、対策を組織で共有、このシステマチックな改善のサイクルが、飛行機を”最も安全な乗り物”たらしめることに私は納得したのです。
「ボタンの押し間違い」「作業手順の抜け」軽視していた我々のミスの歴史にも組織を進化させる学習機会があったのでしょうか。一体いくつの「担当者の不注意」の結論で処理されてきたのか気になります。
失敗という学習機会を”いい意味”で獲得するためには個人が進んでミスを報告する姿勢が不可欠です。ここで非難が起こるとどうなるでしょう。当の本人は悪意を持ってミスをしたわけではないはずです。それなのに、過剰に責め立てられる。今後、その人は積極的に自分のミスを報告することができるでしょうか。
「思わず組立中の製品に小さな傷をつけてしまった。言うと面倒だしこのまま黙っておこう。ここは目立たない場所だし、ばれないだろう…。」
もしかしたら、その小さな傷の裏には、運んでいた部品の形状、養生のやり方、足元の悪さ、他作業員とのすれ違いなど、様々な環境的な要因があったかもしれません。再発の防止策の答えがあったのかもしれません。
一方、非難をする人もミスを無くすことを本気で望んでいるのです。「規律を正すために」「責任を再認識してもらう」しかし、人を律することで、実際に減るのはミスではなく、ミスの報告。知る機会が無ければ学習は出来ず、ミスが再発する。再発の度に非難が強まり、隠蔽体質は加速する。世直しのはずが、真逆の方向に進みかねません。
ミスを適切に分析し、組織で学びを共有する。簡単には聞こえますが、非難の衝動と決別する自制心、ミスの開示を促す組織内の心理的安全性、これらを確立するのは一筋縄ではいかないと見ています。弱気な話ですが、今の私の立場ではまだまだ難しいと感じるのです。しかし、このような漸進的な企業を実現できれば怖いものはないはず。
従業員のマインドを半ば強引にでも変えることができる。それがオーナー企業の経営者のメリットでもあると思います。いつか、時が来たらチャレンジしてみたい。そんな思いになりました。
”結果は、ソーシャルワーカーの辞職の急増だった。[中略]
当然、一人ひとりの子どもにかけられる時間は減る。そして、彼らは自分の管理下の子どもたちに何かあった場合を恐れ、強引に介入し始めた。[中略]
家族から引き離される子どもの数は増え、裁判所は急増した保護事案の処理に追われ、保護命令は次々と出されることになった。[中略]
あらゆる記録文書の内容が長くなっていったが、増えたのは情報ではなく弁明だった。貴重な情報は、問題視される可能性を恐れて隠蔽された。さらなる魔女狩りを防ごうと、自己防衛にばかり時間が割かれ、実際の社会福祉活動はないがしろにされていった(10)。[中略]
こうした非難騒ぎの翌年、虐待によって死亡した児童の数は25%以上増加し、その後3年間上昇し続けた(12)。”
『失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織』
株式会社ディスカバー・トウェンティワン Kindle版
Kindleの位置 No.3157-3185
このnoteを800文字程度にぎゅっと内容を凝縮した私のコラムが松浦機械製作所の広報誌、マツウラNEWS!にて掲載されております。

このコラム以外にも、弊社の社長コラムやユーザーインタビュー、最新の松浦機械の活動も紹介していますので、もしご興味あればそちらも読んでいただければと思います。
また、私のDX推進の日々や工作機械の話をかなりカジュアルにTwitterにて発信しています!もしご興味ありましたらぜひフォローお願いします!
あのファナックが内部を公開…ッッ!!
— しつちょう【DX推進室】@松浦機械製作所 (@yuto_matsuura) January 30, 2023
工作機械の頭脳…松浦機械の信頼性を支えるFANUCの秘密をしつちょうと探る7分間!
諸事情により再アップロードすることになりました🙇♀️
良かったらもう一度見てください🙇♀️
フル動画はYouTubeで公開中!https://t.co/KOtL1VLauL#惜しまれる高評価63件 pic.twitter.com/QlOesGcI7E
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
