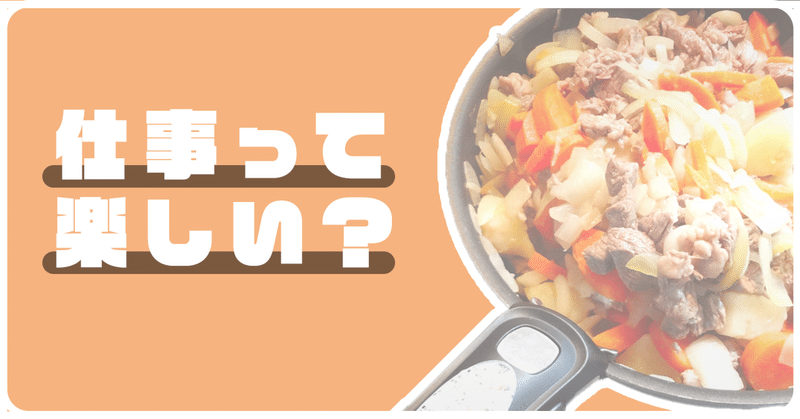
仕事って楽しいのか?
仕事というものは、人生の大半を占めるものになります。そして、本当に満足するための唯一の方法は、「あなたが素晴らしいと思う仕事をすること」です。
これはスティーブ・ジョブズのスピーチ内の一文です。(めっちゃ好きなんですよね、あのスピーチ。)
仕事は人生の全てではない。これは大前提。でも、大半を占めるものだから、楽しい方がいいに決まっている。
仕事って勉強みたいな一面もあるから、楽しいばかりじゃない。当時は大変だったけど、振り返ってみれば、辛い経験が役に立ったことなんてこともあると思います。
何を目指すべきか。
何を目指してほしいのか。
自分は社会人になって2023年9月で丸8年を迎えます。これまでに、下っ端のエンジニア、課長クラスの管理職、取締役という経営層までを数年ずつ経験するという目まぐるしいキャリアを駆け抜けてきました。
下っ端の時に楽しかったことや嫌だったことはよく覚えています。会社が嫌になりすぎて、仕事なんてストレスの対価に給料をもらうだけの場所だなんて考えてた時期もありました。そして、その記憶も薄れぬままに経営層に入りました。
今回はそんな稀有な経験をしてきた自分が勝手気ままに、仕事の楽しさをキャリアの成長と関連付けて論じてみようと思うのでお付き合いください。
ついに4月から新入社員に講話をすることになったのでパワポつくりました!
— しつちょう【DX推進室】@松浦機械製作所 (@yuto_matsuura) March 7, 2023
しつちょう流仕事の流儀…
皆さんやったら、新入社員に仕事ってこういうもんだよってどうやって説明します?#やっぱりもっと懸垂のフォームによる効かせられる部位の違いの説明を詳しくした方がいいかな pic.twitter.com/rKl09z2wIt
仕事の楽しさとは何か?
自分はこの2つだと思います。
他人からの感謝/他人の喜び
自分の成果を自分でコントロールしている感覚
前者は自明です。しかし、この感謝や喜びって簡単に得られるものではないのではと思います。
会社の仕事は、商品開発も営業も広報もすべて「分業」だから、自分の作業がお客さんをどういう風に喜ばせているのか実感することができない。
もし仕事に関わる人全員が、サービスを作ってからお客さんに提供するまでのすべての過程を経験できたとしたら、もっと自分の仕事を楽しむことができるようになるはずだ。
「夢をかなえるゾウ3」
文響社 Kindle版
Kindleの位置 No.2797-2800
まさに引用の通りですが、分業でも仕事には必ずお客様がいるわけです。例えば、工作機械の設計においてはある意味、製造する現場がお客様という考えも出来ます。
しかし、社内のやり取りだからこそ、当たり前に取られて、感謝されたり喜びを感じたりすることってなかなかないのではないでしょうか?「現場をお客様だと思って仕事をしろ」と発言するだけでは無責任なのです。会社の仕組みや文化作りが必要です。これは今後、何とか考えていかなければなりません。
また、実際にお客様の喜びや感謝をいかに社内と共有できるかも重要だと考えます。BtoBの製造業だと直接お会いする機会はなかなかないためです。
話はそれますが、松浦機械では海外のユーザーインタビュー動画に日本語訳をつけて、社内向けに隔週でYouTubeリンクを配信しています。動画に載せればポジティブな声も直接届けられる。2年前に始めた当初は皆、珍しがって見てくれていましたが、最近は社員からの視聴数はちょっと低迷しています…。他のこと考えないとですね…。
人間にとって、自分で考えて工夫していくんはめっちゃ楽しい作業なんや。それはゲームしたりテレビやネット見たりする以上に楽しめるんやで。せやけどほとんどの人は、仕事をそういう形までもっていけてへん。
「夢をかなえるゾウ3」
文響社 Kindle版
Kindleの位置 No.2528-2530
さて、今回メインで話したいのは、自分の成果を自分でコントロールする感覚についてです。
皆さんはゲームはするでしょうか?私は学生の時はかなりゲームにはまっていて、時間があれば際限なくやっていました。しかし、ふと考えるとなんで人ってゲームを楽しいのだろうと思いませんか?
無機質な言い方にもなりますが、ゲームはボタンの入力から電子計算の結果を表示しているだけで、実質何も生み出さないはずです。それでも人間の脳ってそれが楽しいと思うわけです。それは、自分の成果を自分でコントロールしている感覚に関連していると考えます。
書籍の引用にもありますが、自分で考えて工夫して実行していく。そして、その結果/成果/フィードバックが目に見えてすぐ出てくる。このなんとも言えない達成感や刺激が楽しさを生み出しているはずです。これは、ゲームに限らず、スポーツ、SNSなどの趣味にも同じようなことが言えると思います。
本題に戻りますが、仕事が楽しいと思えることもこの感覚が持てるのかが重要だと考えます。自分で考えて工夫して実行して結果を出す。そして、さらに仕事ができるようになる。
”仕事ができるようになる”という感覚はどのようなものでしょうか。ここでは自分が思いついた身近な例で考えます。
母親にカレーを作る手伝いを頼まれたとしましょう。
自分が中高生。そして、まったく今までキッチンに立ったことが無い前提です。元々、母親が夕飯でカレーを作るはずでしたが、急ぎの用事が出来たたため、手伝いをお願いされたということです。

カレー作りですが、単純な作業に分解したら色々なことがあります。例えば、スーパーでの買い物、ニンジンを切るのようなことです。
カレー用の肉を買ってきてくれと言われたとき、全く普段料理をしない人なら、どの価格帯のお肉を買うかって結構迷いませんか?
ニンジンを切れっと言われて、まず皮むきをしないといけないことは大体の人が知っていると思います。しかし、いざキッチンに初めて立って、ピーラーがどこの引き出しに入っているか分からないなんてことはあり得るのではないでしょうか。
なんとなくやること分かったけど、必要なものがどこにあるか分からない。これって仕事の世界でもあるあるですよね。知っている人に聞いたり、ネットで調べたりして解決しているはずです。
まずは、「分からない」を減らすのが仕事ができるようになるの第一歩だということです。
聞いて、調べて、覚えるということですね。特に重要なのは覚えるだと思います。聞いて調べて、覚えられないようなら、仕事ができるようになっているという感覚にはなかなかつながりません。
ピーラーがどこにあるかを毎回毎回聞いているようでは前進していないということです。
「分からない」を減らすを続けていくと、全体の工程がなんとなく理解できます。カレーで言えば、どんな材料が買えばいいかも、料理の具合をも経験で分かるはずです。こうなると「あんたカレー作っといて、任せたわ」となるわけです。
カレーを作るって色々な判断が必要だったりします。
何時に完成を目指すのか、冷蔵庫にあるものの何を使ってスーパーで何を買うのか。
いざ、スーパーに行くといつものカレールーがなかった。他のルーを買うのか、他のスーパーでさがすのか、時間的には大丈夫か…?一応、ラインでみんなに聞いてみよう。弟に頼んで帰りの道中で買ってきてもらえば間に合うか。
任されるというのはどういうことでしょうか。私は、言われたことに対して、目的を定義し、自分で判断し選択することだと思います。
カレーを作ることは、仕事で言えばプロジェクトを管理するということに等しいです。カレーを作るためのマイルストーンの設定や判断は多くあります。自分で考えて決めるべきこと、上司の判断を仰いだ方がいいこともあります。これをバランスよくできるセンスを持つのが任される人間です。
理解力、想像力、提案力をフル活用するわけです。自分で目的を理解し、状況を分析、不測の事態を想像し、考えた対策を実施していく。これこそが自分で考えて工夫していくということであり、仕事の楽しさが詰まっているところではないでしょうか。ゲームと同じです。
その先には何があるでしょうか。
それは、挑戦するということです。
未知なモノ、初めてのことに取り掛かるということです。
今までカレーしか作ってなかったけど、何か他の物を作ってみる。カレーを作るにしても、さらに美味しいものを作り出せるように最大限の新しい工夫をしてみるということです。
料理だと大したことが無いように聞こえますが、「やったことないから」と言って、断ったり、予防線を張る人は仕事上でもいます。これは非常にもったいない話です。挑戦し乗り越えるからこそ自信につながります。自信こそが、自分の成長の実感であり、自分の努力と工夫で手に入れるべき成果の1つだからです。
自分のできることを増やすには実践しかありません。そのためには挑戦が必要です。同じことをただルーティンのように繰り返す毎日では、たどり着けない領域です。
「分からない」を減らす
任される
挑戦する
この3つを段階的に進めていくことで、仕事ができるようになるという持論です。そして、最終的には楽しさに繋がると思うのです。
みなさんはどう考えるでしょうか。
このnoteを800文字程度にぎゅっと内容を凝縮した私のコラムが松浦機械製作所の広報誌、マツウラNEWS!にて掲載されております。
このコラム以外にも、弊社の社長コラムやユーザーインタビュー、最新の松浦機械の活動も紹介していますので、もしご興味あればそちらも読んでいただければと思います。
また、私のDX推進の日々や工作機械の話をかなりカジュアルにTwitterにて発信しています!もしご興味ありましたらぜひフォローお願いします!
弊社は日本で20年以上、金属3Dプリンターを開発製造しているメーカーです
— しつちょう【DX推進室】@松浦機械製作所 (@yuto_matsuura) September 3, 2023
製造業でこれからもっと3Dプリンターが普及するには何が必要かよければご意見ください🙇♂️
・材料(粉末)の値段
・機械の値段
・機械の造形速度
面白い意見が集まるのを願い、上記関連以外だと嬉しいです#3Dプリンター pic.twitter.com/j3JUwmBejL
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
