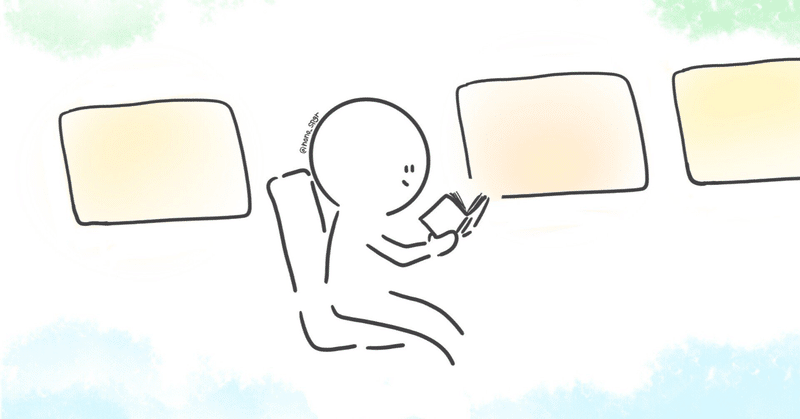
No.9 GTO Wizard Blogの解釈記事【What is Equity in Poker?】
本記事はGTO Wizard Blogを私なりに解釈し、友人に説明するならどのように書くかな?と再まとめしたものとなります。
今回の記事は「What is Equity in Poker?」になります。
承認欲求を満たすために是非「♡」をお待ちしております。
X(Twitter)のフォローもお待ちしております。
本記事では「EQ(エクイティ)」について、説明を進めていく。本記事を読めば、「EQの取り扱いについて」の全体像を把握することができると思う。是非腰を据えて読んでみてほしい。
(筆:質問等あれば、TwitterにてDMください。一緒に座学しましょう。)
■ EQの定義について
「EQ」の定義は以下の通りである。
ストリートにおいて、それ以降アクションが全てチェックダウンで進行されることを前提とし、その時点で自身のハンドの勝率をEQという。
別の観点で言うと、EQはポットのシェアを表している。
例えば、EQ=50%である場合、それらのハンドは現時点ではお互いが50%ずつポットを取る可能性を有している。ということである。
■ EQの比較方法について
EQは何に対して、そのEQを算出しているか。が重要である。
例えば、君がBTNでAAをオープンし、BBがコールした場合を考えよう。
① ハンド vs. ハンドのEQ
「AA」は「65s」に対して:EQ=77%
② ハンド vs. レンジのEQ
「AA」は「BBのディフェンスレンジ」に対して:EQ=83%
③ レンジ vs. レンジのEQ
「BTNのオープンレンジ」は「BBのコールレンジ」に対して:EQ=53%
実際、相手のハンドを特定することは非常に難しい。そのため、基本的に「ハンド vs. レンジ」もしくは「レンジ vs. レンジ」のEQを活用して、意思決定を行っていこう。
数学的にEQは次のように定義される。
EQ = (win% + 0.5 tie%)
例えば、君が持っているハンドは50%勝ち、20%引き分け、30%負けるとしよう。そのハンドのEQは以下に計算する通り、60%となる。
→ EQ = 50% + 0.5×20% = 60%
■ 2と4の法則について
君がドローを持っている際、簡単にEQを見積もる方法を紹介しよう。方法は以下の通りである。
① アウツを数える。
② アウツに対して、フロップの場合4を、ターンの場合は2を掛ける。
→この計算結果がおおよそのEQとなる。
※デッキには約50枚のカードがあるため、シンプルにアウツを引く確率は1枚あたり2%である。
(筆:フロップの場合には残り2枚引けるので4%、だからアウツに4を掛ける。ターンの場合には残り1枚引くことになるので2%、だからアウツに2を掛ける。ということになります。)
では実際に計算をしてみよう。
例:相手がフロップでポットのAIしていて、君はスペードのドローを持っている。
ボード:A♠ 6♠ 8♦
ハンド:K♠ J♠
君には9枚のアウツがある:2♠ 3♠ 4♠ 5♠ 7♠ 8♠ 9♠ T♠ Q♠
フロップであるため、アウツに4を掛ける:9 x 4 = 36%
君は約36%のEQを持っていることがわかった。
では、これを計算して、何に役立つのだろうか?
→自分のポットオッズを計算してみよう。
ポットのAIを受けているので…
Pot Odds = call額 /(call額 + pot)= 1/ (1+2) = 1/3 = 33%
コールをするためには33%の勝率が必要であることがわかる。先ほど計算した君が保有するドローのEQは36%であったため、勝率を上回っている。従って、このドローはコールとなるわけである。
(筆:ドローを完成させる以外にも勝つ可能性はありますからね。例えば「TT」でブラフAI打ってきた等。)
説明をしてきたこの方法は、ドローを持っている時、EQの推定に役立つが完璧ではないことに注意が必要だ。 もし、フロップのベットがAIでない場合、ターンで更なるベットが来る可能性を考慮しないといけない。 相手がブラフをしている可能性もあるため、君のEQはより高くなるだろう。 想定したアウツがそもそもアウツでない可能性もある(例:相手が上記の例でAAを持っている場合、8♠のアウツは相手がフルハウスになる)。その他、よくあることとして、ドローがヒットした場合、降りられなくなる可能性もある。 それでも、プレイ中には計算することは有意義である。
(筆:基本的に、ドローを持っていて、AIされている時に使用したらいいと思います)。
■ EQR(エクイティリアライゼーション)について
「実際の(他に正味の/生の等記載有)」EQの問題は、チェックダウンされることを前提としていることである。
(筆:理論上と現実世界は違うのです。)
加えて、EQ50%のハンドがポットの半分を獲得するとも仮定している。しかし、ポーカーはそううまく行かないのが現実だ。あるプレーヤーが理論的に示されるEQよりも、より多くのポットを獲ることがある。
(筆:書籍などではEQをオーバーリアライズする。等と書かれています。逆に下回ることをアンダーリアライズと言います。)
この現象はレンジやポジション、ボード等様々な要因が重なる。
この現象のことをEQRという。
(筆:このEQRについては別の記事を作成予定です。)
■ EQを使ってはいけない場面について
君はBBにいて、BTNが2.5BBにオープンした状況である。
君は以下のように考えたとする。
「1.5BB上乗せしてコールだ。ポットは5.5BBになって、ポットオッズは27.3%だ。レーキも含めると、コールに必要なEQは29%くらいになるだろう」
上記の考えから、君は72oをコールすることにしたのである。ただ、残念なことに、このコールは平均で48bb/100 hands を失ってしまうアクションなのである。
(筆:実は最弱の72oでさえ、BTNのオープンレンジに対して、30%のEQを保有しています。)
理論上、72oは30%のEQを持っていたとしても、実際のところEQの一部しか実現しない。
GTO Wizardを確認すると、72oをコールするEVはフォールドに比べて、0.48BBマイナスであることがわかる。従って、72oは1.02BB(1.5 - 0.48)しか取り戻さない。残念ながら君が考えたことはEQとポットオッズの理論上からは正しかったとしても、EQRの観点から、72oはポットの18.5%(1.02/5.5)しか獲得しないため、誤りなのである。

もし、その後のストリートでBTNがチェックダウンしてくれるのであれば、72oはEQの100%を実現することができ、素晴らしいコールとなるだろう。しかし、ポストフロップを戦っていく上で、ポジションやレンジ等の不利な要因が相まって、72oはEQをアンダーリアライズするのである。
(筆:全部コールする!!!!!!!といった気合があれば、EQは100%実現されますが、現実はそうは甘くないですよね。)
■ EQRの定義
EQRはエクイティをEVに変換する方法であり、次のように定義される。
EQR = pot share % / Equity %
「ポットシェア(pot share)」はEV/ポットである。長期的にみて、実際に獲得すると期待されるポットの割合となる。
EQRは次のようにも表すことができる。
EQR = EV / (pot × equity)
これは、実際に獲得するであろうポット量と、「生の」EQ(チェックダウン仮定のEQ)が獲得するであろうポットの量を比較するもう一つの方法となる。
(筆:理論的に取れる量(EV)と実際のポットとEQを掛けて、実際の獲得量を比で表したものがEQRになると言った方がわかりやすいでしょうか?実際の獲得量が多ければEQをオーバーリアライズ(EQRが1以上)しますし、少なければアンダーリアライズ(EQRが1以下)します。)
■ EQRの実例を見てみよう
GTO Wizardを使用すると、君は各ハンドのEV、EQ、EQRを確認することができる。仮に、A♠9♠でオープンし、フロップがJ♠ 8♥ 5♥になったとしよう。バックドア、オーバーカード、9は8と5を上回る可能性があり、エクイティは43.3%である。EQRを無視すれば、平均で(43% * 5.5)= 2.36bbを獲得することになる。さて、EVはどのようになるかを見てみよう。

驚くべきことに、ポットの43.3%を獲得するはずが、5.5BBポットの13.5%(0.74/5.5)しか獲得できていない。下記に示すされるEQの1/3にも満たないのである。

次に、6♥3♥を見てみよう。このハンドは43%のEQを持っているが、インプライドオッズや相手からのプレッシャー(ベット)に対抗できるため、EQRは90%以上となる。

(筆:EQRはあるボードにおけるハンドの扱いやすさを示していると言ってもいいかもしれません。ベット側はEQRが高ければ、そのEQを実現してくれる。ということなのでベットしてもOK!コール側はEQRが高ければ、そのコールのEQを実現してくれる。ということはコールしても耐えることができる。ということなのでコールしてOK!と単純に捉えることもできます。(注)最初の内は)
■ EQ分布について
レンジ vs. レンジのEQは通常、ひとつの数字として表される。ただそれではより深い検討をすることができない。そんため、より良い表現方法として、分布として表現することが挙げられる。EQをひとまとめに表したとしても、その中にはナッツハンド、エアー、その他の全てのハンドから、その数値は計算されている。これらの全てハンドをEQ分布として見ることで、戦略的な傾向を見ることができるのである。
BB vs BTN J♠8♥5♥の例を使って、EQに関する一般的な指標を見ていこう。

■ EQバケツについて
EQバケツとは、君のレンジ内にどの強さのハンドがあるかを分類し、自身のレンジ構成を把握しやすくしれくれる。

(筆:簡単に言えば、ベストハンドに属するハンドはバリューに、トラッシュに属するハンドはブラフに適している。と考えてもいいです。ただドローなどのハンドはトラッシュには含まれないことが多いので、一概にトラッシュはブラフ!とは言えないですが大まかな指標としてはこのように考えてもいいと思います。)
J♠8♥5♥では、EQバケツは以下のようになる。


図の通り、BTN(緑:右側)はBBに比べて「高EQのハンド」が2倍近くあり、「ゴミEQのハンド」は3分の1しかないことがある。
(筆:このことから言える簡単なことはBTNの方が有利である。ということですね。)
■ EQグラフ
EQグラフはEQをグラフ化し、視覚的に確認することができる。横軸と縦軸は以下の通りである。
横軸:自身のレンジに含まれるハンドをEQの低い順に並べたもの
縦軸:そのハンドのEQ
下の例では、62付近にはBTNはA5sを持っている。語弊を生まないように注意が必要だが、レンジを100に分割したとして、A5sは62番目の強さを持つということである。そして、A5sはBBのレンジに対して、57%のEQを有している。
次にBB側の視点でも見てみよう。BBは62番目の強さを持つハンドはA5oであり、BTNのレンジに対して、51%のEQを有している。
これから言えることは62番目の強さのハンドにて、BTNは57%、BBは51%を有している。よって、相対的に62番目の部分ではBTNの方が優位性がある。と言える。
今回は62番目の部分に視点を置いたが、グラフ全体を見ると上位98付近を除いて、BTN側の方が常に優位であることが見て取れるだろう。このようにEQグラフは視覚的にどちらが有利なのか?の情報を我々に与えてくれる。

■ EQグラフの解釈について
これまでの記事でエクイティ分布がどのようなものか。についてわかっただろう、次はそれを解釈する方法を説明していく。 エクイティ分布がGTO戦略とどのように相関するかに関する研究は発展途上の研究分野だが、理解しておくべき重要な要素がいくつかある。
ナッツアドバンテージ
「ナッツアドバンテージ」とは、シンプルにレンジ内のナッツ領域におけるアドバンテージを指す。 通常、ナッツのアドバンテージを有する側が、レンジをポーラライズさせ、より大きなベットサイズを使用し、強いハンドを主張することができる。

上記の状況で、BTNは K♥J♦5♦2♣にてダブルバレルし、Q♥がリバーで落ちた。EQは互いに50%/50% だが、BTNはナッツアドバンテージを有している。これにより、BTNのレンジはさらにポーラライズされる(ナッツハンドやブラフハンドに大体ポーラライズされていることがわかるだろう)。対照的にBB のレンジ構成は大体がトップペアとなっている。 このポーラライズされた状況は、BTN の EV に大きなアドバンテージをもたらす(この際の最適な戦略はオールインとなる)。
次にEQグラフに焦点を当ててみよう(ナッツアドバンテージを強調している)。 ドットの部分は、相手のレンジに対して少なくとも 90% のEQを有するハンドである。

ナッツアドバンテージにより、どれだけポーラライズできるか、どれだけ大きくベットできるかが決定する。より大きく、より積極的にベットすると、相手のレンジはすぐに狭ばるだろう。
(筆:大きなベットにコールできるのはある程度のEQ、EQRを持ったハンドに限られるからですね。)
そのため、トリプルバレル後に、君のバリューハンドが相手のバリューハンドからどれだけチップを引き出せるか。が重要となる。これを達成するために、BTN はナッツとブラフからなるポーラライズしたレンジにてベットする戦略を使用するのである。 もし、BTN がマージナルな強さのハンドでベットした場合、単純に強いハンドからコールされるだけとなり、EVロスの要因となる。
レンジアドバンテージ
レンジアドバンテージとは、全体的にEQの優位性がある。ことを示す用語である。レンジアドバンテージはレンジの特定部分にて使う場合があり、例えば、先程説明したナッツアドバンテージは、EQ分布の上位部分に対するレンジアドバンテージのことを指す。
例えば、Q♥J♥8♣A♥のボードでは、BTN は 52% のEQを有している。EQグラフを見てみると、全体的に緑の線(BTN)が青の線(BB)より上にあるため、レンジアドバンテージを有していることがわかる。より詳しく見ると、BTN はEQ分布の中央付近に対してレンジアドバンテージを有しているが、ナッツ付近では拮抗しているため、アドバンテージがないことがわかる。


ベットサイズはナッツアドバンテージに関係することが前回の説明でわかっただろう。 今回の場合、ナッツアドバンテージはお互いに有していない。その結果、BTNはレンジアドバンテージを活かして、中間付近のハンドを小~中サイズのサイズにてベットを行う戦略を取る。
■ まとめ
EQはハンドを評価する考え方の基本となり、 様々なEQ分布を活用し、解釈する方法を学ぶことは非常に貴重なスキルである。
本記事を要約すると
ストリートにおいて、それ以降アクションが全てチェックダウンで進行されることを前提とし、その時点で自身のハンドの勝率をEQという。
→これは理論的なEQである。
EQRはポストフロップにて現れる変数を考慮するために使用される。
→EQRが高ければ高いほど、そのEQを実現できる。
EQ分布をバケツ化またはグラフ化することで、より戦略的な情報を確認することができる。
(筆:本日も座学お疲れさまでした!! この調子で座学を続けて、どんどんポーカー強くなりましょう!!)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
