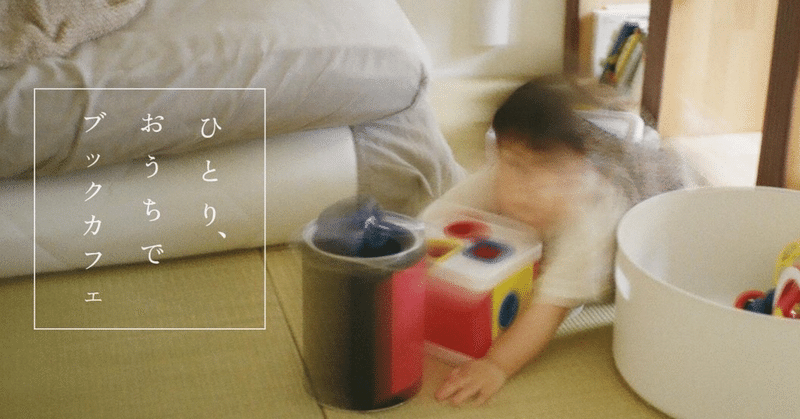
【noteで本屋】noteプロデューサーのおすすめは「本のメモ」を書くこと。
noteで本屋を作るために、ひとり企画会議をしています。
今回は「どんなスタンスで書評を書いていくか」について、noteプロデューサーの方の本を参考に考えていきます。
前回までで、本屋の趣旨やデザインの方向性がざっくりと決まりました。
次は書評ブログとして、文章や構成の方向性について考えていきたいと思います。
「本のメモを書く」というスタンスでいく。
本屋で見かけた、noteプロデューサーの徳力基彦さんが書かれた『自分の名前で仕事がひろがる 「普通」の人のためのSNSの教科書』がヒントになりました。
タイトルに「自分の名前で仕事がひろがる」とありますが、この本の趣旨は『ネット上ではどんどん実名で発信していくべき』ということ。
それは『SNS発信は「リアルの延長線上」でつかってこそ、ビジネスで真価を発揮する』から。
私自身は実名ではやらないので、その部分に関しては取り入れていないのですが、したたかに発信することの大切さであったり、仕事とプライベートを結びつけることで、垣根なく仕事を楽しんでいる印象がありました。
個人の名前が知られることで、最終的には会社に貢献できる。なるほど、と思いました。そういう働き方もいいですよね。
中でも、noteで「本のメモ」「ニュースのメモ」「イベントのメモ」を書くことをおすすめされていました。
文章を書くスタンスとして、以下の2つをベースにしたいと思います。
役立ちそうな部分、実践してみたいメソッド、印象に残ったフレーズ、キーワードなどをメモしていく。
法的なルールをきちんと守れば、自分の仕事に役立ちそうな部分、実践してみたいメソッド、印象に残ったフレーズ、キーワードなどをメモしたり、本について自分の意見を述べるために引用したりするのは問題ありません。
引用するときは、かぎかっこをつけるなどして、自分の意見と引用部分を明確に区別します。
SNS発信は、あくまでも自分の意見が「主」で、引用部分は「従」であることも意識しましょう。
引用元を明記することも忘れないでください。
ルールを意識しながら、まずは自分のためのメモとして、役立ちそうなことを書いていく。
それは他の人にとっても役立つことかもしれません。(といっても、期待しすぎないことも大切!)
書評と気負わないことが大事。
本について書くからといって、「書評」などと気負わないことが大事です。
著者や本を評価しようと思うと、発信のハードルを一気に上げてしまうことになります。
繰り返しになりますが、「自分のためのメモ」と割り切りましょう。
この割り切りは、結構大事な気がします。
ハードルを上げずに、あくまでも自分のためのメモとして書いていく。
途中で何かに迷ったら、この文章を振り返りたいと思います。
この連載のマガジンをフォローしてくださった方、ありがとうございます…!調べたことは今後もちょこちょこと更新していきます。
よかったらフォローお願いします◎
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
