
◯◯からの学び【2】合唱編
こんにちは。
「◯◯からの学び」シリーズの第二段は、"合唱編" にしようと思います。
0. なぜ合唱部に入ったか
合唱部に入ったのは、大学生の頃です。
歴史のある、男女混声の合唱団に入りました。
私は3歳からピアノを習っており、中高は吹奏楽部と音楽には触れ続けてきましたが、正直歌うのは嫌いでした。
嫌いというか、自分で上手くないと思っていたので、楽器の方が好きだったのです。
声も通らないし、音痴だし、と思っていました。
ところが、大学に入って唯一の友達(入試のときに仲良くなった子で、大学で仲が良いのはその子だけでした)が合唱部に入ることを最初から決めていました。
その友達と新歓の飲み会に参加してみて、先輩たちの人柄が良かったのと、もしかしたら歌が好きになるかもな〜、くらいの感じで入部を決めました。
1. 合唱の醍醐味

大学4年間は、ほとんど歌ってばかりいました。
年2回の定期演奏会に向けて、通常の練習もそうですし、合宿では一日8時間以上歌いっぱなしでした。
発生練習からボイストレーニング、パート練習、全パートの合わせ練習、やればやるほど楽しくなり、最終的には歌うことが大好きになりました。
合唱の醍醐味は、やはりハーモニーがバチーっと決まったとき!
全パートの和音とリズムと響きがバッチリ噛み合って一体感が生まれたときは、ものすごい快感と感動です。
本当に、歌っている最中に感動して泣きそうになることがよくありました。
声は体の一部。
中高吹奏楽部で楽器を吹いていたからこそ、人間の体だけでこんなにも素晴らしい音や響きが出せるのだということを、合唱部に入り改めて知りました。
中学も高校も、合唱コンクールというものはありましたが、おそらく私はそこまで真剣に取り組んでいなかったのかもしれません。
大学に入り、本気で歌に向き合ったからこそ分かる良さと想いがありました。
歌には、体ひとつで人を感動させる力があります。
そして合唱は、その力が何人、何十人分も集まった集大成なのです。
私がいた時代のものではありませんが、私がいた合唱団の曲がYouTubeに上がっていたので、ご参考まで!
最初は嫌いなことでも、継続してできるようになったら好きになるものですね!
2. パートリーダーになって学んだこと

私のいた合唱団は、2、3年生がメインの、仕切りの学年でした。
2年生になると、パートリーダーを決めることになります。
その場面はあまり鮮明には覚えていないのですが、たしか自分で立候補をしました。
それまで、リーダーなどやったことは一度もありません。
なんとか委員の委員長とか、班長とか、そういった役割は全力で避けてきたタイプ。
でも、ここでも「パートリーダーをやったらもっと歌が上手くなって歌が好きになるかもしれない」と思い、ドキドキしながら手を挙げました。
私のほかにアルトパートの同学年は3人いたのですが、快く承諾して頂き、パートリーダーをやることになりました。
今思うと、そうやって新たなチャレンジをしようと思えたのも、その3人をはじめ、同学年、先輩、後半、全員が本当にいい人ばかりで「ここでならチャレンジしてみても大丈夫!」と思えたことが大きいと思います。
本当に、人に恵まれた大学時代でした!
さて、パートリーダーになって学んだことは、リーダーにもさまざまなタイプがいるということ。
同学年のソプラノのパートリーダーは、合唱経験者で声も通るため、一番前でぐいぐいメンバーを引っ張っていくタイプに見えました。
すごいなー!!
純粋にそう思いマネしてみようとしましたが、やってみて自分はそういうキャラではないことに気付きました。
自分の強みを考えてみると、小さい頃からピアノをやってきたのもあり音程を取るのは得意だということに気付きました。
なので、私はいつもアルトパートの最後列に立ち、後ろからみんなを正しい音程に導く役割をしました。
サーバントリーダーという言葉を聞くようになりましたが、どちらかというとそんな形の支援型のリーダーシップを取るようになってから、パートが上手くいくようになった気がします。
リーダーはぐいぐいみんなを引っ張っていくべき!
と、勝手なイメージを最初は持っていました。
でも、チームが一丸となって目標を達成できるのであれば、リーダーにもさまざまなタイプがいていい、ということをこの体験を通して学ぶことができました。
3. 合唱から学んだこと
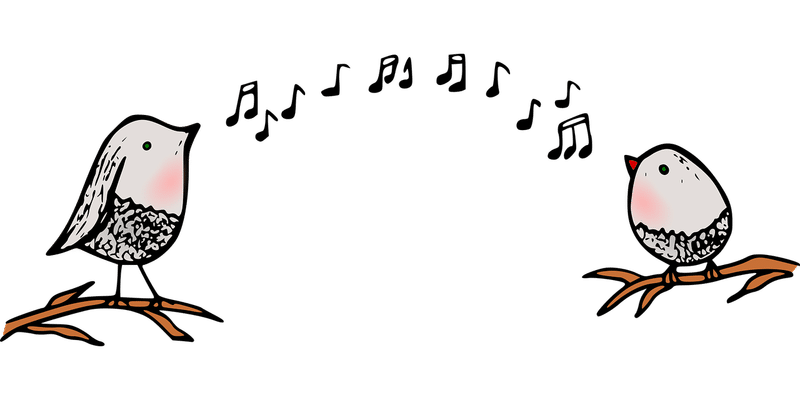
4年生の引退の日、引退セレモニーのスピーチの内容を考えていてふと思いました。
合唱の一番の魅力は、
"全員そろってからがスタート、
全員そろっていて正解"
というところだ。
どういうことか。
私はスポーツについてあまり詳しくないですが、例えばスポーツだと上手い人がレギュラー(スタメン?)になるのだと思います。
野球なら9人、サッカーなら11人、ですかね。
でも、合唱は、全員が最初からレギュラーなんです。
正直、歌が上手い人も、下手な人もいます。
楽譜が読める人も、読めない人もいます。
音程がバッチリな人も、外しがちな人もいます。
声質が柔らかい人も、芯が強目の人もいます。
声量が大きい人も、小さい人もいます。
でも、全員がいて初めて合唱は成り立ちます。
上手い人だけが本番に出るわけではなく、全員がステージに乗る前提で、
どんな人でも、ひとりも欠けてはいけないのです。
そのひとりひとりがいてこそのハーモニーなのです。
その、合唱の懐の広さに、私は感動しました。
全員がそろって初めて完成するもの。
上手い人も下手な人も、声質がバラバラでも、全員がいて正解。
ひとりも排除することもなく、ひとりひとりの個性を受け入れ、受け入れた上でバランスを取りながら曲という作品を作っていく。
もともと、私は人との関わりが好きではなく苦手意識もあり、好き嫌いやいろいろな条件から人を自分勝手に取捨選択するような生き方をしていたように思います(当時、取捨選択されていたのはむしろそんな性格の自分の方だと思いますが…)。
でも、どんな人でも関係なく包み込むような合唱に出会い、さまざまな個性のある人をおもしろいと思い、受け入れ、認め合えるような人間関係を作れるように少し自分の枠が広がった気がします。
自分の幅をもっともっと広げて、本当は器の大きい、どんな人でも受け入れられる人になりたい。
今でもその原動力はありますが、そんな風に思えたのは、合唱があったからかもしれません!
以上が、私が合唱から学んだことでした。
書けば書くほどもっと経験値を積みたくなるので、これからもさまざまな経験をしていきたいと思います!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
