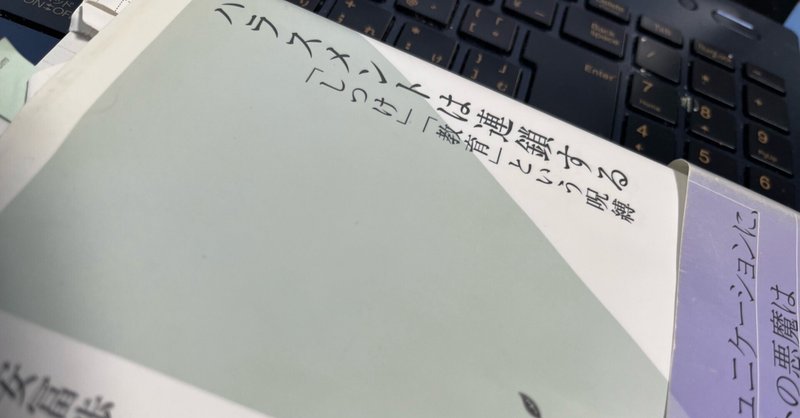
ハラスメント この本に出合って(2)私の生い立ち まあまあ良かったかな
ハラスメントは連鎖する
「しつけ」「教育」という呪縛
という副題がついている
この本に出合って(1)では、この副題に触れないまま
職場でのハラスメントの話になってしまった。
この本の前半部分の抜き書き
P25 子供は愛される権利がある。しかし、親が誰にも愛された経験がなければ、自分の子供ですら愛することはできない。愛される権利を奪われる子供は不幸ではあるが、それでも、親がその愛情の欠如を露呈してくれるならまだましである。
P26 「お前を愛していない」というメッセージと「愛されていない」という感覚が矛盾していないなら、子供は自分の感覚をそのまま信じることができる。
P26 親に愛されないこどもは不幸である。しかしそれ以上に不幸なのは、親が子供を愛せない事に罪悪感を覚え、自分が子供を愛していると思い込もうとする場合である。
このとき、子供は真に悲劇的な情況に置かれる。親が自分に対して、愛情に満ち溢れたように見える行為を熱心に行っているのを目撃しつつ、親の愛情を感じないとき、子供は、自分の感覚への信頼を失う。
この部分は、自分のまた他の人の育ち方を見る時の大きな視点になる。
私の場合
愛情に不器用な母親(父親も)を思い出す。仕事に疲れて忙しくて仕方がないと思える環境にあったのがなにより良かった。夜寝る時に、ぎこちなく布団の首元を寒くないようにと押さえてくれること、それが愛情表現だったと思う。この時に母親を感じられた。その一時を待っていたことを覚えている。デパートや外食に連れて行ってくれたが、その方法でしか愛情を表現できなかったのかもしれない。
御手伝いさんが家事をし、住み込みの従業員と食事をする。めったに1対1になれない。ある夜二人で外を歩く場面、私が母親と手を繋ごうとすると、ふりほどかれた。その動作をしてしまった母親も「あっ」と思っただろう。私は何事も無かったように手をひっこめた。お母さんはとても疲れているから仕方がないと思った記憶がある。
母親も多分その母親に十分愛される環境に無かったように思われる。祖父が権力を振るうなかで自己主張を全くせず6人の子供を育てたおとなしい祖母。孫の私への愛情表現を思い出せない。
育った地域が、どの家も親は仕事(商店が多かった)に追われているようで、自分だけでなかったのも良かった。それほど変に思わず育った。
お互いに、善意はあるが、親子の親密な愛情表現が出来なかったと思う。
勉強のこと、進路のこと、干渉されなかった。放任され(信頼され)て育って私に不満は少しも無かった。小学校のころから一人で電車に乗って出かけた。38度の熱でも自分で小学校の帰りに医者に行った。親の期待の圧力がない。自分で決めて受かれば学費は出すと言う。予想以上の大学に合格してもああそう。私は全く不満はなかった。
もし、私に子供がいたら、うまく接することができたかなと思う
これは、子供ができなかったので、分からない
同じ環境で育った姉が、放任に見えて教育ママの一面もある
一つの切り口からだけでは 分からないかもしれない
私は、親からハラスメントを受けたとは思いません。
抜き書きの、前半部分の一面はあったものの
母はぎこちないながらも親らしい行為をしようとしていました。
それを感じられたので、私は全く大丈夫でした。
大人になった娘を「ゆみさん」と呼び、
親子と言うより友人のような関係でした。
あっさりとした 良い関係でした。
P135
大人から子供へのハラスメントは「しつけ」もしくは「教育」という名前で呼ばれ、しばしば奨励されている。これらはすべてハラスメントであり、愛情とは正反対のものだ。
子供は必要なことを自分で自然と学んでいく能力を持っている。大人は単にきちんと庇護さえすればよい。
続きますが 間が開くと思います
このあと
ハラスメントの構造 の本題部分に入っていきますが。
とても難しい部分があります。
私の力では読み解けないかもしれませんが、
また(3)を書きたいと思います。
追伸 編み物どうなっている?


レッグウォーマー と思いましたが、アームウォーマーでも行けそうです。片側できました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
