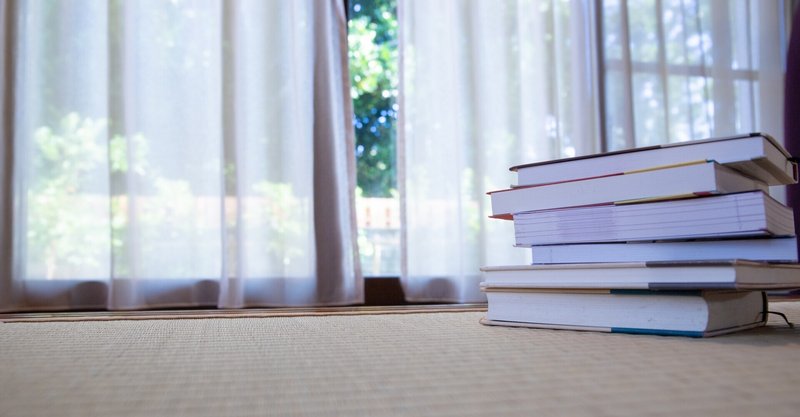
いい文章を書くために文章術の本を後回しにする私のおすすめ10冊
何度かブログでも書いたけれど、私は文教術の本をほとんど読まない。
正確に言うとライター1年目くらいから読まなくなった。
読まなくなったのは自分の文章に自信が持てるようになったから...というわけではなく、むしろ逆で、どうしてもうまくなりたいから読まなくなったというのが正しい。
文章術の本がためにならないと思っているわけではない。単純に、もっと読むべき本があると思っているのだ。
というのも、いつからか私は「読みやすい文章だね」と言われることが誉め言葉ではなくなった。読みやすい文章であることは当然「いい文章」に必要だけど、それは表現の話であって書いていることそのものに惹かれているわけではない、と感じるからだ。目指すべきは「惹かれる文章」。
私は、1日の大半を書くことか読むことに費やしているのだけれど、読み漁る中で「惹かれる文章」に共通点があることが分かった。『目線』や『視点』『事象の噛み砕き方』『解釈』が繊細だったり面白かったり目新しかったり、ささやかなことをすくい上げて言葉にする能力が高かったりすることだ。
あ、なるほど。私がいい文章を書けるようになるには、表面的な文章力ばかりを身につけるのではダメなのだとその時に思った。
さまざまな物語や表現に触れて『なぜか惹かれるもの』や『言葉にならない感情』をなるべく多く見つけ、それを自分の今ある力の限り咀嚼し、伝える努力をしなくてはいけない。それこそがいい文章を書くためのトレーニングだと思ったのだ。

文章術の本を読まないと言ったそばから、文章術の本の話を持ち出して恐縮なのだけど『三行で撃つ〈善く、生きる〉ための文章塾』に書かれてあった言葉が、まさに!だったのでここに引用する。
いいライターとは、善く生きている人だ。
これがすべてだ。善く生きたい。誠実に暮らし、丁寧に心を観察し、善い文章を書きたい。私がこれまで感動してきたように、誰かの心に『なんかいい』とか『妙に惹かれる』という感情を落としたい。
そして大好きな場所やもの、そこで感じた感覚のすべてを、なるべく伝わる形で表現したい。
ということで、今の私にはそういう「内側」を鍛える本が必要な時期なので、まだ「外側」である文章術までたどり着けていないというのが本当のところ。欲しい服を買うために、まずはダイエットを頑張るみたいなものである。まだ服を買う段階ではない。
*
と、いうわけでまだまだ文章術の本を読む機会は向こう1年は確実に巡ってこなさそうだ。そんな中でも、日々「内側」を鍛えるためにさまざまな本に触れているので、今回は私が刺激を受けた本を10冊ほどご紹介して終わろうと思う。
うたうおばけ(くどうれいん)
著者の日常と友達を軽快に書いたエッセイなのだけど、取り扱うカテゴリの平凡さに反し、筆致が巧みで圧倒される。いかに自分が物語の大きさに頼って文章を書いてきたかわかったし、この本と出会ってから確実に日常を見る目が変わった。
おいしいもので できている(稲田俊輔)
タイトルのとおり食べ物エッセイ。なんだけど、この本を読んで自分が「グルメの定番」に流されすぎていたことにまず反省した。「卵料理で1番好きなのは、月見うどんの卵黄を破ってうどんをすする最初の一口」など、とことん自分の偏愛に目を凝らしていて、面白いながらも「多分私だけが好きなアレ」を無性に食べたくなる。
平熱のまま、この世界に熱狂したい 「弱さ」を受け入れる日常革命(宮崎智之)
きっとこの本の著者はめちゃくちゃ本を読んでいるんだろうなと思う。読んだことがない本の引用が次々と出てくるし、なにより言葉選びの巧みさと観察眼が凄い。本を読み続けるとこういう文章がいつか書けるようになるかもしれないと希望が持てる1冊。
はじめての短歌(穂村弘)
短歌に興味がない人もぜひ読んでほしい。短歌会で超有名な穂村弘さんが「いい短歌」について解説していく本なのだけど、31文字をここまで解釈するのかと鳥肌が何度も立った。解釈することの楽しさ、喜びを体感として学べる本。
言葉にできない想いは本当にあるのか(いしわたり淳治)
「愛を込めて花束を」など有名曲を次々と作詞してきた、作詞家のいしわたり淳治さんが「言葉」をとことん面白がる短編コラム集。ネタ元はお笑い番組からCM、流行語まで幅広く、言葉に対する敏感さと経緯、言葉を扱う姿勢を学んだ1冊。
脚本家 坂元裕二(ギャンビット社)
普段ドラマを見るときに脚本家が誰かなんて気にしないんだけど、坂元裕二さん脚本だけは絶対に見逃さない。彼はドラマ界きっての言葉の魔術師だと思うし、この本にはその魔術のタネとか魔術に関わった俳優さんの目線とかが豪華にも程があるレベルで詰め込まれてて、もうなんか凄い。気付けば毎日どこかのページを開いてしまう自分がいる。
生きるための選択 ―少女は13歳のとき、脱北することを決意して川を渡った(パク・ヨンミ)
北朝鮮を脱北した女性の実話。衝撃的な展開尽くしの1冊だけど、中でも衝撃を受けたのは、やっと自由の身になれた時に彼女が自由に苦しんだことだった。だけど、こういうことって実は日常に潜んでいる。選ばないことや諦めることに慣れてしまったら、選ぶことが苦しくなるし、考えることの大変さに戸惑うのだ。無意識にそこに自分や誰かを追い込んでしまわないよう、気をつけたいと思った。
三行で撃つ 〈善く、生きる〉ための文章塾(近藤康太郎)
先ほども引用した本。結局文章術かい!と突っ込まれそうだけど、この本は文章術というより文章寺って感じ。書く姿勢について、書くための善い生き方について、背中で語ってくれる1冊。
ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと(奥野克己)
狩猟採取民であるプナンの人々について、小気味良く語られた1冊。何かをプレゼントした時に「ありがとう」じゃなくて「いい心がけ!」って言われたらイラッとしません?でもプナンではそう言う。なぜか。私たちの当たり前とは違う価値観があるから。物質的には豊かな私たちが精神的にはなかなか豊かになれないのは、あまりにも複雑に物事を考えすぎているからかもしれない。
Neverland Diner――二度と行けないあの店で(都築響一)
めっちゃ分厚くてまだ読み終わってないんだけど、化け物みたいに文章がうまい人100人が書く「二度と行けないあの店」エッセイ集。著者の都築響一さんを筆頭に、世の中にはこんなに文章がうまい人がいるのかと絶句、目眩、恐怖。だけど興奮する。そんな本。
インタビューというより、おしゃべり。担当は「ほぼ日」奥野です。(奥野武範)
ごめんなさい、10冊といいながら最後にもう1冊だけ。これはインタビューがおしゃべりになっちゃった会話の実録なのだけど、そこに流れる温かい空気がビシビシ伝わってきて、人と話すことの幸せをしみじみ感じられる本。実はインタビューが苦手なのだけれど、この本を読むと無性に人の話を聞きたくなる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
