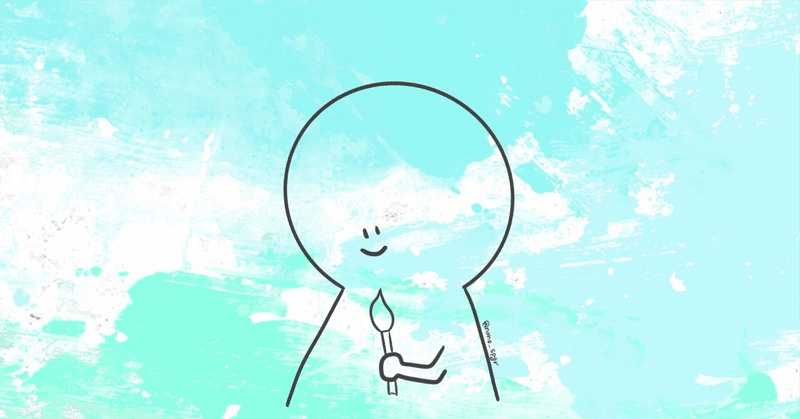
コーチのためのスポーツ心理学②インナーエッジを効果的に鍛えるには?-スポーツ心理学が目的とするもの-
前回のnoteにて、インナーエッジ(いわゆるメンタル)を鍛える、トレーニングすることの重要性をまとめました。
その中で、インナーエッジは、スポーツ心理学の知見を応用することで鍛えることができると述べています。
では、スポーツ心理学という学問は
そもそもどのようなことを目的とする学問であるのか?
ということを今回のnoteではまとめていければと思います。
スポーツ心理学の3つの目的
早速の結論として
①最適なパフォーマンス
②最適な発達
③最適な経験
の3つを達成することをスポーツ心理学は目的としています。
スポーツ科学の領域には、心理学だけではなく、栄養学や生理学、バイオメカニクスや、マネジメント、ゲーム分析、測定評価などなど
当然ですが、スポーツに関わる様々な学問領域がありますが、ほとんどのスポーツに関わる学問領域では①最適なパフォーマンスにフォーカスされることが多いのではないでしょうか。
ほとんどのスポーツチームでは、コーチ、トレーナー、ドクター、アナリストといったスタッフは必ず1人は配置されていると個人的には感じていますが、これらのスタッフも基本的には①最適なパフォーマンスのためのスタッフであることが多いのではないでしょうか。
スポーツ心理学では、もちろん①最適なパフォーマンスも大切にしますが
3つの目的をバランス良く大事にする
ということが1つの特徴になるのではないかと思います。
(もちろん、それぞれの分野においてもパフォーマンス向上だけでなく、長期的に見た人間的成長や障害予防の観点からのより良いスポーツ環境の整備などが含まれていることも熟知しています。)
以下では、それぞれの詳細についてまとめてみたいと思います。
①最適なパフォーマンス
少し想像してみましょう。
皆さんの前に幅30cmの平行版があるとします。
皆さんはこの平行棒を渡ることができますか?
恐らく、多くの方が問題なくサッと渡れるのではないかと思います。

それでは、先ほど想像していただいた平行棒が、スカイツリーの展望台からどこかに伸びている平行棒の場合、先ほどと同じように渡ることができますでしょうか。
強風が吹いたり、揺れたりなどは一切なく、スカイツリーの展望台からという部分以外すべて先に考えてもらった条件と同じです。
そのような条件であったとしても、先の例と同じ状態で渡れるという方は、ほとんどいないのではないかと思います。
しかし、やること自体は、同じ幅の平行棒を渡るだけ。
落下すると大きな怪我をする、ましてやスカイツリーの展望台の高さから落下するとなるとまず助からないといったことを想起することで、ストレスやプレッシャーというものが加わり、平行棒を渡るということに対するパフォーマンスは格段に悪くなると思います。

実際のスポーツの現場においてもこの例のように外的な要因(歓声、賞金、周囲からの期待など)によって普段できていたことができなくなるといったような状況が多々起こるのではないかと思います。

インナーエッジでは、このようなストレスやプレッシャーに適切な対処を行い、自身の最適なパフォーマンス発揮に繋げていくことを1つの目的としています。
②最適な発達
僕のようにどっぷりと競技に浸かっている人間がつい忘れがちになってしまうこと
あなたは何のためにスポーツをしているのですか?
なぜ、人がスポーツをするのかというと
楽しいから
の一択であるはず。
もちろん、トップレベルのアスリートにもなると周囲の注目などからのプレッシャーなどもあり、楽しいだけでやっていけないということもあるかもしれませんが、それでもそこまでその競技を続けているのは、その競技が好きだからということに変わりはないでしょう。
その競技が好きで、その競技のスキルが上達を楽しむということに、しっかりとフォーカスする。
そのための具体例として、適切な目標を設定したり、適切なものに注意を向けるトレーニングがあります。
そして、スポーツで培われるそのようなスキルは、1人の人間としても欠かせないスキルの一つになります。
以上のような理由から、スポーツ心理学は最適な成長にフォーカスすることも目的としています。
③最適な経験
繰り返しにはなりますが、人はなぜスポーツをするのか
健康のため、勝ちたいから等、色々な理由があるとは思いますが
何よりも楽しいから、その競技が好きだからでしょう
自分のスポーツを「好きになる」ことは、アスリートがスポーツで成功するために必要な大規模なトレーニングに取り組み、それを継続するための重要な第一歩である(Bloom, 1985; Cote et al.)ということが提唱されています。
先述しているプレッシャーなどもあることも含めてスポーツというのは
たとえ負けたとしても、本人がスポーツをすることで最適な経験ができるものである必要があると思います。
また、このような自身のスポーツが楽しい、好きであるということは
選手の最適な精神状態(いわゆる、ゾーン)とも深く関係しているといわれています。
↑詳しくはまたの機会に
このようにスポーツ活動の中で、最適な経験をすることで結果的に最適なパフォーマンスの発揮にもつながります。
まとめ
今回は、前回の内容を踏まえ、スポーツ心理学の3つの目的
についてまとめてみました。
大切なのは、この3つをバランス良く成長させていけるようにすること
これ以降のnoteでは、メンタルスキルの土台となるもの、メンタルトレーニングと理論的背景、インナー・エッジを達成するために必要な3つのメンタル・スキルを紹介していこうと思います。
内容を紹介していく中で、多くのコーチの方々が
あれ、もう既に自分はできているかもしれない
感覚的にはわかっていたけど、理論を抑えると理解度が上がる
などのように、おそらく自分が思っている以上に多くのことを知っている!と思っていただけると思います。
実際に、「コーチがスポーツ心理学のアイデアを革新的な方法でアスリートに応用しているものの、コーチたちはそれをスポーツ心理学だとは思っていないかもしれない」と指摘されています(Veally,2023)。
成功するコーチングとは
アスリートにとって外側の「エッジ」と内側の「エッジ」の両方を追求することです。
皆様の内側の「エッジ」をトレーニングすることができる一助となれるよう自分自身も学びながらご紹介していければと思います。
今回もご一読いただきありがとうございます!
いいねやコメントもよろしくお願いします!
各種SNSのフォローも良ければよろしくお願いします!
Xアカウントはこちら
Instagramアカウントはこちら(コーチのためのスポーツ心理学図解版を投稿予定)
Facebookアカウントはこちら
次回以降も、よろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
