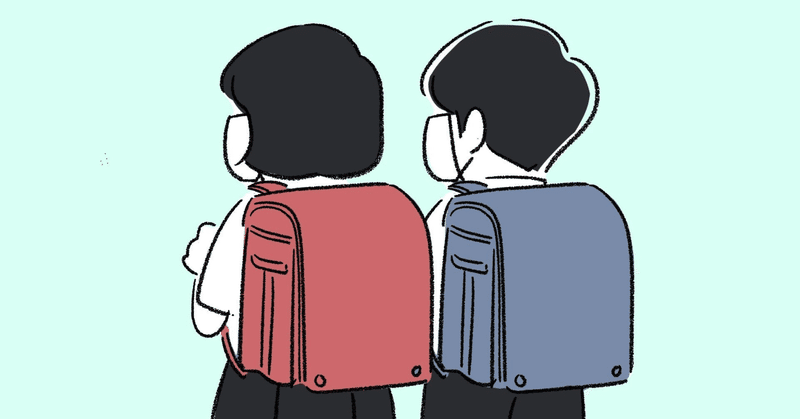
「(仮称)川西市子ども・若者未来計画(案)」へのパブコメ
私たち『地域と日本語教師の会@川西』は、川西市の多文化共生推進を願い、2023年1月に正式に川西市総合センターの登録団体となり、活動を始めた地域団体です。この度、川西市教育委員会 こども支援課にて「(仮称)子ども・若者未来計画(案)」についてのパブリックコメントを募集しておりましたので、『地域と日本語教師の会@川西』として、以下の意見書を共同で市に提出いたしました。
少し長いですが、川西市の方にぜひ読んで頂けたらと思い、こちらにも公開します。
(※以下の文書を書いたのは共に活動する仲間です)
地域と日本語教師の会@川西
私たちは、川西市で、外国ルーツの人々の支援をしている日本語教師のグループです。川西市の小学校、中学校でパートタイム職員として、あるいは、日高町の総合センターの「けんけんひろば」で支援者として、外国ルーツの子どもの日本語学習の支援をしています。
その立場から、会の共同代表3名の共通意見を述べます。
以下、外国籍の人を含む施策にかかわる当事者を「外国ルーツの人々」と書きます。日本国籍の人であっても、外国にルーツを持つ人で、言語など様々な困難を抱える人がいることを踏まえての表現です。
1. 私たちの提言:多文化共生の観点から、外国ルーツの市民の調査を。そして、その結果の政策への反映を。
まず最初に、私たちの提言を簡潔に述べます。川西市に在住する、外国ルーツの人々の状況について、市として、多文化共生政策の必要性を検討するため、アンケート調査を行うべきと考えます。
「計画案」(以下「(仮称)川西市子ども・若者未来計画(案)」を「計画案」と書きます)の「第1章 計画の概要」の「1 計画策定の背景」には、
「さまざまな困難や新たな課題に対応できずにいる子ども・若者が増え、引きこもりや若年無業者(ニート)など若者の自立をめぐる問題が深刻化するとともに、貧困、児童虐待、いじめ、不登校などの問題も依然として深刻な状況となっています。」
との現状認識が示されています。
そして、「第2章 子ども・若者を取り巻く現状」の「4 子ども・若者の状況」では、ひきこもり、不登校、高等学校中途退学、若年無業者・フリーター、経済的な困窮、ヤングケアラーなどの問題群が、対処すべき課題として挙げられています。
しかし、ここには、重要な視点が欠落しているのではないでしょうか。それは、外国ルーツの人々の事です。
近年、日本では、急激な人口減少の一方で、外国ルーツの住民が増えています。川西市も例外ではありません。以下は、出入国在留管理庁の「在留外国人統計表」よる、川西市における、外国籍市民の推移をグラフにしたものです。川西市における外国籍住民の数は、過去5年間で、20%近い増加を示しています。

2. 多文化共生政策が求められる全国的な状況
これは単に、一地域の問題ではなく、日本全体の、そして日本の未来にかかわる問題であることは、ここ数年広く知られるようになってきました。近年、日本では、さまざまな在留資格を持つ外国籍の人々が増え、いろいろな産業において、日本社会を支える欠くことのできない住民となっていることが、たとえばNHKの「外国人“依存”ニッポン」など、さまざまな形で報道され、知られるところとなっています。
2019年には、入管法の改正によって、人手不足への対応として、新たに「特定技能」の在留権が創設され、この傾向が今後加速することは確実です。
そして、そのような状況で、国は「多文化共生」を掲げ、総務省によって「地方公共団体における「多文化共生の推進に係る指針・計画」の策定に資するため」として、「地域における多文化共生推進プラン」が策定されています。
言語の面では、2019年に「日本語教育推進法」が施行され、「第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、日本語教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とされています。
このような、我が国の地域社会のあり方を求める総合的な観点が、「子ども・若者支援」の中に反映される必要は無いのだろうか、という疑問を、日々、外国ルーツの子どもたちと接する中で、私たちは率直な思いとして持ちます。日本全体の問題が背景にあると同時に、川西市には川西市固有の状況があると思います。その状況に応じた的確な施策のためにも、まずは調査が必要と考えます。
3. 課題点の一つ:高校中退
例えば、「計画案」では、高校中退の問題が取り上げられていますが、外国ルーツの子どもたちの観点からこの問題を見ると、どんなことが見えてくるでしょうか。
以下は、文部科学省による「令和3年 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査結果の概要」です。
https://www.mext.go.jp/content/20221017-mxt_kyokoku-000025305_03.pdf
高校中退についての調査結果は以下です(p.17)。全体が1.0%に対して、日本語指導が必要な高校生等の中退率は5.5%で5倍強、大学などへの進学率は全体が73.4%に対して、51.8%で7割、就職者における非正規就職率は3.3%に対して39.0%で11倍強、進学も就職もしてない者の率は6.4%に対して13.5%で2倍強で、極めて深刻な状況です。
日本の産業の多くが外国人に支えられている中で、このような状況が続けば、世代間の負の連鎖によって、外国ルーツの人々の生活が困難な状況のまま固定され、日本社会に大きな分断を生む結果になりかねません。私たちも、サポートしている子どもたちが、これからどのような人生を歩んでいけるのか、どのようなキャリアを描いていけるのか、とても心配です。外国ルーツの子どもたちへの支援を伴ってこそ、高校中退の問題の解決が図れるものと考えます。
4. 「特に支援が必要」な人々として外国ルーツの人々が固有の困難を抱えていることへの視点が必要
「計画案」の「基本目標2 子どもに応じた教育保育を提供する」では、
(1)就学前の教育保育環境の整備、(2)さまざまな子育て支援施策の充実、そして特にその中の「⑤特に支援を必要とする家庭への支援」において、さまざまな理由で困難を抱える人々への施策が挙げられています。外国ルーツの人々は、子育て、就学前、就学後のそれぞれの局面で、固有の困難を抱えていることは想像に難くありません。しかし、それに対する施策は全く挙げられていません。
川西市においても、まずは、外国ルーツの人々が、言葉の問題をはじめとして、どのような困難を抱えているのか、市として調査し、実態を把握し、それに基づいて必要な対策を講じていくことが必要だと考えます。
5. 兵庫県の政策
「計画案」では、第1章の「3 計画の位置づけ・期間・対象者」において、「(1)計画の法的根拠」として、以下の記述があります。
◉子ども・若者育成支援推進法(第9条第2項):
市町村子ども・若者計画
市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱(都道府県子ども・若者計画が作成されているときは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画)を勘案して、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画を作成するよう努めるものとする。
◉こども基本法(第10条第2項):市町村こども計画
市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画を定めるよう努めるものとする。
では、兵庫県ではどのような施策を掲げているのか確認してみたいと思います。
兵庫県では、「ひょうご子ども・子育て未来プラン(令和2~6年度)」が制定されています。
その第2章「基本理念と目標」の「Ⅵ 特別な支援が必要な子どもや家庭への支援」において、「8 外国人児童生徒への支援」の項目が立てられ、以下の記述がなされています。
8外国人児童生徒への支援
【現状と課題】
日本語指導が必要な外国人児童生徒は増加を続けている。県内においては2009年度の744人から2019年度には1,076人となるなど、10年間で約4割増加しており、母語の多様化も進んでいる。
外国人児童生徒は日本語の活用能力やコミュニケーション能力が十分でなく、日本語の習得と基礎学力の定着を図ることが極めて難しいため、将来の進路に展望を持ちにくく、自己実現を図ることが難しい状況にある。また、外国人児童生徒が母国の文化や言語に触れる機会が少ないことなどにより、自己を肯定的に受け止めにくい状況がみられる。
【取組の方向性】
外国人児童生徒等の生活適応や心の安定、アイデンティティの確立を図るとともに、日本語の習得や基礎学力の定着を図り、外国人児童生徒等の自己実現を支援する。また、全ての子どもたちが国籍や民族等の「違い」を認め合い、多様な文化的背景を持つ人々と互いに尊重しながら豊かに共生する心を育む。
また、外国人児童を含めた外国人家庭の生活が、安全・安心で暮らしやすいものとなるよう生活相談をはじめ各種支援を積極的に展開していく。
【主な取組】
① 外国人児童生徒の居場所づくり
子ども多文化共生教育を推進するため、人材や情報を一元化し、研修や交流等の機能を有する子ども多文化共生センターを運営し、外国にルーツをもつ人々が地域社会において安心して生活できるよう地域のNPO法人、ボランティア団体と協力して居場所づくりを推進していく。
② 定住外国人の子どもに対する学習支援
小・中学校における日本語指導が必要な外国人児童生徒等を支援するための日本語指導に関わる支援員の配置や、子ども多文化共生サポーターの派遣、教員研修の実施等を行うことで日本語を学べる機会を充実させ、学習支援を推進する。
③ 定住外国人家庭に対する支援
外国人児童生徒への支援にとどまらず、その親も含めた外国人家庭が県内で暮らしやすい生活基盤を築けるよう、「ひょうご多文化共生総合相談センター」での生活相談、文化・習慣に関する情報提供、地域の日本語・母語教育活動の支援、ホームページでの多言語による情報発信等を実施していく。
日々、地元で、外国ルーツの子どもたちと接する中で、これら兵庫県の施策が、川西市においても推進されることが必要だと強く感じます。
6. 周辺市の政策
県下の周辺市では、どうでしょうか。
例えば、尼崎市では、18歳以上の全外国籍市民を対象としたアンケート調査が実施されています。その項目には「子育て」も含まれています。
また、伊丹市では、以下の「伊丹市子ども・子育て支援事業計画」を策定しています。
その「第4章 施策の展開」では、「基本施策2 すべての子どもが社会を生き抜くことのできる力の養成」として、以下の項目が挙げられています。
「外国人児童生徒等受入事業
適応指導員を派遣し、日本語理解が不十分な外国人児童生徒等の学校生活を指導、支援するとともに、多文化共生教育を推進する。」
では、その「多文化共生」という観点については、伊丹市はどのような政策ビジョンを持っているのでしょうか。上記、子ども・子育て支援に記載されている多文化共生の観点に基づく外国人児童生徒への支援は、以下の政策方針にも記載されています。
「伊丹市多文化共生推進指針」
何よりも重要と考えるのは、私たちの提言でもある、外国人住民に対するアンケート調査や、外国人労働者を雇用する事業所に対するアンケート調査が、すでに伊丹市では行われ、その結果に基づいて、この多文化共生政策が策定されていることです。
日々地元で外国ルーツの子どもたちと接する中で、川西市においても、より充実した施策が、多文化共生の方針の中に位置づけられた形で策定され、実施されることが必要と感じます。
7. 私たちの活動から見えてくる川西市の課題
「計画案」に照らして、私たちの活動を通して見えてくる課題点について、以下、要望も含めて書きます。
7-1. 保育と小学校の円滑な接続について
「計画書」の「第3章 計画の考え方」の「2 基本目標」の「2. 子どもに応じた教育保育を提供する」において、以下の記述があります。
「各施設においては、教職員が能力の向上を図り、相互理解を深めることにより、それぞれの施設における教育保育を充実させるだけでなく、小学校生活への円滑な接続をめざし連携を強化します。」
外国ルーツの児童と、その家庭は、言葉や文化の違いなど、この課題における固有の困難を抱えていると感じます。その支援のために、市行政の業務として、支援手順のフローチャートを作成し、関連部署が横断的にこれを活用する体制を構築することを提案します。
想定される支援としては、外国ルーツの児童が、幼稚園・保育所から、小学校に入学する際、幼稚園・保育所からの情報をもとに、就学前健康診断や、入学説明会、教材の準備など、日本語ネイティブでない保護者をサポートする手順を整えることが課題の一つとしてあげられます。
また、転入に際しては、校長・教頭・担任・ALT・多文化共生サポーター・市費通訳翻訳支援員など、そして保護者も揃って、入学後の児童の支援について、コミュニケーションを取れる場を設定することが有効な方法になるのではと考えます。
保護者の国籍が日本であっても、日本語や日本の学校の制度・慣習についてよく知らない場合もあり、その点にも留意する必要があると考えます。
市として、そのようなケースにおける、支援のためのフローチャートを作成し、幼稚園・保育園と小学校との連携によって、事前に支援計画を立てることが必要なのではないでしょうか。適切で、安心できる支援手順を政策として確立することにより、当事者が市内のどこでにいても同様のレベルの支援を受けることができるようになります。外国ルーツの人々が、川西市民として安心して生活を営むことができるような条件の整備を通して、共生の街としての川西市の活性化に資するものと考えます。
以下の、兵庫県教育委員会の「外国人児童生徒のための受入れハンドブック」は、そのようなフローチャートを作成する上で、参考になるものと考えます。
7-2. 北部での日本語教育の拠点の形成を
川西市北部に住む私たちのメンバーの1人は、猪名川町国際交流協会を通じて知り合った10代後半の外国ルーツの若者を支援することになりました。
その若者は、川西市北部に住んでいるので、私たちが支援者として活動している総合センターまでは遠く、また、北部地域には日本語を学ぶことができる教室や、子どもの学習支援のための活動拠点がありません。
そこで、近くの北陵公民館を借りて個人で日本語レッスンを始めました。しかし、料金が発生することなどから公民館使用はあきらめ、現在はお店で日本語の勉強をしている状況です。
多文化共生という観点から、学齢期を過ぎた若者も含め、外国につながる児童、青年、住民たちの日本語学習や、学校の勉強をサポートできる場所が、全ての市民の学習権を保証する行政施策として、北部にも設けられることが必要なのではと考えます。
8. まとめ
「計画案」では、「すべての子どもたちに人生最高のスタートを~子どもたちの成長を支えあえるまちづくり~」「子ども・若者の自立をみんなで応援 希望が持てる未来を」との理念が掲げられています。
外国ルーツの子どもたちももちろん、「すべての子どもたち」に含まれる川西市民です。そして、特有の困難を抱えています。私たちは、川西市に暮らす市民として、彼ら彼女らの成長と、キャリアの形成によって、共に生きる社会が実現することを願ってやみません。
外国ルーツの住民への、市行政による適切で、的確な施策があってこそ、川西市は、これからも増え続ける外国ルーツの住民、少子化の中で私たちが多くを頼っている外国ルーツの市民が、共に「希望が持てる未来」を展望する街となり、私たちの川西市に活性化をもたらすものと確信いたします。
そのためには、まず何よりも、実態を把握すること、外国ルーツの住民への調査が必要と考えます。そして、その調査結果をもとに、市としての多文化共生の政策が形作られ、私たちが日々関わっている、外国ルーツの子どもたちが、川西市民として共に未来を描けるような街になることを心から願っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
