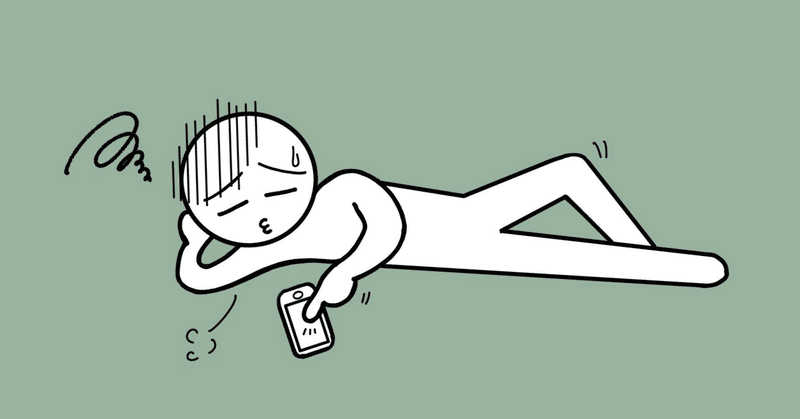
新米日本語教師2022年の授業準備奮闘記
2022年6月に日本語学校に採用が決まりまして、週1回4コマ、初級クラス(20人)を担当させて頂くことになりました。
数えてみますと、今までにした授業回数は、19回とあまり数はこなしておりません。
使用教科書は、『みんなの日本語 第2版 初級Ⅰ・Ⅱ』です。
うちの学校は、例えば、「5課 A1‐3」など、担当する文型に指定はあるのですが、必ず、教科書の通りに授業しなければならないわけではなく、それ相当の練習ができていれば良いという、かなり自由度の高い学校です。
教案は、主任の先生に提出してチェックしてもらえますが、他の先生の授業見学はしたことがないので、完全に手探り状態でオリジナルの授業を作成しなければなりません。
私はコロナ時代の養成講座受講生で、非同期型のe-learningでの授業がほとんど。急遽、付け焼刃でつくられたようなe-learningも多かったですし、申し訳ありませんが、正直、養成講座の内容は、高額な割には、全く不十分なものだったと思っています。
(今、文化庁では、日本語教師の「質」の確保についての検討が繰り広げられていますが、あのような養成講座では、本当にダメだと思います。)
そして、実習でも45分の授業を1回も作ったことがないまま、養成講座を修了してしまった私は、おかげで、現場に出てから、本当に苦労しました。
「どうやって授業を組み立てたらいいのか全然分からない!!!」
こんな私が模擬面接を通過して採用されたのは、ひとえに、私の模擬授業は同期の仲間たちと先輩に作成をほとんど手伝ってもらったからに他なりません。(こんなところでバラしてしまった)
そこで、あとで振り返ってみたら面白いかと思いまして、2022年、なんとか19回の授業をし終えた私の「集大成」を、記録として、ここに残すことにしました。
授業準備 Step1:教科書分析・文法分析
まず、私の授業準備は、先輩から強引にお借りした、先輩の書き込みだらけの『みんなの日本語』の教科書を観察するところから始まります。
そして、次に、定番の『みんなの日本語 教え方の手引き』を参考にしながら、教科書分析を始めます。

次に文法分析に入ります。私が参考にしている本は以下の4冊です。


この文法書を読んでいると、どのようにその文法を解釈し、授業で導入したらいいのか、
アイディアとイメージが浮かびあかってくるようになったのです。本当に大好きな本です。
あと、Tomo塾の仁子先生のサイトもとても分かりやすいのでよく参考にさせてもらっています。
授業準備 Step2:文型の使用場面を考え、導入を考える
ここで失敗すると、全てがうまくいきません。
私が今、授業準備で一番時間をかけているのはここだと思います。
「これだぁ!」というアイディアが沸き上がってこないと、本当に苦しい授業準備時間が続きます。アイディアが湧いてこなくても、授業はしないといけないので、苦し紛れに、手引き書を真似して授業をしても、全然、うまくいきません。そのような失敗を繰り返し、「私は日本語教師に向いていない」と何度も思いました。
苦しんだ末、今、感じていることは、授業の形を整えようとして導入を考えるより、文法理解と分析に時間をかけた方がアイディアが湧いてくる、ということです。
しかし、文法理解の浅い新米の私の頭で、『日本語文法ハンドブック』なんか見つめていても時間ばかり過ぎるので、以下のような本の助けを借りています。

また、直太朗さんという方がNOTEに『みんなの日本語』についての解釈を詳しく投稿して下さっていたので、すがるような気持ちで読ませて頂きました。
そして、何度かコメントでやり取りをさせていただいた後、私のために記事を1本書いてくださったのです。
私は日本語学校で日本語教師が授業するところを一度も見たことがありませんので、全くイメージが湧かないという問題に苦しんでいました。けれども、この記事を読ませて頂いたときに、「あ、そうか」という気づきがあり、1つの関門を突破できたように思います。本当に感謝しています。
また、文型の使用場面を考えるという意味で、以下の初級教科書を参考にしたりもします。

『できる日本語』は会話場面を参考にします。
先輩が、『みん日』と『できる日本語』の文法対応表を作成してくださり、検索がすごく楽になりました。
『いろどり』は、トップダウンでの音声インプットの仕方などの教授法を真似したりします。
授業準備 Step3:基本練習問題を作る
最初のころは、パターンプラクティス用の問題を山ほど作成して、ひたすらドリル演習させることが、私に課せられた仕事だと思っていました。
何回かそんな授業をした後、すっかり嫌気が差してしまい、『みんなの日本語』を使用している学校で働くのはもう辞めようと思いつめました。
しかし、直太朗さんからアドバイスを頂き、また、「練習B」が単なる問題ではなくて、やり取りを伴った場面に見えてくるようになった頃から、
『みんなの日本語』という教科書は、ものすごい情報量過多ではあるけれど、その一つ一つの情報はよく練られているので、それを少しずつ取り出して、生きた場面として扱えばいいのだな、と感じるようになりました。
また、基本練習のときに、ペアワークにしたり、何か飽きさせない工夫をしたり、ちょっとだけテクニックがついてきたように思います。

授業準備 Step4:応用練習、活動を考える
最初のころ、応用練習って言ったって一体どうしたらいいのか皆目見当もつかない。そして、以下のような本を参考に何かやってみるのだけれども、Queがうまく出せないということが続いていました。

今でも、応用練習を考えるのは得意な方ではないと感じているのですが、
Step2の文型の使用場面を考えている時に、アイディアが浮かぶということが起こるようになりました。アイディアが浮かびさえすれば、あとは、教材作成に時間がかかろうともそこまで苦しい作業ではなくなります。
そして、時間が足りなくて、応用練習の時間を十分にとれない、という事がよく起こります。
まだまだ、時間配分では、課題が多いです。
自己表現活動
ところで、私は、西口光一先生が開発されたマスターテキストアプローチにものすごく興味を持っており、自分の授業で使えないかなと思って、活動として、自分でイラストを書いたり、マスターテキストを作成したりして、何度か導入を試みたことがあります。
マスターテキストアプローチの存在は、西口先生のNOTE記事に惹かれて読むようになってから知ったのですが、同じマスターテキストアプローチである、地域の日本語学習者用に作られた『きいてまねしてはなして』の教材を地域のボランティア教室で使うようになってから、さらに魅力を感じるようになりました。

今後もこの試みを続けていこうと思っています。
授業準備 Step5:授業構成を考え、教材を作成する
ここまで授業準備が終われば、あとは気持ち的にはラクチンです。
教案は、Googleドキュメントに書き出すのが、私の好みです。
教案を主任の先生に提出していた時は、一言一句、セリフを書いていましたが、今は、自分が分かる程度のメモと、授業の流れを整理するために書いています。
教材に関しては、なるべくパワーポイント作成に時間はかけるまいと、口頭や板書で何とかするよう努めています。
聴解の音声などは、授業でスムーズに再生できるように音声トリムで、問題ごとに切り取って、PPTに貼り付けています。
フラッシュカード、レアリア教材、活動で使う小道具、ロールプレイカードなど、そういったものを作成、準備します。
授業準備 Step6:授業をイメージする
最初の数回は、部屋で声に出して、小道具も使って練習していたのですが、最近では、出勤する電車の中とか、モーニングする時のカフェで頭の中だけのイメージですませてしまっています。
以上が、2022年、通算19回の授業をし終えた私の授業準備「集大成」となります。
その他
初級のメインテキストの授業準備だけで、上記のような奮闘を繰り広げました。
他にも、私が初級でしなくてはならないことは、漢字、発音、語彙導入、読解、聴解、作文指導、会話活動です。
来学期からは、JLPT対策も入ってきそうです。
積読図書がもう山積みです。

Ⅱは、今年の夏刊行予定だそうです。
Ⅱのテーマは、文法指導、会話指導、作文指導、総合的な指導
また、時間ができたら、他の項目についても投稿してみようと思いますが、たぶん、授業準備に追われて、書けるのは、春休みか夏休みか、1年後の正月休みか・・。
読んでくださってありがとうございます。
追記:
昨年は、散々、私の嘆き悲しみ、愚痴、かと思うと、興奮した私の授業実践報告を長文で読まされた仲間の皆様に、大変お世話になりました。
いつも本当にありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
