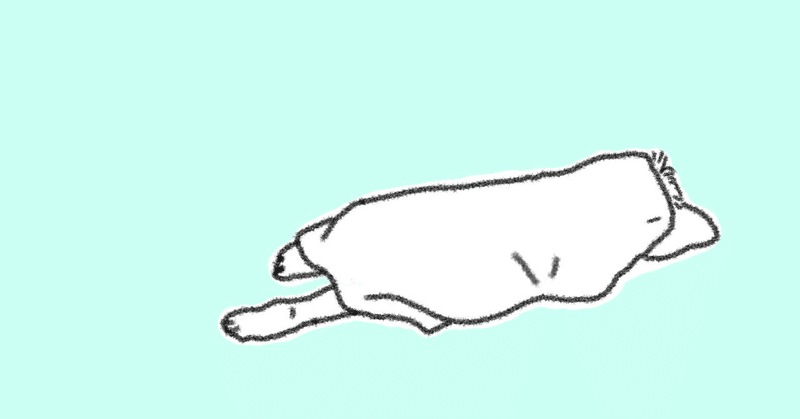
ワタシハニホンゴキョウシニハムイテイナイ病
私は今、「ワタシハニホンゴキョウシニハムイテイナイ」病を患っている。なぜならば、勉強が苦手な学生たちが集まっているクラスで、基礎練習をしっかりせねば、自由度の高い活動へは進んでいけないという現実に直面しているが、文型積み上げの世界でどのようにしたら、生き生きとした授業展開をすることができるのか私の力遠く及ばず、この基礎練習の時間が、どうしても好きになれないからだ。
文型の基礎練習、これは、私がピアノが嫌になった、あの感じによく似ている。
子どもの頃。
家にはグランドピアノがあって、私はよく時間が経つのも忘れて好きなように弾いて遊んでいた。ところが、ある日、私の自由な演奏を聞いていた親が「この子は音楽の才能があるに違いない」と大盛り上がりし、近所のピアノ教室に連れて行かされることになった。小学校1年生の頃だったかな。
別に自分から行きたかったわけではないピアノ教室でまず、赤バイエルをさせられた。
私にとって印象深いのは、赤バイエルの「ドレドレド」
「猫の手、指使い!」とやたらと注意されながら、弾き続けるのだけど、何がダメなのかさっぱり分からなかった。
それで、両先端がそれぞれ赤と青になってる色鉛筆の赤い方で、(先生はやたらと筆圧が強い方だった)刻々と「ダメの烙印」を押される。いや、つまり、チェックされたら、もう1回家で練習して来てねって意味だったのだけど、まぁ、私からしたら「ダメの烙印」。
楽しくピアノで遊んでいただけなのに、ある日、「私の音楽」は「赤バイエル」「黄バイエル」の練習に、「私の遊び」は「宿題という義務」に取って代わり、練習をして来ないと叱られるようになるので、「練習不足という罪悪感」と共に教室に渋々通うようになる。それを何年も続けていたら、ピアノなんか大嫌いになってしまったという、まぁ、私の年代の女の子達にはよくある話しなんだと思うが、
コミュニケーションの道具である「ことば」の活動を、文型で種類分けして、延々とリピートさせたり、パタプラさせたり、ドリル練習をさせるのが、指使いの練習のために「ドレドレド」を延々とさせられたあの感じに似ている。
もちろん、基礎練習は必要だと思う。
でも、練習している音が音楽が聞こえなかったら、やる気になれない。
私のクラスは、私の力及ばず、どんどん活気を失い、音楽(日本語でのコミュニケーション)に関心は示さなくなり、多くの人はもう踊って(活動)なんかくれなくなった。
そして、教科書開いても、私の耳にも音楽が聞こえなくなってきて、もう嫌だという拒絶反応で授業準備が捗らない。
これが、ワタシハニホンゴキョウシニハムイテイナイ病の正体。
結論:
『みんなの日本語』(文型積み上げ式の教科書)を使いこなすというのは、豊かなシンフォニー(文脈)の中で、いかに生きた音楽としての「ドレドレド」(文型)を演出し、演奏者(学習者)に鳴らせることができるかどうか、コンポーザとしての力量と、コンダクターとして振舞う事が求められるんだと思う。
私のバイエル練習も、先生が弾いてくれる音楽の中で「ドレドレド」を慣らすことをリードしてもらっていたら、美しい音色を出すために、何故、指使いや「猫の手」が大事だったのか、感じとることができたんだろうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
