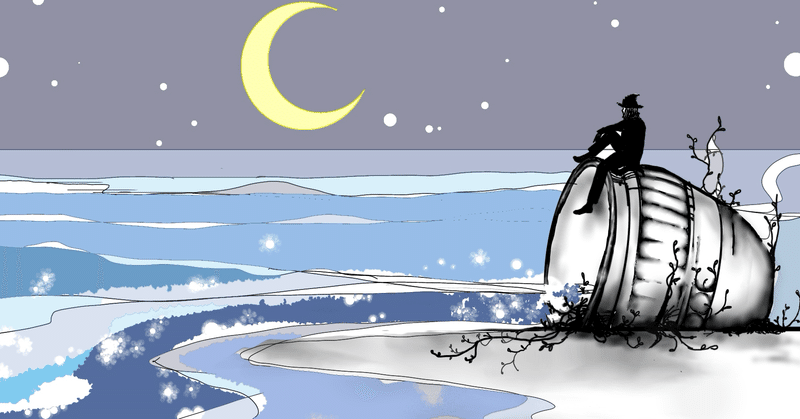
論文の「書き方」にコツはない
「予備試験の論文どうやって書いたらいいですか」という旨の質問をたまにもらう。
「書き方などない」というのが私の答えである。
もちろん、それっぽいアドバイスをすることはできる。
「問題の所在をまず提示しましょう」
「規範はコンパクトに」
「あてはめは事実のコピペがメインです。評価は一言あればいいです。」
「法的三段論法を意識しましょう」
「分かりやすくナンバリングしましょう」
しかし、はっきり言って、これらのテクニックは合否に影響しない。
「上位合格者しか知らない秘密の論文の書き方」のようなものは存在しない。ほとんどの合格者は、文章の書き方を特に学ばないまま、予備試験や司法試験の論文に合格してしまうのだ。かくいう私も、誰かから論文の書き方を教わったことはない。しいて言うなら、予備試験の直前に受けた模試で添削を受けたぐらいだ。それでも論文試験では上位に入ることができた。
では、論文を上手く書けない人はどうすればいいのか。「模範答案を真似する」これに尽きる。
法律の文章というのは、特定のパターンや型がある。法的三段論法もそのうちの一つだ。そのようなパターンや型は自分で頑張って捻りだせるものではない。誰かが書いたのを見て真似して覚えていくしかない。司法試験や予備試験の模範答案になるような文章はだいたい判例の文体を真似して作られたものであり、その判例というのも古い判例の文章を真似して再生産されたものである(その究極の起源がどこにあるかは知らない)。
だいたい、司法試験・予備試験の科目で出てくる論点は限られている。オリジナリティのある書き方を要求される場面は、滅多にないのだ。「原告適格が出てきたら規範を提示して個別法解釈やって被侵害利益検討して…」「因果関係が出てきたら条件関係検討して介在事情の寄与度を評価して実行行為との関連性を検討して…」というように、特定の論点に対する処理手順は決まっている。答案ではその処理手順に従って文字を埋めていくだけなので、「書き方」を意識する場面がまずないといってよい。
そして、これらの処理手順や書き方は、過去問や問題集の模範答案を見れば一目瞭然である。模範答案のない学者が書いた演習書を使うべきでない理由の一つはここにある。
普通に過去問を何周も回していく過程で模範答案を何十回、何百回と読めば、意識しなくても「それっぽい文章」は書けるようになる。「書き方がさっぱり分からない」と言っている人は、そもそも模範答案を大量に読むという過程を踏んでいるのだろうか?もちろん、良質な模範答案を選ぶべきであることは言うまでもない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
