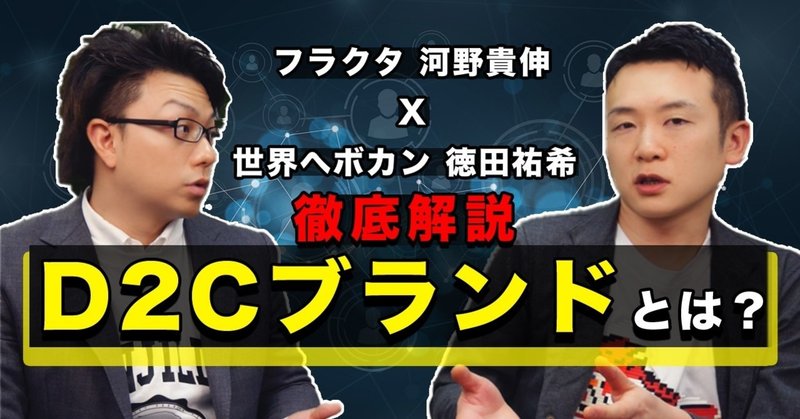
D2Cとは、「顧客と心のつながりを持つ」こと。フラクタ・河野貴伸氏に訊く
徳田祐希(以下、徳田) こんにちは、「世界へボカン」代表取締役・徳田祐希です。弊社は、英語圏の越境ECに特化したWebマーケティングを得意とする会社です。
本日は「D2Cブランドのブランディング」について、Shopify 日本公式エバンジェリストであり、弊社のブランディングのアドバイスもしてくださっているフラクタの河野さんとの対談をお送りします。
このインタビューは、以下の方向けです。
・D2Cブランドをお持ちの方
・D2Cブランドをこれから立ち上げる方
・D2Cブランドの今後が気になる方
何か一つでも気づきや学びがありましたら幸いです。
話し手:河野貴伸氏
株式会社フラクタ 代表取締役。Shopify 日本公式エバンジェリスト。「日本のブランド価値の総量を増やす」をミッションに、ブランドビジネス全体への支援活動及びコマース業界全体の発展とShopifyの普及をメインに全国でセミナー及び執筆活動中。
"心のつながり"がダイレクトにできること
河野貴伸(以下、河野) 株式会社フラクタの河野貴伸と申します。弊社は「デジタルネイティブ ブランディングエージェンシー」を掲げ、ブランド構築をお手伝いさせて頂いています。また、ShopifyというECのSaaSのサービスのエバンジェリストもやらせていただいております。
徳田 河野さん、「D2Cブランド」という言葉をよく聞きますが、正確にはどういった定義なのでしょうか?
河野 よくいただくご質問ですね。恐らく皆さんもネットの記事や様々な書籍でD2Cについて学ばれているかと思います。そういった前提はありつつ、改めて整理した視点でお伝えしたいと思います。
まず"D2C"とは、「Direct to Consumer」「Direct to Customer」などの略です。

ただ「ダイレクト」で誤解されがちなのは、「直販」という解釈だけで捉えられること。「日本にはEC直販のブランドっていっぱいあるよね」「別に新しくないのでは?」という考え方も出てきます。
一方で、eコマース(EC)はずっと伸びています。「一体何がダイレクトなのか」というと、"お客様と直接つながりを持つこと"です。
Amazonや楽天で売ってることは"ダイレクト"ではない、D2Cではないという見解です。お客様と共感などの"心のつながり"がダイレクトにできることが、一つの定義だと思ってますね。

徳田 1WAYじゃないんですね。
「中間がないから安くなる」だけではない
河野 そうですね、双方向です。その要因は、まさしくテクノロジーの発展だと思ってます。

商品が単一の流通だけだった頃は、一方的に流れてくる商品を顧客が選ぶか選ばないかだけでした。今は「お客様がこういった商品を求めている」ということをメーカー側が理解でき、販売員がハブになって商品開発に活かしたりといった双方向の流れができています。
お客様の考えていることを商品の作り手、メーカー、ブランドがダイレクトにやり取りできるようになった。ここで少しずつ生まれてきた概念が、ここ最近になって体系化されてきたように思います。
直販イコール「中間がないから安くなる」だけではなく、もっとフィードバックをダイレクトに受け取れたり、商品の開発に活かせたり。
徳田 そういうところがD2Cの醍醐味ですね。
河野 そうですね。なぜD2Cが伸びてきたのか。よく言われるのは、アメリカでたくさん立ち上がっているD2Cブランドは中間コストを省いて「良いものを安く提供している」ということ。
一方、皆さんがかなり疑問に思われるのは、ひいき目に見ても「日本製の商品の方が良いのでは?」という状況だと思います。
河野 アメリカの(D2C)だと、Casperというベッドのブランド、Warby Parkerというメガネのブランドがあります。彼らはすごく丁寧で、スタイリッシュなモノづくりをしています。僕は好きですけど、一方で日本のメーカーが商品力で負けているかというとそんなことはありません。
忘れてはいけないのは、彼らは「顧客とダイレクトにやり取りをする」ことを念頭に置いて設計しているということです。

テクニックではなく「スタイル」
徳田 宅配で届いたメガネを試着し、ハッシュタグ #warbyhometryonと共にInstagramに自撮り写真を投稿すると 、Warby Parker公式からコメントがつくんですよね。こういったインタラクティブな感じは、すごく良いですね。
河野 そうですね。「顧客との双方向のやりとり」をするD2C的なブランドやお店は、日本でも歴史をさかのぼるとたくさんあったんですよね。
だから、日本でEC支援をされている方やアパレルブランドを展開されている方は、D2Cを見た時に「なぜそんなに新しいと言われるのか?」疑問に思われるんですね。
D2Cブランドが出てきて何が良くなったかというと
「顧客との直接のやりとりを考えよう」
という概念ができあがったことだと思うんですよね。
テクニックではないブランドとしての在り方、"スタイル"が大事だということが、一部でなく全ブランドで考えるべきことになってきた。すごくいいことだと思っています。
徳田 物が売れなくなった時代では、情緒的な価値や、企業の存り方、スタイルみたいなところが共感を生んで商品を購入するきっかけになりますね。
河野 そうですね。奇しくもコロナがあり経済が停滞してる中で、僕が感銘を受けたのは例えばうなぎパイの「春華堂」さん。
高速道路のパーキングエリアなどでお土産として売っていたものが、(コロナで)売れなくなった。そうして春華堂が生産中止を発表すると、「中止してほしくない」「買い支えたい」と言う声がたくさん届いたらしいんです。
これこそが双方向じゃないですか。お客様側からメッセージを発信して、企業が頑張れるっていうのもそう。
一方、ヨーロッパではラグジュアリーブランドが自分の商売を差し置いて、社会に貢献する行動を起こしました。社会を良くするために助成金を断わったり、自分たちの工場を使って消毒液やマスクを作ったり。これはまさしく"スタイル"なんですよ。

D2Cは「周囲を淘汰する」ものではない
河野 つまりビジネスとか目先の利益とかではなくて、「自分たちの存在は何なのか」「世界に何を求められているのか」「なぜ存在してるのか」これらを語れるからこそやれることだと思います。
徳田 今こそブランドの"在り方"が試されるタイミングですね。
河野 そうですね。在り方が試される場面が急速に増えていると思うんですね。D2Cブランドの在り方は、今までのものを上回って周囲を淘汰していく、ディスラプトしていく話ではないと思っています。
D2Cはお客様と直接やり取りをして、お客様から支持される、信頼されるブランドにならなければいけない。そのようなムーブメントのきっかけだという風に捉えています。

ただ今のD2Cのやり方は、まだ発展途上なんですよ。アメリカなどでは(D2C企業が)多額の資金を集めて上場を目指し、実際に上場したけれど広告費の比重が多すぎたり。ネガティブな側面も見えてきています。
これで「D2Cはダメ」「単なる流行り言葉だよね」と捉えるのではなく、発展途上にある思想の一部と捉えて次に活かしていく。D2Cという言葉はブランドのあり方における中間点、まだまだ発展途上だというのが僕の中での定義です。
<今回の記事のまとめ>
①D2Cブランドとは?
・Direct to Consumer (Customer)の略称。
・テクノロジーの発展により、ブランドと顧客の関係性が 単方向→双方向になった事で生まれてきた概念。
②なぜ注目されているのか
・ブランドと顧客間の「双方向のやりとり」が重要だから。
・ブランドの「スタイルの確立」が重要だから。
③これからのD2Cブランドの在り方
D2Cは「発展途上にある思想の一部」として捉え、
ブランドの在り方における「中間点」として未来に活かすべき。
河野 貴伸(こうの・たかのぶ)氏
株式会社フラクタ 代表取締役
Shopify 日本公式エバンジェリスト
「日本のブランド価値の総量を増やす」をミッションに、ブランドビジネス全体への支援活動及びコマース業界全体の発展とShopifyの普及をメインに全国でセミナー及び執筆活動中。
株式会社フラクタ様
ブランディング事業を柱に、ブランド戦略策定からマーケティングコミュニケーション設計、ECサイト制作などをデジタルネイティブに一貫して実行。プロフェッショナルたちの専門力と、カテゴリと媒体の垣根を超えた実行力により、ブランドにとっての象徴的な体験「シンボリック・エクスペリエンス」を実現するとともに、ブランドの新しい可能性を広げる。
世界へボカン株式会社は、英語圏の越境EC・BtoBマーケティングに特化したWebマーケティング会社です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
