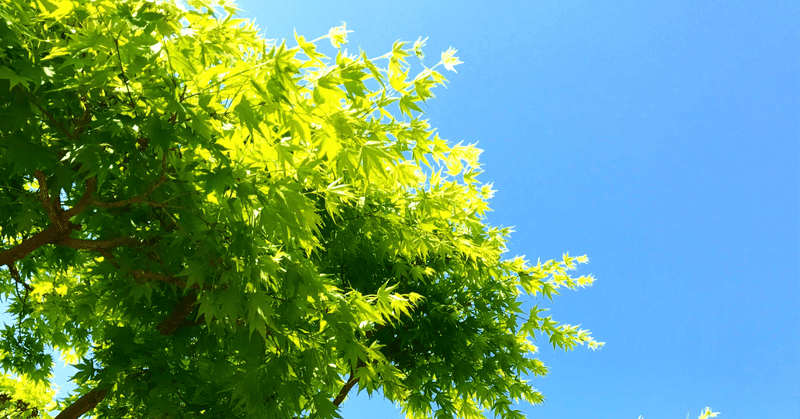
天神山にのぼろう
佐藤正午作「冬に子供が生まれる」の二次創作小説を書きました。
いろいろ「その後」を考えていたら描きたくてたまらなくなって。
では、いきます。
* * *
天神山にのぼろう
「理科の理と書いてオサムと呼びます」
佐渡くんは自分の名前をそう説明する。
あまり覚えてくれる人はいない。苗字だけで事足りるくらいの存在なのだと自分では思っている。
佐渡くんは、息子の創理(ソウスケ)が18になるのを待って妻の美典(ミノリ)と離婚した。
妻は結局タバコを辞めることができなかった佐渡くんのことを心底軽蔑していたし、自分の説得が届かないことにたいして憎しみすら感じていた。
「しばらくは辞めてたのに、なぜに緩慢に自殺していくの。わたしを未亡人にしたいの?」
と責め立てた。
でも、タバコはただのきっかけなんだと思う。妻はそれ以外にも、佐渡くんがこだわっているもの、大切に思っているものが嫌いだったのだと思う。憎しみすら感じていたかもしれない。うまく言えないけれど(自分がけして関わらないガラクタ)が佐渡くんの心の中には詰まっていて、それを排除できない佐渡くんのことを(軽蔑すべきつまらない人間)だと思うようになってしまっていたのだ。佐渡くんはもうとっくに妻に理解されることをあきらめていたのだけれど。
「せめて創理が高校を卒業するまでは」と妻は言ったが、それは形式とかお金の問題で、気持ちではもう5年以上は離婚しているようだと佐渡くんは思う。
未練はない。そもそも、なぜあのときに美典を一生をともにしたいと思ったのかさえ、今は思い出せない。
県内の国立大学に進学することになった息子は、通学時間を考え大学の近くのアパートを借りた。
妻はそのまま市内のマンションに残った。
佐渡くんは、会社まで歩いて15分ほどの坂の上のマンションを借りた。ワンルームにキッチンがついているだけだが、7階からの眺めはとても気持ちいい。
こんもりとした森の向こうに、通っていた高校のグラウンドも見える。
そう。
あのグラウンドで野球をしていたのがマルユウだった。
湊先生は、マルセイの後を追うように、翌年になくなった。
2度目の脳梗塞は、たまった新聞に気づいた近所の人が勝手口から入って発見されたのだという。
机の上には、推敲途中の原稿用紙と、万年筆が置かれ、そこにうつ伏せたまま、湊先生はなくなっていた。
自分はそんなに友達が多いわけじゃないし、話したいと思った相手もいなかったと、
佐渡くんは思う。
でも、公園などで中学の恩師である湊先生を見かけると声をかけないではいられなかった。
湊先生は、妻の言うところの(心の中のガラクタ)と繋がっていて、それは佐渡くん自身が静かに大事にしているものだった。
一方で佐渡くんにはいつも「自分は愛されなかったのだ」という気持ちがつきまとっている。
誰に?
自分は、誰に愛されなかったのだ?
それを考えようとはするのだが、佐渡くんはその気持ちが(妻)に対するものではないこと以外何もわからない。
そこの部分だけ。
空気にもやがかかっているようになっていて、どうしても記憶がないのだ。
* * *
「不思議ね。同じような話を以前父から聞いたことがあるの」と本田は言った。
「結局は愛されなかったのだって。事故で即死だった父が死際にそんなことを言うわけないのに。なぜかわたしの記憶では、父が死際にそう言ったことになってるの。でもそれは記憶の間違いだと思う。どこか別の機会に言ったのだと思う。そのときわたしは悲しかったわ。自分が愛されなかったって何? 父のことはずっと好きだったのに、その言い様は何? そして、わたし自身もまた、結局は父に愛されてなかったと思うようになってしまった。それがどういうことかわからないけれど。愛している人に愛されていない空虚さみたいなものだけがなぜか、父がなくなってからずっとあるのよ」
本当はそんなことはなかった。父とわたしは仲の良い親子で、わたしはたしかに愛されていたはずなのに、と本田は付け加えた。
本田の著書「ワッキー伝説」はベストセラーとまでは行かないまでも、ロッカー脇島田ファンのあいだでは話題となり、それなりの売り上げをあげた。
高校時代にバンドをやろうと言いだし、そののちに脱退した初代メンバーについては深く触れられなかった。友人のおもしろおかしい証言にはページを割いていたが、初代メンバーであるマルセイの名前やその後については語られなかった。死者からの証言は得られない。周りの話だけで彼を語ることは適切ではないと本田は判断した。
佐渡くんは本田の決断を好ましく思った。
佐渡くんは、自分の代理店での仕事のひとつを本田にお願いしたいと思い連絡をとったことがある。それはうまく行きそうで、結局は疫病の蔓延から頓挫してしまったが、その後も本田との交流は続いた。
自分は彼女の取材や文章の作り方について知っている。
そして、彼女が適役だと思う仕事はいくつもあった。
仕事のやりとりがZoomでできるようになると、それほどの障害もなくなった。
その後いくつかの仕事を本田にお願いしたし、仕事のやりとり以外でも、なんともなく二人でZoomで話すことも増えた。
本田の言う「愛されなかった」という形のない感覚。
佐渡くんも感じてしまうその感覚が結局何なのかはわからないのだが、それでも、二人の中には何かしら似たものがあるのだと、双方が感じていた。
そしてそれは(マルユウ、マルセイに関するもの)だとうっすらとは思っていたが、それを言葉にするのはむつかしかった。
むしろ、それは(余分な記憶)であって、どこかに捨ててしまってもいい、そういう気持ちすら、ふたりの中にはあったのだが、それすらもあえて言葉にすることはなかった。
* * *
マルユウと真秀(まほ)の子供の名前は「流星(リュウセイ)」と言う。
子供が生まれたとき真秀の母である杉本先生は「マルユウそっくりの男の子じゃないの!」と言って号泣した。
その様子を見てマルユウの父は、はにかむように笑った。
「この夫婦が何も言わぬなら何も聞かないでおこう」
その子供の顔を見たときに、二人は同時にそう決心した。
氷のように押し黙っていた真秀もマルユウも、「流星」の顔を見たとたんに安心のあまりに氷が溶けたような感覚に陥った。
「遊星という名前を、ふたりで考えたんだ」とマルユウが言ったときに、マルユウの父も真秀の母もぷっと吹き出した。
「マルユウとマルセイで遊星? 悪くはないけれど、いかにもすぎるな」
「そうそう、それじゃあ、いつまでもいつまでもマルセイを思い出してしまうじゃない。遊星じゃなくて流星なんてどうかしら?」
そんな簡単な会話のすえに子供の名前はあっというまに流星となった。
誰も反対しなかった。
流星がすべてを結びつけた。
流星は名前のとおり流れ星のごとくやってきて、誰もが流星に心奪われた。
流星はすごい、と、マルユウ夫婦は思わないではいられなかった。
* * *
「今日は、マルユウ夫妻が来るんだよ」
佐渡くんは本田とzoomで話している。
「噂の、聞きしにまさるのまさるくん!実はまだお会いしたことがないのよ」
「え? そうだっけ?」
「ふたりの子供、流星を連れてきてくれるんだ。早いもんだよね、もう小学3年らしいよ」
佐渡くんが転校してマルユウに会ったくらいの年だ、早いものだ。
「本田に紹介するよ。何年会ってなくても僕の数少ない友達だよ」
「いつもZoomごしだけどね。紹介してほしいわ」
その会話の最中にチャイムが鳴った。
予定していたマルユウ一家と思いきや、佐渡くんの息子の創理が立っていた。
「あれ、なんで?」
「大学入って免許とって、車買ったって言っただろ? 親父にも見せようと思ってドライブしてきたんだよ」
「アパートから? ずいぶんな距離だな」
「ずっと自分の車が欲しかったから。ぜんぜん苦じゃないよ。実を言うとおかあさんがお金出してくれたんだけどね。それって結局親父が払ったお金だろ? だから親父に見せなきゃって思ってさ」
本田がZoomごしのそのやりとりを聞いていたら、創理がちょこんと挨拶したからびっくりした。
「親父、ごめん、お話し中だったんだね」
「いや、ただ話していただけだから」と佐渡くんは言う。
「実は、離婚したあとの親父のことが心配だったんだよ。どうやって生活するんだろうって。友達もろくにいないのに。時間を持て余してやしないかって。でも、ちょっと安心しました」
本田は、本を作るときに取材したことや、仕事で世話になっていることを簡潔に説明した。
佐渡くんは少し顔が赤いように見えた。
本田はいつもクールな佐渡くんの狼狽した様子がとてもおかしかった。
ほどなくしてもう一度チャイムが鳴り、マルユウ夫婦がやってきた。
実はマルユウに会うのも流星が生まれたとき以来だ。
流星は(小学生の頃、転校してきて出会ったばかりのマルユウ)にそっくりだった。水筒をぶら下げている? 水筒? いまどき水筒をぶらさげている子供なんているのか? でもこれがないと落ち着かないのだという。
妻の真秀が言った。
「なにからなにまで、自分の思ったようにする子よ。そしてわたしたちの子供にしてはちょっと活動的すぎる」
「当たり前だよ。おれ、お父さんとお母さんの子供じゃないもん、宇宙からやってきたんだもん!」
「もう!自分からお父さんとお母さんの子供じゃないなんていう子供がいますか!おじいちゃんもおばあちゃんも、そんなこと言ったら本気で悲しむわよ」
「悲しむかなあ?」
「悲しむわよ! 大事な孫がそんなこと言うなら」
「じゃあ、この話は秘密にしとく!」
もういっぱしのキッズギャングだ。マルユウはその様子を静かに笑いながら眺めている。
マルユウは病院の事務長になったという。理学療法士の資格は取らなかったが、社会福祉士の資格をとったらしい。
「できれば持っていた方がいいって言われたしね」
と、マルユウは言う。
それでもマルユウは変わらない。いつもどおりのマルユウだ。
真秀は中学校の先生を続けている。
そして流星は野球をやっているんだと話す。
「じいちゃんが前に監督やってたんだって!」と自慢する。両親の帰りはそう早くもないため、同居するマルユウの父と野球の練習から一緒に帰り、夕食を食べてすごすのだと言う。
「ねえ、流星くん。お兄さんの車でドライブしない?」
マシンガントークが止まらない流星に創理が言った。
「うん!行きたい!あ、でも、お母さんが知らない人についていったらダメって言うよ」
「流星。創理くんは佐渡くんの子供だし、知らない人じゃないわ。行ってきなさい」
「やった〜。ねえ。創理にいちゃん、天神山って登ったことある? おれ、天神山に行きたいんだ。友達から教えてもらってさ。すごい眺めがよくてかっこいいんだって!!」
「天神山かあ」
創理はつぶやいた。
「いいよ、おれも流星くらいのときに天神山に行きたくてたまらなかった。行って宇宙船を見てみたかった」
「大人のくせに何言ってんだよ〜。宇宙船なんているわけないじゃない?まあ、でも創理にいちゃんが見てみたいんだったら、一緒に待ってやってもいいけど?」
真秀がぷっと吹き出す。
「もう、いいからいいから。ふたりで、行ってきなさい。すみません、創理さん、お願いします。とちゅうでハンバーガーを買っていくといいわ」
真秀がそう言って財布を出すものだから、流星は喜んでお金を受け取り、創理の手を引いて出ていった。
* * *
「不思議だな。昔はマルユウにいろんなことを聞いてみたかったんだよ。でも、そう思っているときは会わなかったし、いざ、こうして会ってみると、何を聞きたかったか忘れてしまった」
マルユウはふふっと笑った。
「びっくりしたよ。うちの病院の待合席に佐渡くんがいたから。知ってたの?僕が勤めてるって」
「いや、風邪を引いて偶然駆け込んだだけ。熱はなかったけれど、最近はみんな神経質だから、病院にも行かないっていうと責められそうでさ」
Zoomだとどうしても会話に加われなくなってしまうのだが、本田は画面越しに3人の旧友をじっと見つめていた。
言葉が少ない。
まるで、いるだけで通じあっているように。
言葉少なく。なんとなくコーヒーを飲んだり、窓際の多肉植物を眺めたりしている。
それは「おたがいに愛されている」と感じるに足りる光景だった。
ときに自分が見放されたように感じる瞬間があったとしても。
それでも世界は続いている。
本田は、取材を通していろんな悲惨な出来事を目の当たりにしてきた。
茫然とするほどの大災害や、世界全体が疑心暗鬼になってしまう疫病。そう言ったものを実際に見てしまうと、頭を抱えて絶望することも幾度となくあった。
そして、戦争もなくならない。
偶然に亡くなってしまう人や、家をなくす人、病に苦しむ人。
なぜにこの星にはこんなに災害が多いのだろう?
自然はなぜに人間の営みを愛さずにこんな試練を与えるのだろう?
そう、「愛されていない感覚」はここに通じる何かなのかもしれないとも思う。
絶望の中で「神よどこに行きたもう」と叫んでも、手を差し伸べるのは神ではない。
取材という場面の中で、手を差し伸べるのは、気持ちを支えてくれるのは、いつも近くにいる誰か、離れたところから駆けつけてくれる誰かだ。
その人は、マルユウのような、真秀のような、そして佐渡くんのような、いつも当たり前のような顔をして、何もなかったように静かに過ごしている人。
案外そんな人たちではないのか?
本田は、そんなことを考えながら、3人のことを画面ごしに眺めていた。
* * *
「そういえば、お母さんの方の杉森先生は元気?」
佐渡くんの問いに、真秀がコーヒーを飲みながら答える。
「元気よ。あいかわらずのひとり暮らし。ぜったいにあの家を離れないの。お父さんの思い出が詰まっているからって。そして、わたしやマルユウが同居の話をしてもぜったいに許さない。あの人にはあの人の理屈があって。とても頑固なのよ」
うつ病を発症したり、軽快したりを繰り返していた杉森先生は、少しばかり認知機能の衰えも出てきた。
薬さえ飲み忘れなければおだやかに過ごせるが。飲み忘れるととたんに後悔の波が襲ってくる。襲ってくるともうダメで。その日は全く動けなくなってしまう。
今は介護サービスを使って、薬を飲んだか確認してもらったり、通いのデイサービスのようなところでお風呂に入ったりしているという。
「有料老人ホームの併設の小規模多機能っていうサービスなの。いつか、家で暮らせなくなったら、そこの老人ホームに入ればいいと思って、もう3年くらい利用しているの。母は最初は嫌がったけれど、利用してよかった。だってこの3年間、まったく症状が悪化しないのよ」。
真秀はそれから思い出し笑いをした。
「そうそう、母がね、いつも送ってくれる介護士さんのことを、マルセイって呼ぶのよ」
え?
「杉森先生、ありがとうございました、またお会いしましょうって彼が言うの。おそらく先生って言った方がいいだろうと思ってなんだろうけど。マルセイよりもずっと華奢でひょろひょろしてるし、似ても似つかない人。話し方もぜんぜん似てない。天然パーマの髪を染めてて若くて、役職もない介護士さん。でも、母はその人だけをマルセイって呼ぶの」
(先生、他の人を送ってたから帰り着くまで長くかかちゃいましたね、腰が痛くならなかったですか)
そう言いながら、自分の手を手刀のようにして、腰のあたりをトントンって叩いてくれるのよ。
(ああ、マルセイ、気持ちいい。いつも気がけてくれてありがとう。あなたがこんなに優しい子だったって、もっと前に気づいてあげれればよかった。ごめんね。気づいてあげられなくて)
(でも、今はすごく褒めてもらってるから僕は嬉しいですよ。先生、また明日!)
真秀は言った。
正直、わたしは母が認知症って診断されたときにちょっとほっとしたの。
母の中には忘れられない後悔が山ほど、動かせないゴミ屋敷のゴミのように積まれていたから。
これを少しずつ忘れていけたら、母はどんなに楽だろうと思っていたの。
もちろん、わたしも頑固だったのは認める。
でも、母が後悔ばかりを胸に抱いたまま亡くなってしまうことを想像するだけと気が狂いそうだった。
だから。ああ。お願い、もっともっと忘れてくれますように。もっとおだやかにいろんなことを忘れてくれますように、ってそればっかりわたしは考えるようになった。
認知症はわたしには「神様が母のために用意してくれた贈り物」のように見えたの。
不謹慎かしらw
最初は「年を取った人ばかりのところはいや」と言ってた母は、先生と呼ばれるうちに自分のアイデンティティを取り戻していくように見えた。
とくにあの若い介護士は、母と同時期に入ったらしくて、さながら転校生のように目をかけたっていつか話してくれた。
あの母がよ!
わたしに「転校生のようでねえ」「気になってねえ」って話してくれるの。
わたしが高校生の頃を思い出した。
学校での同級生の話をたくさん母としていた頃を。ほんとうに、母は少しだけどあの頃の母に戻ったように見えるの。
いいときの思い出だけを見続けていられて、そして、今のおだやかな毎日を少しでも長く続けてほしいとわたしは思っている。
「いいね」
佐渡くんが言った。
「いいと思うよ」
それから佐渡くんが続けた。
「ねえ、僕たちも天神山に行かない? ひさしぶりに行ってみたいんだ。マルユウ、車で僕を連れてってよ」
「わたしも連れてって!」
画面の中からそう叫んだのは本田だった。
「スマホでわたしを天神山にのぼらせて! 父の思い出の道をわたしもみてみたいの!」
本田の父は天神山の山道で亡くなっている。大丈夫なのか?
「大丈夫?大丈夫なら、僕のスマホで、天神山を見せてあげるよ、ドライブのあいだ」
「ええ! 父の愛した風景よ。すごいわ。スマホでついていけるなんて、思いもしなかった!すごい幸せ!」
「いいわね!」
真秀が言った。
「みんなで天神山にのぼりましょう!本田さんも一緒に、みんな一緒に」
マルユウはみんなの会話を聞きながら、車のキーをポケットから出し、一足先にエンジンをかけに下に降りた。
佐渡くんはZoomをいったん消して、本田をスマホで外に連れ出した。
今になってようやくそう思う。
みんなが誰かに愛されている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

