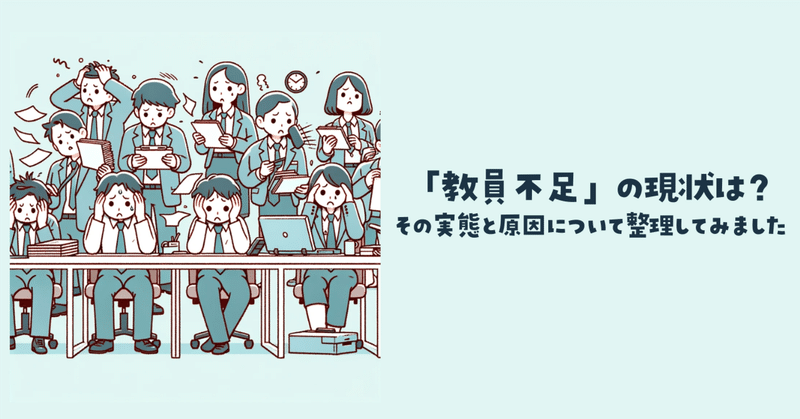
「教員不足」の現状は?その実態と原因について整理してみました
本日のテーマは、教員不足。
これまであまり把握できていなかった話題で、世間的に最近よく話題になっていることもあり多少なりとも対応は進んでいるのかなと思っていました。しかし、調べてみると現状はなかなか厳しいということが分かりまして、その現状や背景について今回は書いてみます。
※ 「教師」と「教員」という表記について、学校の先生という意味では「教員」らしいので基本的にこっちに揃えます。文書の名称や文中に「教師」とあるものはそのままにしてます。
「教員不足」の現状は?
そもそも、「教員不足」とは?
まずは、教員不足の実態について。この状況については文部科学省が2年前に「『教師不足』に関する実態調査」というド直球な調査を行っており、その結果が公表されています。

そこでの教師不足の定義はこちら。
臨時的任用教員等の講師の確保ができず、実際に学校に配置されている教師の数が、各都道府県・指定都市等の教育委員会において学校に配置することとしている教師の数(配当数)を満たしておらず欠員が生じる状態を指す。
本来配置すべき教員の数を満たすことができていない、ということです。
どれくらい足りていない?
次に、どの程度足りていないのかという点。この調査の結果で言うと、それぞれの学校種別で足りてない数は下記のとおり。
小・中学校 :2,086人(全体の0.32%)
高等学校 : 217人(全体の0.32%)
特別支援学校: 255人(全体の0.32%)
なんとなくパーセントで示されると小さいようにも見えますが、全国で本来配置するべき教員の数が2,600人も足りてないというのは衝撃的です。
より最近の数字だと、教職員組合による調査によれば2023年10月時点で全国の公立の小中学校や高校で3000人余りの不足が出ているという報道もあります。
どのように対処してる?
足りないのは分かったとして、当然に学級や教科を担当する教員がいないと学校の運営が成り立たないことからその場にいる人たちで何とか回すしかありません。
この結果として、本来担任ではない職務の教員が学級担任を代替するというケースが発生しています。その内訳として示されている数字はこちら。
指導体制の充実のために配置を予定していた教員(少人数指導のために配置された教員など):143件
主幹教諭・指導教諭・教務主任:205件
生徒指導の充実のため配置された教師:37件
管理職:53件
本来は少人数指導などで多めに配置しようとしていた人に担任を依頼するということが生じているということです。数は多くないですが校長/副校長のような「管理職」も現場に出ざるを得ないという状況もあるようです。
少人数指導の要員の場合には当初の想定であった少人数指導ができなくなってしまうでしょうし、管理職であれば管理職としての仕事がどうしても手薄にならざるを得ません。このように、苦しい状態だけど何とか回っているという状態であって、早急に改善が求められているのです。
「教員不足」はなぜ起こる?
それでは次に、この「教員不足」はなぜ起こってるのでしょうか。足りないのであれば増やせばええやん!と思ってしまいますが、この事情はなかなかに複雑です。わたし自身、全てを理解しきれているとは思いませんが、大まかな部分についてのわたしの理解について整理してみます。
まず、上記の文科省の調査結果において現在生じている「教員不足」の直接的な原因として挙げられているのは2点。
1) 産休・育休、病休者数の増加、特別支援学級数の増加により、必要な臨時的任用教員が見込みより増加したこと
2) 講師名簿登録者数が減少していること
1点目は、必要となる教員の数の増加。育休や病休者が増えたことによって、臨時で雇わなければならないケースが増えたということ。2点目は、その臨時で雇う場合の人材プールが減っている、ということです。
なぜこのような話になるのかという点については、そもそもの教員の配置の仕組みについて理解する必要があります。以下、簡単に説明します。
教員の定数算定の基本的な考え方
まず、基本的な教員の定数に関する仕組みについて。それぞれの都道府県において、必要な教員の数というのはある程度機械的に算定されるようになっています。
細かな部分は省きますが、学校の数に対して校長や副校長が1人、児童・生徒の数に対して必要とされる教員の数(35人に対して1人など)といった計算で、これが「基礎定数」と言われる基本的な考え方。
※ 細かく言い出すとこんなコマゴマとした考え方があるのですが、まずはざっくり理解することが大事かと。

現場における必要な教員数の変動要素
この「基礎定数」はある程度機械的に算定される定数ですが、この数がそのまま実態の現場において必要とされる教員の数とイコールではありません。これまたざっくり言うと、この定数から増減するケースがそれぞれあります。
勤務できる教員が「減る」ケース
1つは、勤務できる教員が減ってしまうというケースです。たとえば基礎定数として必要な教員を100人であるとしても、実際に働くことができる教員が90人しかいないといったようなことです。その主な要因は、産育休取得者数の増加と病休者数の増加。
産育休所得者数の増加については元々あったことではあるものの、近年では若い世代の採用が増えていることから増加傾向にあります。病休者についても、原因は様々あるようですが増えています。
勤務できない期間はそれぞれの事情によって異なりますが、どちらにしても一時的に離脱してしまうという点では共通しています。そして、これらの方々がいる場合には現場での教員の数が足りなくなり、その穴埋めをしなくてはならなくなります。
必要な教員が「増える」ケース
もう1つは、必要な教員の数が増えるというケース。これは、子どもや学校の数に対して必要な教員の数がたとえば100人だったとして、実際には120人が必要になるといったようなこと。この主な要因として挙げられるのは、少人数指導の広がりと特別支援教育のニーズ増加。
少人数指導、つまり児童生徒あたりの教員数をより多く配置した指導を行おうとすると、追加で教員を増やさなければならないというのは自明でしょう。たとえば公立小学校では2021年度から順次35人学級とすることが進められており、これにより教員の数を増やさなければならない状況となっています。この他、ティームティーチングや通級指導、不登校対応など特定の教育目的のために国の判断で上乗せされるものがあります。
また、特別支援教育を必要とする児童・生徒数は増加傾向にあります。特別支援学校や特別支援学級は1学級6〜8人、あるいは1学級3人などと通常学級よりも教員の配置が多くなることから、特別支援教育のニーズが増えれば増えるほど必要な教員の数は増えることになります。
最初に書いた「基礎定数」とこれらの「加配定数」が教員の数を決める主要な要素です。

変動要素はどう埋められているのか?
このように、あらかじめ設定された定数が機械的に設定されるにしても増減する要素があります。さらに言うと、基礎定数の部分についても子どもの数に応じて算定されるものである以上、子どもの数が増減すれば定数についても年度単位で増減するということになります。
したがって、これら複数の変動要因がある中で必要な教員の数をきっちり揃えるということはメチャクチャ大変です。もちろんあらかじめたくさん教員を雇っておけばこの手の問題は起こりにくくなるのですが、国からの予算として措置されるのは基本的に必要数分だけなのでそれ以上の部分は都道府県や市区町村の持ち出し。
とすると、都道府県にとって合理的なのは「ほどほどに正規教員を雇っておいて、変動する部分は非正規で調整する」という戦略です。そして、この非正規の教員を採用するための人材プールとして主要な役割を果たしてきたのが教員採用試験の不合格者なのでした。
しかしながら、近年教員採用試験の受験者は減少の一途をたどっており、さらに採用者が増加していることもあって競争率は下がり続けています。 これをグラフ化するとこうなります。

傾向はあまりにもはっきりしていて、受験者数は2013年度を境に10年ずっと減少傾向。一方の採用者数は常に上昇。これらの結果として、一部の例外はあるにしても、競争率は大きく下がっています。
これらによって生じていることは不合格者数の減少。だいぶ雑に図示するとこのようなことです。

全体の受験者数が減って、かつ採用者数も増えたことで不合格者数の数が以前と比較して大きく減少。これらの人たちがこれまで非正規雇用の母数となっていたのですが、この数も減っています。これによって、うまくマッチングができず結果として現場での教員が不足するという事態が起こっているのです。
改めて、なぜ教員が不足する?
これらの事情を踏まえた上で、最初の方に挙げた文科省のアンケートで挙げられた2つの要因を改めて見てみましょう。
1) 産休・育休、病休者数の増加、特別支援学級数の増加により、必要な臨時的任用教員が見込みより増加したこと
2) 講師名簿登録者数が減少していること
「1」として挙げられている要因は、基本的に必要とされる人数から教員が増えるケースと減るケースがあるという件で、トータルでは必要な人数が増えることでその確保が十分が難しくなっているという話です。
「2」の「講師名簿」というのは非常勤講師などを雇うための名簿で、その主要な担い手が教員採用での不合格者であることを説明したとおりです。教員採用の競争率が減ったことで不合格者が減り、さらにこの名簿への登録者が減ったことによってマッチングがうまく行かず結果として現場に教員が不足しているということです。
最後に
今回は、「教員不足」の現状とその背景について書いてきました。簡単に言うと、教員確保の仕組みにおいては非正規の教員に過度に依存した構造があり、必要な教員数の増加や受験者数の減少といった昨今の事情によってうまく対応できなくなっているということです。
それでは、これらの現状を理解した上でどのようにこの問題を解決していくべきでしょうか。短期的には、受験者数を増やしてその結果として十分な数の非正規の教員が増えれば良いということになります。「教員のやりがいPR!」や「教員免許なしでも受験可能!」といったような動きはその一例です。
目の前の不足への対応としてこれらの対応を行わざるを得ないことについては理解します。しかしながら、これらの対策では本質的な問題解決にはなり得ないというのがわたしの考えです。非正規という立場の方々に頼った今の構造を維持し続けるのでは、その当事者の生活の面でも教育の質の確保という点でも大きく課題があります。また、この構造が維持される限り、正規の教員も含めた働き方の改善や処遇の改善といった問題も先送りにされてしまいます。
これらも踏まえて、都道府県や市区町村としてどうあるべきかという点については別の記事に書いていきます。
本件に関して、ご意見ご要望などがあればお気軽に以下からお知らせください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
