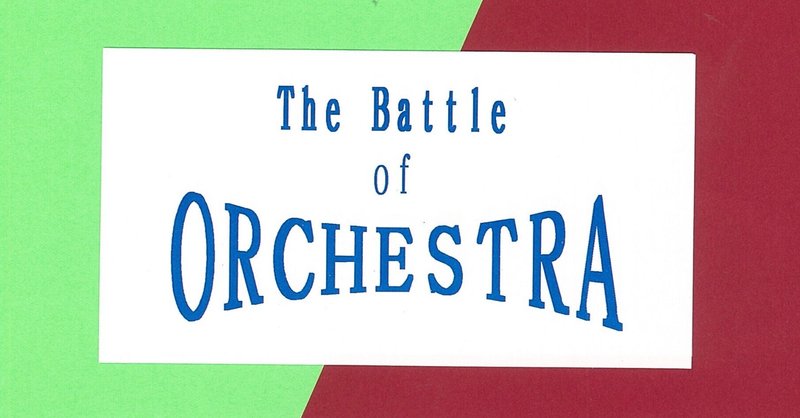
「オケバトル!」 32. 明るい夏の朝
32.明るい夏の朝
たいていの人間は就寝時、もうろうと意識を失いかける寸前に、その日に繰り返し行った作業や印象的な出来事、さりげない会話などが漠然と脳裏を駆け巡るもの。Aチームの面々もまたしかりで、多くの者がめくるめく舞踏の旋回に記憶を委ねつつ、その夜は幸せな眠りについたのだった。伝統のウィーン風舞曲のリズムも潜在意識にしっかりすり込まれながら。
有出絃人のもくろみも、あながち無駄ではなかったようだ。
ダンスでは普段使わない筋肉を駆使し、慣れない姿勢を保ち続け、身体をたっぷり動かし、よく知らないパートナーへの遠慮がちな配慮など多少の神経も使って、心身ともにくたびれきって熟睡したからか、気分も爽快、誰もが心地よい目覚めの朝を迎えゆく。
漠然とはいえ舞踏の感覚は体感できたのだし、仕上げのリハーサルは本番直前の確認程度で充分だろうということで、前夜に引き続き、翌朝も自由時間を多めに得られたAのメンバー。各々が思い思いに素敵な朝を過ごせることになる。
三時間睡眠きっかりで、いち早く飛び起きた有出絃人は、今日こそはと早朝の散歩に繰り出していた。
バトル参加者の外出は、前庭から鉄柵ゲートまでの散歩道や、木々に囲まれた敷地内であれば自由。しかし広大な領地のこと、うっかり獣道にはまって迷う危険もあるので、普段なら遠出は禁物だ。課題曲の発表やリハーサルの段取り、己の基礎練などが気にかかり、この館に到着してからは絃人も好きな散歩は控え、中庭で森林の空気をたっぷり吸い込みながらの絶大効果ストレッチで身体をほぐす程度で済ませていたのだ。
まだ低い位置から木立の中にきらめきを投げかける陽光と、館の方角関係さえ把握しておけば大丈夫、迷いはしまい。少年が抱くような冒険気分で絃人は森の奥深くに分け入っていく。
きらきらと輝きを増しゆく木漏れ日に、さわさわとそよぐ涼風、小鳥たちの静かな朝のさえずりに混じって、どこからか、珍しい鳥の鳴き声。自然が奏でる爽やかなハーモニーに身を委ねながら、思い切り深い呼吸で朝の凛と澄み切った空気を全身の細胞に取り入れる。
繰り返し鳴き続ける小鳥の歌声。そのリズムの、音程の何たる正確なことか。
いやいや、そう感じること自体がナンセンス。絃人はふっと苦笑する。こうした様々な鳥の声を、ついついカタカナやアルファベット表記、あるいは音階やリズムに転じて記憶に留めようとする人間の習性から、何とか脱皮したいものだ。それは、外国語をいったん母国語に置き換えて理解しようとする、むなしき行為に近いだろうか。音楽の世界でも、作曲家の思い描いた意図そのものを、解釈云々や理屈抜きに、純粋に、直に理解できたらいいんだけどな。
遠くからやってきたと思われる一陣の風とともに、霧雨のようなしずくが舞い降りてきて頬に当たる。この感触、この空気。絃人は懐かしいドイツの森の散歩道に思いを馳せた。
緑の木々は歌う
遙かな昔のメロディーを
ひそやかに風が鳴り
ともにさえずる小鳥たち
ハイネの詩によるシューマンの《詩人の恋》の一節が自然と浮かび、原語で口ずさむ。
まさにここは、彼=シューマンが愛してやまなかった故郷ツヴィッカウの、あの丘の上に広がる森の小路そのものではないか。
こっちに帰国してからというものの、ヨーロッパの豊かな、そして生活にしっかり溶け込んだ自然の情景にばかり名残惜しんでいたけれど、この国にだって、森のロマンはいくらでもあるんだな。ここは最高に素敵な環境ではないか。
絃人は歩みを止め、どこまでも高く生い茂る木立を仰ぎ見る。風に揺れる小枝から漏れる陽光の、何たる美しきことか。
──木漏れ日は、どれほど高価な宝石にもまさる、絶対的な美しさ──。
とりわけ早朝の澄んだ空気の中での輝きは格別に違いないんだけど……、あの娘は分かってくれなかったんだよな。
永遠の愛の証として、音楽の贈り物や薔薇の花束などではなく、形が手元に永遠に残る贈り物、つまり宝石、つまりダイヤの指輪を欲しがっていた彼女。こちとら留学生の身で、猛勉強の合間のバイト代をいくらため込んだって到底無理な話だったから、俺は彼女を早朝の森に連れ出し、小鳥の歌声や風にそよぐ木々のざわめき、清流の音、そしてダイヤモンドにもまさる木漏れ日の輝きのシャワーを浴びさせたのだ。これが僕から、というより自然界からの、最高の贈り物だよと。
自分なりの精一杯の愛を伝え、精一杯の抱擁の中、彼女も感激の涙を流していたと思い込んでいたものの、それは自分の大いなる勘違いで、実際はがっかりさせていたのだと、ずいぶん経ってから気がついた。
ウィーンでの生活関連の一切合切に、やっかいな譜面の製本まで、彼女自身のピアノの練習時間も割いて散々尽くしてくれてたし、音楽的相性は抜群だったから、ヴァイオリンとピアノでデュオを組んで生涯ともに活動を続けようと誓っていたのに。結局は自分の方が愛の重圧に耐えかねて、学業を終えるや、「ドイツでオケに入る」と言い捨てて、俺はウィーンを飛び出した。
以来、女心は謎のまま。何故、揃いも揃って女性という生き物は宝石なんぞを欲しがるのか。どんなに高価な宝石だって、光を当てなきゃ自らは輝けないってのにさ。
輝く夏の朝
僕は庭をさまよう
花たちはささやき
僕は静かに歩みを進めゆく
《詩人の恋》の、今度はピアノパートがあまりに切なくロマンティックな〈明るい夏の朝〉の一節を歌う。
胸にぐさり……。
彼女はどうしてるだろう。今でもウィーンにいるんだろうか。ピアノ教師を勤めながら、年に一度は小さなサロンでリサイタルをしているらしいと、数年後、風の便りで聞いてから、更に月日が経ってしまった。
無性にピアノが弾きたくなる。
今すぐに。AでもBでも、どっちのメンバーだってかまやしない、誰か上手いバリトンでも捕まえて、この曲を歌ってもらえたら──
ふと、遠くから歌声が。
さまよいの詩人は、歩みを止めて耳をそばだてた。
森のローレライ?
いやいや、ここが幻想の森だとしても、朝っぱらから歌声で迷える若者を虜にしたりはしないだろう。
現実世界に引き戻された絃人は森のざわめきに重なって流れてくる音楽を確認する。声じゃない。うん、楽器の音だ。弦楽器のアンサンブル。
モーツァルトか。ディベルティメントの静かなる第二楽章。どこかのアマチュア合奏団かオケの弦楽パートによる合宿中の朝練か。この辺りにはアマや学生オケが使用できる合宿所もあちこちに点在しているのだろう。
いや、これは……。
絃人は森の音を消し去って弦楽アンサンブルに集中した。
上手い。上手すぎる。昨今のアマも大したものだな。音楽がこうして一般人に浸透しゆくのはいいことだ。
それとも単なる愛好家ではないのかな。
切れ切れに聞こえる音楽の流れに意識を傾けていくうちに、いつしか敷地内を迂回して正面のゲート方向に来ていたようだ。
おや? 前方から黒ずくめの怪しい覆面男が千鳥足でやってくるではないか。
「おはようございます」
互いに挨拶を交わし、大丈夫ですか? と、絃人は年かさの男性がふらつく様子を気遣いながら顔色を伺い、そしてはっとした。
砂男コッペリウス!
「まったく何としたことか! お若いの、まあ聞いてくださいよ」
老人は憤ってぶつくさ言い始める。昨夜は仮装パーティーがありましてね、と始まり、だからほら、ご覧ください。私はこうもりに扮しましてね。中々粋な仮装でしょう? 友人に正体不明になるほどしこたま飲まされた挙げ句、泥酔状態のまま道ばたに置き去りにされてしまったか、気づいたらこんな朝方になっていて、木陰で倒れていたわけですよ。
通りかかった小学生の悪ガキどもに、「こうもり男、こうもり男」と散々はやし立てられ、観光客までが何だ何だと集まってきて、お巡りさんに保護されて、お説教を食らった挙げ句に、大恥をかきながら帰ってきたわけなんですよ。
──これって、《こうもり》の話だよね──。
どうせ大ぼらなんだろな、と訝しげに聞き流していた絃人は、老人の語るエピソードが、ヨハン・シュトラウスの喜歌劇《こうもり》で、いたずら者の友人に復讐を誓うファルケ博士による前口上そのものだと気づく。
第一、夏の真っ盛りとはいえ、ここは避暑地の軽井沢。こんなご老体を戸外に放り出すなんて、どんな悪友だってしないだろうし、本人、千鳥足を装ってるだけで二日酔いの気配すら皆無。
注意深く推理を働かせながらも、絃人はそれでも面白いので、老博士に調子を合わせてみる。楽器室での失敗の二の舞はゴメンなのだ。
「すると、あなたは他ならぬファルケ博士なのですね?」
「まさしく」と老人は丁寧にお辞儀をした後、マントに細工を施してあるこうもりめいた羽を翻して、さあーっと飛び去って──実際は走り去って──行った。
老人とは到底思いがたいあまりの素早さにあっけにとられて、絃人はこうもり博士を見送った。
──次なる課題曲は、《こうもり》か──。
また誰か歌い手が入るのか? あのオランピア嬢が再び華麗なソプラノを響かせるか? それとも序曲?
ウィーン節がふんだんに盛り込まれた名曲の、華やかな出だしの全合奏が絃人の心に鳴り渡る。絃人は確信した。そうだ、きっと序曲だ。
夜中にダンス教室まで開いて苦心して仕上げつつある〈青きドナウ〉という課題は、次の《こうもり》序曲のための、大切な予習だったか。
この曲ばかりは自分が振らないと! 絃人は己に言い聞かせた。誰が何と言おうと、わがままの横暴と非難されようと、《こうもり》序曲は、何が何でも振らせてもらうぞ。
深夜の舞踏会が決行された事実に、またもやBチームは「してやられた!」と悔しがり、後れを取り戻すべく──あるいはただ敵に対抗する目的で──、早朝特訓への招集がかけられた。
「腕もヴァイオリンも、すっかり良くなったので、指揮は降りて弾かせてもらいますね」という浜野亮の要望は、むろん却下。昨夕に引き続き指揮者の位置に立たされる。
個人個人の音出しもままならない状態で始めたって、とりわけ管楽器は楽器が温まってないだろうし、まあ、様子見で通してみようかと始めてみる。出だしのホルンのソロは少々情けなかったが、意外や軽やかなノリはほどよい加減に落ち着いて、中々いい感じであった。
しかし延々リハを続けたからって、完成度がアップするとは思えない。未熟な自分のリードでは、逆に妙ちくりんな方向に行ってしまいかねないのだ。
「ねえ、皆さん? Aチームの夜中のダンス以上のことが僕たちに何かできるとしたら、どんなことがあるでしょうね?」
とのマエストロの問いかけに、
「歌うしかないんじゃないすかね」
といった声が後方から上がる。
「それって、弦のメンバーがってことでしょう? 無理って言ったじゃないですか」
「気軽に蒸し返さないでくださいよ」
と、一斉反発の弦の面々。
「いや、一理あるかも」
意外なマエストロ浜野の言葉に、
「あ~、自分は指揮だからって、仲間の弦を裏切るんですかあ? マエストロったら」
弦楽器群から恨みがましい視線の集中砲火。
「そうじゃなくて」
慌てて訂正する浜野亮。
「本番で実際に歌わなくたっていいんです。ただ、今、この場で全員で歌ってみるだけでも充分に価値はある。楽曲本来のイメージに触れるってだけでも、学ぶべきものはあると思うんです」
そうか。では、やってみますかね。と、納得する一同。
「歌詞は? 日本語で? それとも原語のドイツ語?」
「まずは訳詞で。それから原語もいってみましょう」
「ライブラリーで歌詞を調達してきます」
コントラバスの青年がさっと出て行く。己が若く下っ端と意識してか、生来の気の利く性質ゆえんか、彼はいつもマメに雑用をこなしてくれ、誰もいない状況においても黙々と後片付けなどをしているのだった。
「いっそのこと楽器を置いて、皆で裏手の散歩道に繰り出すってのはどうでしょうね?」
との意見も出され、自然の中で歌うって、最高に素敵かも。よっしぁ行こうぜー! と、一行は仲良く肩を並べて、昨夜の舞踏会場にもなったメインエントランスを陽気に歌いながら突っ切り、コンバスの彼が入手してきた歌詞カードを手に、森の散策へと繰り出していった。
日焼け止めを塗っていないと慌てる女性らもいたが、遅れをとろうものなら、ともすれば脱落候補一直線なので、覚悟を決めて仲間に付き従う。撮影スタッフも屋外仕様で、そそくさと後を追いかける。
遙かにはてなく
ドナウの水はゆく
麗しい藍色の
ドナウの水は常に流れる
49名のメンバーが輪になって集えそうな、少し開けた心地よさそうな陽だまりを発見。朝日とお友達になるべく、多くは何となく佇むも、中には草地に座り込んだり、大木の木陰で陽射しをそっと避けるなど、思い思いに落ち着いて、皆で声をそろえてみる。
こうした場では、誰がどのパートを歌うかなんて、決まり事などナンセンス。大半の者は歌詞を見ながら気持ちよく主旋律を歌い、ヴィオラ族辺りは三度下を上手にハモり、フルートの女性は歌詞ではなく、ら~らら~♪と美しい小鳥のオブリガートを乗せ、低い声で粋な後打ちに徹するのはコントラバスの男性トリオ。
スマートな中年男性が、うやうやしいお辞儀とともに隣の女性に腕を差し出し、ダンスにお誘い。彼女はおっかなびっくり戸惑いつつも、男性の巧みなエスコートに楽しそうに身を任せていく。お騒がせオーボエの倉本香苗とヴァイオリン会津夕子も手を取り合って、歌いながらのデタラメダンスに大はしゃぎ。直立不動だった者も自然に身体を乗せたりと、誰かが拍子をとるでもなく、各々が自由に〈青きドナウ〉を楽しみつつ、全員の心はひとつとなりゆくのだった。
我ら今歌う
青きドナウを讃えて
我ら今歌う
とこしえに美しく青き
ドナウの歌を
第五円舞曲のラストまでを高らかに歌い上げ、さらにドイツ語の原詩にも触れてみる。長年音楽に携わってきた専門家の集まりだけあって、原語でも結構すんなりいけるではないか。気分も更に盛り上がるドイツ語版による大合唱で、心から楽しみながら帰路につく。
「もったいないな、これをお披露目できないなんて」
誰かが惜しそうに言った。
「冗談でなく、本当に歌ってはどうだろうか」
「一部始終、撮影はしてもらえたみたいだから、よしとしましょうよ」
撮影隊に、念をおしておく。
「真夜中の怪しげなダンスも結構ですが、健康的な我らの合唱シーンも、どこかに織り交ぜて流して頂けるとありがたいんですがねえ、よろしく頼みますよ」
「この曲の理解が少しは深まったと思うし、親しみも持てた」
トランペットの上之忠司が言う。
「何よりこの素晴らしい自然の中、みんなでひとつになって声を合わせられたなんて、最高の体験じゃないか!」
33.「彼女がつれない、そのワケは」に続く...
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
