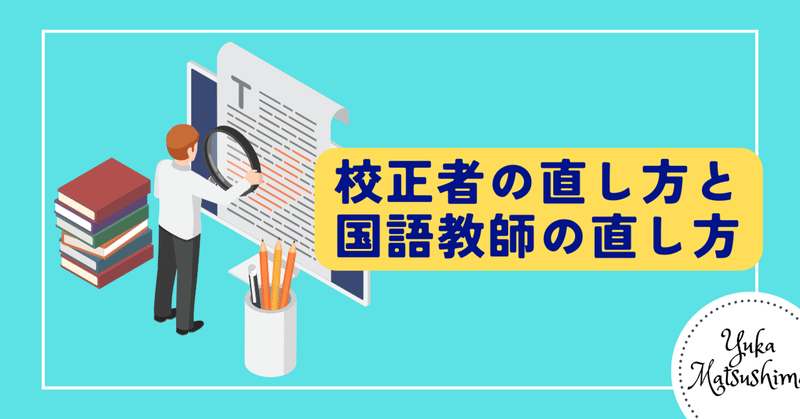
校正者の直し方と、国語教師の直し方
私は、文章指導の仕事をしているが、自分の文章を校正される側の仕事もしている。ここで「え?国語の先生が書いた文章も直されるの?」と思う人がいるかもしれないけれど、たとえ私が書いた文章でも、合っているか合っていないかではなく、仕事の内容によっては、編集方向性の違いから、容赦ない赤ペンが入ることもあるのだ。それを黙って受け入れて直す仕事もあれば、話し合いをもって、メールで何往復かやりとりがあって、決定する仕事もある。特に厳しいのが、出版物となる場合だ。
私がインタビューを受けて、その記事を別のライターさんが書いて、私が校正してという流れの仕事も多い。
その時、出版社の校正は、ルールにのっとって校正する。例えばこの文
日本の食料自給率は、先進国の中でとても低いです。
を
日本の食料自給率は、先進国の中で最も低いです。
としたい時、校正の人はこう直す。
日本の食料自給率は、先進国の中でとて 最 も低いです。
実際には赤ペンをくいっと引く独自ルールがあるけど、ま、伝えたいことは、この書き方で分かってもらえるかな。「とても」と「最も」のうち「も」は共通なので消さない、つまり、生きているのでそのままってイメージ。
国語教師の直し方は違う。
日本の食料自給率は、先進国の中で とても 最も 低いです。
「とても」を「最も」に直したんだよーということ、この二つの違い、しっかり分かってほしいよーということを伝えたい感じ。
私は校正の人が赤を入れた物を直す作業をすることもあるんだけど、切り取った感じのある修正だと「ん?何を何に直したのだ?」と思うこともある。
この文章中、この字とこの字は入れ替え後の言葉にもあるので、残す!みたいなルールは分かるんだけど、それだと、相手は学習できないんだよね。言われたとおりに直してみて、やっと分かるというか。
もちろん、校正はそういう緻密な作業の結果に目的を叶えるものであるから、その世界ではその方式が間違いがなくていい。文字数もカウントしなくちゃいけないしね。つまり、言葉を変えたことにより、何文字増えて、何文字減ったのかっていうことも分からないと、ページが作れないから。
ただ、文章指導の場合は、相手が学ぶことが第一目的だから、理由も添えて、何と言う言葉が何に変わったのか、ということを伝える。それが相手にとって学習になるように。
そんな私も校正する時に使用しているバイブル
ある編集者さんに紹介してもらった本です。webライターさんにもお勧めします。値段以上の価値あり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
