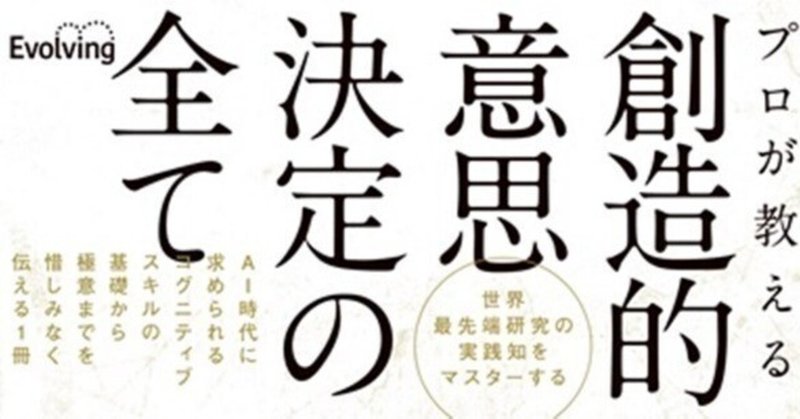
CREATIVE DECISION MAKING 意思決定の地図とコンパス まえがき公開
本書の初稿を読み返していた頃、たまたま旧知の人物がメディアの取材に答えている様子を目にした。
彼は人生の激しい荒波に流されて現在に至っている。今も次から次へと目の前に問題が現れ、それに対処しているうちに生きていると言う。こんなふうに生きてやろう、あんなことをしてやろう、などと考えて実行する余裕もない怒涛の展開で、嵐の中を流れに沿って生きてきたので、自分で選択して現在に至ったという意識を持てない、これからも「なるようにしかならない」と思っている。
私はそれを聞いて「なるほど、これだ」と思った。
彼ほど劇的な半生を送っていない人でも「流されて生きている」人は多い。それをよしとする人もいれば、我ながら主体性がないと自嘲する人もいる。それどころか、人生の中で自分に決められることなどほとんどない、と自信たっぷりに断言する人すらいる。
本書はそういう生き方にはっきりと異を唱える。
実際のところ、人生を有意義に生きていくために私たちができることは無限にある。人生の荒波に流されて生きていくしかないというのは無知ゆえの敗北にすぎない。
世間に蔓延するこうした考え方は、自由な選択や意思決定といった概念に対する根本的な誤解から生まれている。意識的で大きな決断だけをもって自分の選択や意思決定だと思い込んでいるのである。
現実の人生は絶え間ない小さな決断と行動によって成り立っている。そのほとんどは無意識だ。朝目覚めて、まず何をするか。起きてすぐに何をするか。その1日をどう過ごすか。いつ食事するか。何を飲み、何を食べるか。どこへ行って何をするか。誰と会い、何を話し、どう別れるか。1日をどう終えるか。いつ寝るのか。どう眠るのか。起きている間中、私たちはほとんど無自覚に何かを決め、行動し、その結果を引き受けている。夜に眠って見る夢さえもが日中の思考と言動によって左右されている。
その絶え間ない小さな決断と行動の積み重ねによって私たちの日常が左右され、些細に思える習慣によって私たちの小さな世界が形成されていく。
自分には世界を変えることなどできない、世界によって自分が変えられるだけだ、と無力感を訴える人たちがいるが、それは一面の真実でしかない。大きな決断や意識的な意思決定のことだけを考えているために生じた誤解なのだ。
このことを私は大きく3つの次元で学んできた。パーソナルな次元、アカデミックな次元、そしてプロフェッショナルな次元である。
パーソナルな次元とは私自身の人生である。子どもの頃に見た夢、若い頃に描いたビジョン、キャリアの節目で立てた目標などが、次々と現実のものになっている。今から20年前、30代の頃に半生を振り返ってこう思ったことを思い出す。「人生は思うようにならない。しかし思ったようになっていく」と。日々の暮らしの中で考えることは思うように制御できない。次から次へと問題が現れてそれに翻弄される日もある。しかし5年、10年、20年という長いスパンで見ると、自分自身の価値観や志に沿って物事が推移していくことが多い。それは劇的な英断や大胆な言動によるよりも、日々の小さな決断と行動によってそうなっていくのだ。
詳しくは本文(特に第10章)に譲るが、自分で決められることと自分では決められないことを見極め、自分で決められることを一つひとつ決めて実行していくことが大切だ。私たちは波や風を決めることはできない。しかし自分がどの波に乗り、どの風に流されるのかを選ぶことはできる。常にそれができなくても、選ぶチャンスは無数に訪れる。クリエイティブな意思決定を行う知力や体力を日々の習慣の中に織り込んでいくことによって、私たちは地球を動かすのではなく、動いている地球の上で自由に生きることが可能になるのだ。
アカデミックな次元とは、先人たちの研究成果である。歳のときに学び始め、その後も長い歳月をかけて身につけてきた教育ディベートの方法をはじめとして、哲学・芸術・科学の発見や伝統から私が学んでいることは計り知れない。学問は書物や論文の中に存在するのではなく、生きた人間の日々の実践の中から生まれていく。大学や大学院で学ぶ学問だけでなく、さまざまな分野を横断して研究する学際的な研究者や学者たちの洞察から学ぶことが多い。
学問とかアカデミックなどというと「役に立たないもの」という印象を持つ人が多い。たしかに象牙の塔の中で専門分化された特殊な基礎研究は、それだけを持ってきても私たちの手に余る。しかし本来の学問とは人間の実生活と無関係の抽象論ではない。少なくとも意思決定に関する理論は、現実の意思決定の役に立たないなら無価値と言われても仕方ないだろう。
本書にも登場するナシーム・ニコラス・タレブが、実際の役に立たない「意思決定理論」を揶揄している。アメリカの名門大学で意思決定理論を教える教授が、いざ自分自身の転職を考えるときに「あなた自身の理論を使ったらどうですか」と言われて「冗談じゃない、これは真剣な話なのだ」と言い返したという。つまり彼の教えている理論は実際の真剣な意思決定の役には立たないというのである。
私がアカデミックな理論を学ぶときは必ず実地に応用し、実践的な効果があるのかを確かめている。もちろん現実の世界と学校の教室は違う。教科書の内容を料理のレシピのように使うことはできない。理論とはレシピではなく、物の見方や考え方である。自分自身で噛み砕いて身につけなくてはならない。本書にもいくつかの理論が登場するが、それを右から左へと当てはめようとするのではなく、読者が自分の頭で考え、自分の心に放り込み、自分の身体で実行してみなくてはならない。それによって本物の知恵になり、血や肉になり、使える力になっていくだろう。
最後にプロフェッショナルな次元である。本書で詳述した内容は全て例外なく私自身が自分の本業で利用し、活用し、成果をあげている方法である。エグゼクティブコーチング、経営コンサルティング、マネジメント教育、組織変革などが私の専門分野であり、その体験の一端は第8章を中心に紹介している。
ビジネスの世界でクリエイティブな意思決定はほとんど異端と思えるほど珍しい。代わりに流布しているのは問題解決や問題発見の技法だ。
これも詳しくは本文に譲るが、問題解決と価値創造は別の方法である。本来ビジネスとは価値を創造する営みであり、どんなに問題を解決しても価値の創造に至る保証はない。いつのまにか主客転倒しているのだ。
もし読者の中に今まで読書やトレーニングによって「問題解決手法」「課題解決技術」などを学んできた人たちがいたなら、いったん過去の学習体験を棚上げし、クリエイティブな意思決定を新しいアプローチとして学んだほうがいい。「いかに価値を創造するか」がクリエイティブな意思決定の眼目である。問題解決は必要に応じて価値創造プロセスの中に位置づけなくてはならない。
本書は私自身が個人的に学び、学問的に習得し、職業的に応用してきた知恵の結晶と言える。その中には古今東西の賢人たちが推奨して実践してきた良識も含まれるが、現代のビジネス界における一般常識に真っ向から反する稀有な考え方も含まれている。現代の常識にすっかり染まっている読者の中には自分の過去の体験や見識を否定されるような不快感を覚える人がいたとしても不思議ではない。
その意味で本書は劇薬かもしれない。第1章から順に読み進めるとわかりやすいデザインになっているが、もし気になる章があったら先に拾い読みしても構わない。読み終わったら本棚に置いて、必要な章を自分のタイミングで再読するのもいいだろう。
どんな読み方をしても、もしクリエイティブな意思決定が自分の役に立つと思ったら、ぜひ本書の方法を身につけ、人生やビジネス、キャリアや人間関係を創造するために使ってほしい。
2021年8月3日
東京都品川区にて
田村 洋一
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
