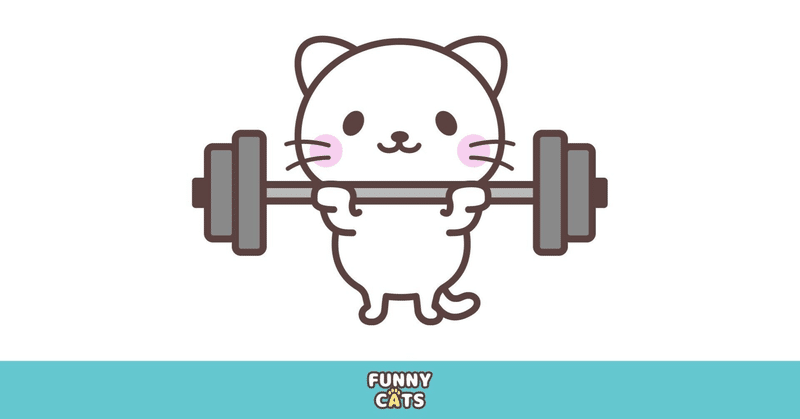
CATなら、軽い負荷でもベンチプレスが強くなる!~スピードを制する者はパワーを制す~
強さってなんだろう
筋力トレーニングをする人は、みな「強さ」を求めて日々努力していることでしょう。
でも、力の「強さ」を表す指標が2つあることはご存じでしょうか。
それは、
ストレングス
パワー
の2つです。
ストレングス(Strength)とは、最大筋力のことです。
単純にいうと、1RMの重量だと思ってください。
たとえば、あなたはベンチプレスで何㎏挙げられるでしょうか。
その最大重量が、ベンチプレスにおけるストレングス=強さです。
おそらく、通常の筋力トレーニングではこの指標の向上を目指していることが多いでしょう。
ボディメイクや筋肥大を重視する人にとっても、ストレングスは重要です。同じセット数と回数なら、重い重量の方が刺激が強くなりますから。
そして、パワー(Power)というのはストレングスとは異なる概念です。
これは、力の立ち上がりの早さのことです。
簡単に言うと、重さ×速さのかけ算で表されます。
同じ重さを挙上したとしても、その速度が違うなら、発揮されたパワーは異なるのです。
たとえば、同じ50㎏のバーベルでも、1秒で挙上するのと0.5秒で挙上するのでは、パワーは2倍違うことになります。
0.5秒の方が、2倍強いです。
パワーがかけ算で決まるということは、どちらか一方が大きくても、もう一方が小さいと、その積はさほど大きくなりません。
たとえば、
10×1 は10ですが、
6×2 だと12になりますね。
左側の数字を「重さ」、右側の数字を「速さ」だと思ってください。
よりたくさんのパワーを発揮するには、このかけ算の積が最大になるよう、最適なバランスをとる必要があります。
人間の筋力は、1RM近辺の重量だと、その挙上速度はかなりゆっくりになります。
上のたとえでいうと、「10×1」に近くなります。
ということは、高重量を扱うトレーニングは、パワー発揮という観点ではあまり効率が良くありません。
では、どのぐらいの負荷がパワーには最適なのか?
だいたい最大筋力の30%の負荷で最大パワーが発揮されることが、これまでの研究で分かっています。
さあ、パワーを鍛えよう
さてこのパワーですが、日本の一般的なトレーニング環境では割と見過ごされがちです。
スクワットやベンチプレスを行っているアスリートは多いでしょうが、パワー獲得のために重要とされるクリーンやスナッチといった種目となると、行っているアスリートはかなり限られるのではないでしょうか。
まあ、設備の問題もありますが。
一般的なジムでは、バーベルを振り回すとスタッフに注意されますので(笑)
バンパープレートにウェイトリフティング用のバーベル、プラットフォームを備えるようなジムは、日本ではかなりコアでしょう。
しかし、ほとんどの競技アスリートにとって、重要なのはストレングスよりもパワーです。
疾走、跳躍、投擲……スポーツに求められるどの動作においても、カギとなるのはパワーです。
逆に、純粋なストレングスが求められる場面というのは、思いつく例を挙げればラグビーのスクラムなど、かなり限定的です。
ところでこのパワー、必ずしもクリーンやスナッチを行わなくても鍛えることができるのを、ご存じでしょうか。
たとえばベンチプレスやスクワットといった種目でも、やり方によっては可能なのです。
しかも、パワーを向上させつつ、同時にストレングスも向上させられる方法があるとしたらどうでしょうか。
なぜそんなことが可能なのかというと、どうやらストレングスとパワーには相関する、もしくは相補的な部分があるらしいのです。
ざっくりいうと、ストレングスが向上すればパワーも上がるし、パワーが上がるとストレングスも上がる、という関係があるのです。
ただ、さすがにダイレクトに比例する、とまではいきません。
お互いの影響も限定的なので、「重なる部分もある」ぐらいに考えた方が良いでしょう。
とはいえ、このパワーという観点からのアプローチは、長年ストレングスを鍛えているけど、向上に行き詰まりを感じているようなトレーニーには特に有効かも知れません。
CATという方法
さて、それでは具体的なトレーニング方法の紹介です。
タイトルにもある通り、CATという手法です。
これはCompensatory Acceleration Trainingの略称です。
直訳すると「代償加速トレーニング」です。
(すいません、「猫」ではありません)
Dynamic Effort、ダイナミックエフォートとも呼ばれます。
どのような方法かというと「挙上重量ではなく、仕事率に注目する」という発想のトレーニングです。
仕事率というのは物理の用語で、質量×移動距離÷時間です。
言いかえると、ストレングスではなくパワーに注目するのです。
先ほどと同じような例を想定して、もう少し詳しく説明することにしましょう。
ベンチプレスで、100㎏を1秒かけて1回挙上したとします。
この時、挙上距離を0.5mと仮定すると、仕事量は
1000N×0.5m=500J
となります。
(N=ニュートン、m=メートル、J=ジュール。1㎏≒10Nというざっくりした概算です)
それを1秒で行ったので、仕事率は
500J÷1s=500W
(s=秒、W=ワット)
です。
同じくベンチプレスで、こんどは50㎏を0.5秒かけて1回挙上したとします。
同様に計算すると、
500N×0.5m=250J
となり、
0.5秒で行ったので
250J÷0.5s=500W
となります。
お分かりでしょうか。
「仕事率」という観点でいうと、1秒で挙げる100㎏と、0.5秒で挙げる50㎏は同等なのです。
つまり、パワーという指標においては、この二つは同じ負荷とみなすことができます。
トレーニングの感覚で表現すると「ゆっくり挙げる100㎏と、すばやく挙げる50㎏は同じ」ということです。
ただし、もしこの人のMax重量が100㎏なら、そもそも意図的にゆっくり挙げることなどできません。
どんなに頑張ったとしても、その挙上はおのずとゆっくりとしたものになってしまうでしょう。
ここで問題なのは、50㎏の方です。
おそらく、ベンチプレスが100㎏挙がる人にとって、50㎏という重量はさほど重くありません。
おそらく、普段のトレーニングでも50%の負荷を用いることはまずないでしょう。
あっても、アップとしてでしょうか。
しかし、ここで発想を変えてみましょう。
50㎏という重量を、全力のスピードで挙上するのです。
そしてもしそのスピードが100㎏の時の2倍なら、仕事率はMax重量を挙げたのと同等になるのです。
もし2倍を超えるなら、それ以上です。
Max重量というのは、基本的に1回しか挙がりません。
もしかすると、その日のコンディションによっては1回も挙がらない場合もあるでしょう。
でも、50㎏を素早く挙げるのはどうでしょうか。
どう考えても、たった1回しか挙がらないということはないでしょう。
最低でも5回ぐらいは挙がるはずです。
ということで、「ある程度の軽い重量を、全力ですばやく挙上する」という手法を用いると、効率よくパワー発揮を行うことができるのです。
これが、代償加速トレーニングの基本となる方針です。
「加速によって負荷を代償する(補う)」のです。
実際の運用方法
さて、ではこのCATをどうやって行うのが良いか。
ここで紹介したいのは、Westside Barbellによる手法です。
ウエストサイド・バーベルというのは、ルイ・シモンズというアメリカの方が創始したジムです。
パワーリフティング競技で数々の世界記録保持者を輩出している伝説的なジムで、入会するにはルイの許可が必要なんだとか。
世界の頂点を獲るためのジムなので、会員はみな世界トップクラスのリフターだそうです。
とことんハードコアなジムですね。
採算は取れるんでしょうか。
簡単にいうと、この方はロシアや東欧など、旧共産圏のウェイトリフティング競技で行われていたトレーニング手法を、アメリカのパワーリフティング界に採り入れた事で有名になりました。
実は、トレーニング科学に関して言うと、かつての旧共産圏は自由主義圏よりもかなり先を行っていた部分があるんですね……
まあ、同時に薬物汚染などの問題もあるので、そこは割り引いて考える必要はありますが……
そのルイのメソッド(Conjugate Methodというそうです)の中に、ダイナミックエフォートという手法があります。
このCATの原理に基づいたトレーニング法です。
具体的なプロトコルを説明しましょう。
ただし一点おことわりを。
ウエストサイドバーベルの手法は現在ではいくつか分派や亜流があるようで、ここで紹介するものが正真正銘のオリジナルだ、という保証はありません。
あくまでも、サンプルとしてご理解ください。
ちなみにルイ・シモンズ氏は、2022年に亡くなられた模様。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
