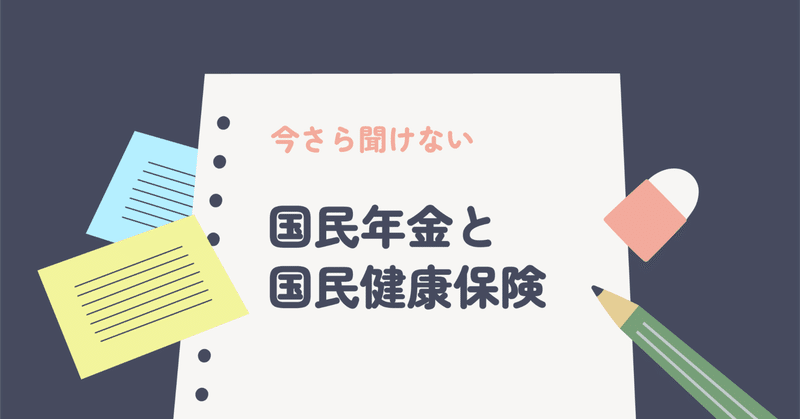
会社を辞めてフリーランスになる人へ 1 - 今さら聞けない 大人のための国民健康保険と国民年金の基礎知識 退職後の届出も忘れずに
「国民健康保険?社会保険?厚生年金?今自分のは何?」
会社員とフリーランスの違いのなかでも重要なものとして、保障の違いがある。ひとことで言うと、会社員は社会保険や厚生年金とても手厚い保障に守られている。
今回は、わかるようでわかっていないかもしれない、国民健康保険と健康保険(社会保険)、国民年金と厚生年金。それぞれの違いについて、そして会社を辞めた際の手続きについてまとめておこうと思う。目次がめっちゃ長くてどうもすみません。
国民健康保険とは?
国民健康保険は、日本に住んでいる人が病気やけがをした際に、治療費の一部を助けてくれる制度。加入していると、条件に応じた負担額で医療を受けられる。つまり、全額自分で払わなくてもよくなる。
国民健康保険の対象者
自営業者、フリーランス、無職者など
国民健康保険は基本的に「世帯」を単位として管理される。一般に、世帯の中にいるすべての人がその世帯の国民健康保険に含まれる。
ただし、世帯の中の誰かが会社員で健康保険に加入している場合、その人は国民健康保険の対象外となる。
国民健康保険の保険料
自分の収入や家族の人数、住んでいる場所によってが変わる。一般的に、毎月自分で直接市町村に支払う。当然、全額自分で払うことになる。
国民健康保険の保険者
各市町村
国民健康保険の加入手続き
自分で市町村の役場や区役所の窓口へ行き加入手続きをする必要がある。会社を辞めた場合にも、忘れずに加入手続きをしよう。
国民健康保険と健康保険(社会保険)の違い
会社員になると、国民健康保険を脱退し、健康保険(社会保険)に加入することになる。では、国民健康保険と健康保険(社会保険)はなにがどう違うのか。はっきり認識していないという人も多いことだろう。
何を隠そう自分もあまりよくわかっていなかった一人である。10年以上も会社員をやっていたというのに。
というわけで違いをまとめてみた。
健康保険の対象者
会社員
健康保険の保険料
給料の一部が保険料として差し引かれる。支払額は会社と折半となる。
健康保険の保険者
健康保険組合 - 大企業や企業グループなど
全国健康保険協会(協会けんぽ)- 中小企業や特定の健康保険組合に加入していない企業の従業員
健康保険の加入手続き
会社がやってくれるので、自分ではなにもしなくてよい。
国民健康保険と健康保険(社会保険)のサービスの違い
健康保険(社会保険)は、国民健康保険と同じく、条件に応じた負担額で医療を受けられる。
さらに、健康保険(社会保険(健康診断や予防接種などのサービスが受けられることもある。
国民年金とは?
老後や障害、死亡などのときに、基本的な生活を支えるためのお金を提供するための制度。具体的には以下のような目的がある。
年金制度の目的
老齢基礎年金 - 老後の生活を支えるため。65歳から受給開始。
障害基礎年金 - 病気やけがで障害状態になった場合の生活を支えるため。
遺族基礎年金 - 国民年金の被保険者が亡くなった場合、遺族の生活を支えるため。
国民年金の対象者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する
自営業者、フリーランス、学生、無職など
国民年金の保険料
当然だが自分で支払う。口座振替、納付書払い、クレカ払いなどが加納。
まとめて前払いで割引がある場合がある。
国民年金の保険者
日本年金機構(国)
国民年金の加入手続き
会社を辞めたら、国民年金第1号資格取得の手続きが必要になるため、自分で市町村の役場や区役所の窓口へ行き手続きをする。
※国民年金第2号被保険者である配偶者の被扶養者になる場合は、国民年金第3号被保険者となる。
詳しくはこちらをどうぞ。
参考
会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構 - https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html
国民年金制度の3つの区分
日本の国民年金制度には第1号から第3号まで3つの区分があり、それぞれ異なる対象者と特徴がある。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満で、厚生年金保険や公務員共済組合などの被保険者ではない人。基本的な年金保険であり、全ての人がこの基礎的な保障を受けることがで切る。保険料は全額自己負担。
例: 自営業者、フリーランサー、学生、パート・アルバイト(厚生年金の適用を受けない)、専業主婦(夫)など
第2号被保険者
厚生年金保険に加入している人。国民年金の基本的な保障に加え、就業実績に応じてより高い年金が受け取れる可能性がある。
例: 会社員、公務員など
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者で、20歳以上60歳未満で、自身は収入が一定額未満の人。
保険料は第2号被保険者が負担するため、第3号被保険者自身は保険料の支払いがない。将来、基礎年金を受け取る資格がある。
国民年金と厚生年金(厚生年金保険)の違い
会社員や公務員になると、社会保障の枠組みより充実した保障を提供するため、国民年金に加えて、厚生年金に加入する。
厚生年金は、国民年金(基礎年金)を土台とし上乗せされた、2階建て部分ということになる。
厚生年金の対象者
会社員や公務員
厚生年金の保険料
給与の一部が保険料として差し引かれる。支払額は会社と折半となる。
厚生年金の保険者
健康保険組合や日本年金機構
厚生年金の加入手続き
会社がやってくれるので、自分ではなにもしなくてよい。
ほかにもあるよ 日本のいろいろな年金制度
日本の年金制度にはいくつか種類があり、それぞれが特定の目的に合わせて設計されている。ここでは、主要な年金の種類をリストアップする。
国民年金(基礎年金)
厚生年金(職員共済含む)
公務員共済組合の年金
私立学校教職員共済の年金
農業協同組合中央会(JA共済)の年金
個人型確定拠出年金(iDeCo)
企業型確定拠出年金
新NISAと並んで名前を耳にすることが多いiDeCoは、加入者自ら資産運用を行うシステムという意味では投資と言えるが、税制優遇措置があるほか、老後の生活資金の確保に特化した制度であるという点で、公的年金制度の一部として機能している。
社会保険の5本柱
健康保険や厚生年金保険は、大きい意味で「社会保険」の一部である。
日本の社会保険は以下の5本柱で成り立っている。社会保険は、個人が自己責任ですべてのリスクに備えるのが難しいため、社会全体で支え合おう、という仕組みである。
健康保険
厚生年金保険
雇用保険
介護保険
労災保険
会社を辞めたら国民健康保険と国民年金の届出をしよう
さて、ここまでで健康保険や年金に関する基本的なことは整理できたのではないだろうか。というわけで、ようやく本題。最後は、会社を辞めた際に自分で行う手続きについてまとめておく。
国民健康保険加入の届出
健康保険(社会保険)を脱退し国民健康保険に加入するため、自分で届出を行う必要がある。
国民健康保険加入届出の期間
会社を辞めてから14日以内に届出を行う。
僕の場合、13日目に区役所へ行き手続きを行なった。
国民健康保険加入の届出に必要なもの
健康保険資格喪失証明書
マイナンバーカードや運転免許証(顔写真付き証明書)
国民健康保険加入の届出窓口
お住まいの市町村の国民健康保険窓口
国民年金の届出
60歳になる前に職場を退職した場合、2号から1号へ変更になるため自分で届出を行う必要がある。
国民年金の届出期間
国民健康保険加入の届出と同時に行えばよい
国民年金の届出に必要なもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバー確認書類のうちどれか1点
離職日のわかる書類(健康保険資格喪失証明書、離職票など)
運転免許証など
※年金番号がわかるものがあるとよりスムーズにいくようだ
国民年金の届出窓口
お住まいの市町村の国民年金窓口
僕が実際に届出をおこなった際の備忘録
さて、最後に、備忘録を兼ねて自分が実際に届出を行った時のことを書き残しておく。
新潟市西区に住む僕は、退職から13日後に、新潟市西区役所区民生活課 給付係へ。
持参したものは以下のとおり。
健康保険資格喪失証明書(退職した会社から発行してもらう)
マイナンバーカード
免許証(使用しなかったと記憶している)
新潟市の場合、国民年金の届出に必要なものに「離職日のわかる書類(離職票など)」とあったが、国民健康保険と一緒に「健康保険資格喪失証明書」があれば問題ないと、退職した会社から教えてもらった。
実際、離職票が手元に来るまでに、退職から14日以上かかった。(雇用保険に関するものなので、労務事務局へ作成を依頼するため少々時間がかかる、とのこと)
窓口に行き、健康保険資格喪失証明書とマイナンバーカードを係の方に見せる。15分程度で手続きが完了した。
ちなみに、途中で年金番号がわかるものを持っているかと聞かれた。持っていたらもう少しスムーズに進んだのかもしれない。もちろん、なくても問題ない。
さいごに
わかっているようであまりわかっていなかった保険の話。特に会社員の場合、保険料は給料から差し引かれるので、自分がどのくらい支払っているのか、正直ちゃんと把握していない…なんて人も少なくはないのではないだろうか。
でも大丈夫!大人になってからでも遅くはない。大事なのは、学ぼうとするその姿勢だ。学びに早い遅いなどない。学ぼうと思ったときが学ぶべきとき。そして学ぶなら、あなたの人生で一番若い時期、つまり、今だ。
というわけで以上で保険関連の話は終わりにしようと思う。
このnoteでは、引き続き、同じように中年フリーランスになった方やなりたい方に向けて、自分の経験や学んだことを発信していきたいと思う。
サポートありがとうございます。いただいたサポートは、味玉トッピングに使わせていただきます。
