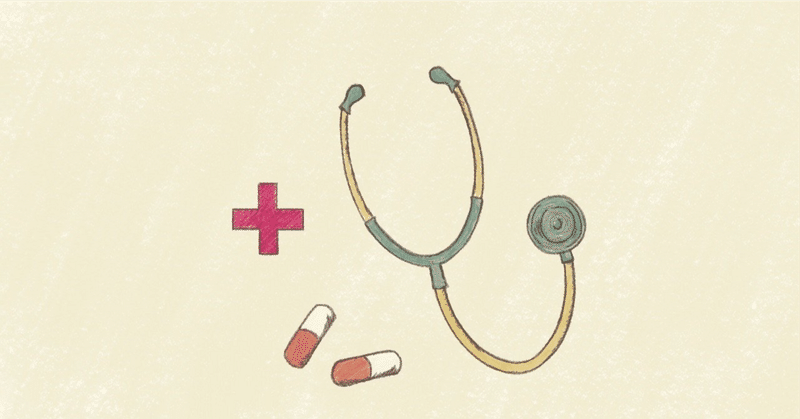
ワーママライフ# 親もツラい、子の体調不良。少しでもハッピーで過ごすために考えたこと。
先月1ヶ月は精神的に辛すぎる1ヶ月でした。
というのも、毎週、金曜〜水曜日にかけて2人の娘が高熱を出し、その看病に追われたことで精神的にすり減り、メンタルがやられてしまいました。
家族に(特に夫)かなりあたってしまったのです・・・。
発熱していた日数は月の半分(数えたら12/30日)でした。
熱がある期間は急な悪化が心配でよく眠れないし、
熱がない期間も辛い咳や鼻水で眠りが浅くなる子どもに
「水飲みたいーー!」
「咳が止まらない!!!」
と真夜中に頻繁に起こされる。
日中の看病に加え、自分の睡眠不足が積み重なっていく日々なので、
自分の体調だけは崩せない、と自分の睡眠時間をとることにも必死になり、
唯一の自分の時間だった朝の時間(朝活)も諦めモード。
すると・・・日に日に、気持ちが辛くなってきてしまいました。
もちろん、免疫力のない子供の体調不良は、強くなる過程に必要なことなので仕方がないし、親としても辛そうな我が子を全力でサポートしたいのですが、さすがに1ヶ月は辛すぎるーー!
確実にまた同じようなことがあると思うので(ちょうど1年前はもっと酷かった)、気づいたこと、少しでもラクに乗り越えるにはどうするか、考えたことを残すことにしました。
どうして辛くなってしまうのか
をまずは分析。
■仕事
・コントロール不能で結果的に調整をつけられずに休むことによる罪悪感
・休んで看病をするのがいつも父親でなく自分であることの不公平感
■子ども
・小児科の予約の取れなさと連れていくのが大変
・まずい薬を飲んでくれない
・四六時中、子どもといると次々に出てくる欲求に応え続けなければいけなくてしんどい
■自分
・自分の時間がなく、やろうと決めていたことが全くできない
・睡眠不足が続く(夜中も咳や鼻水で寝られず起きる子どもと一緒に何度も起きることになる)
以上が主な理由なのですが、
なかでも私にとって一番のストレス原因だったことは何かを考えた時、
「自分の時間が取れない」
「やりたいこと(勉強など)が終わっていない」
という状態が1ヶ月続いたこと
でした。
子どもの相手が大変なのは、わかっている。仕方がない。それも含めて、かわいい!
でもそう思えるのって、自分の時間が取れて自分が十分満たされていてこそなんですよね。
ちなみに夫との分担については、私の方が仕事の調整をしやすい状況なので「いいや」と思っていましたが、不公平感を感じている自分に気づいたので、次からはやってもらおう〜と思ってます。
余白 & Bプランを用意しておく
この1ヶ月、私がやろうと思っていたこと(読書や、勉強や、インテリアの発信など)はかなりのボリュームでした。
それは、
子どもが病気にならなかった場合を考えても
「そんなに時間あるっけ私?」
というようなパツパツの量
でした。
をれが全くできないことで、よりストレスが増幅していることに気づきました。
「万事うまくコンディションが揃えばできるけど、誰だって常に良いコンディションではいられない。そんな時のこと考えている?」
このことに気づかせてくれるための1ヶ月だったのかもしれないです。
幸い、自分個人での仕事だったり、誰かに迷惑がかかるものではなく、
勝手に自分で「あれもこれも」と思っていたことのでよかったですが、
自分のメンタルのためにも、
そして今後どんな状況でも約束した結果を出すためにも、
余白を持ったプランニングはもちろん、常にBプラン(その時間がなくなったらどうやってやる?)を作っておかなければいけない、と感じました。
調子が悪くても自分の発言と行動を一致させて、言ったことは必ずやる人
(特に人との約束など誰かが関係するものなら、なおさら!)
になるには、今のやり方では難しい、と気づかせてくれた1ヶ月でした。
1人になれる手段を用意する勇気
もう一つ大事なのが、1人になれる手段を用意しておくこと。
まずは自分が元気でないといけないことは、よくわかっているのに、
その手段を用意できていなかったと思います。
アメリカでは、
"Happy Mommy, Happy Family" という言葉があるようです。
ママが元気で初めて家族が元気!
自分の機嫌を自分で取れるように、
・1時間くらいカフェに行ったり、
・シッターさんを探しておいたり(中々マッチングせず見つけられない)、
この事前の準備自体がめんどくさいのですが、自分のために、自分で能動的に自分をラクにする手段を複数用意しておこうと決意を固めました。
ちょうど新しい月が始まりました!
気分一新して、楽しみたいです。
お読みいただきありがとうございました♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
