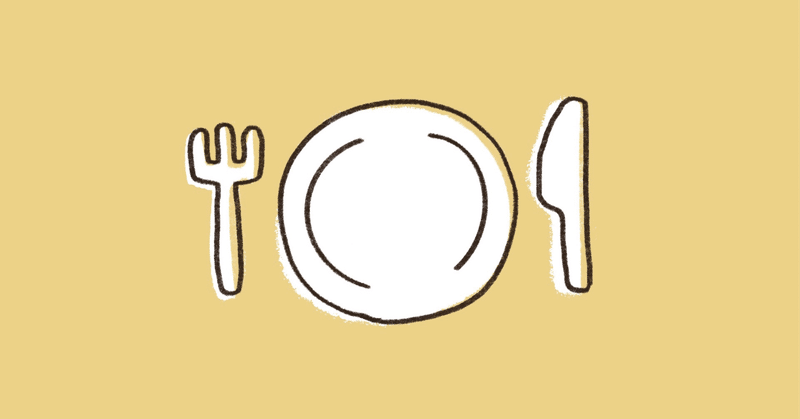
嚥下食とか、離乳食とか、特別な名前をつけるから特別になる。
1人1人が最上(さいじょう)の暮らしをすることを広げたくて、山形県最上地域にある新庄市にて、喫茶と間貸「万場町 のくらし」/スナックCandy山形の店主をしています『最上のくらし舎(もがみのくらししゃ)』よしのゆうみ です。
最上(さいじょう)の暮らしをふやしていきたい!という思いと共にモグラーという仲間たちと日々活動しております!
昼は喫茶店・夜は不定期開催のコミュニティ・スナックを開いてます。
今回は、2023年7月18日のモグラー会員向けの記事のシェアです。
今年から【山形放送・番組審議委員会】というものの委員をしております。
山形放送さんが自社制作で放送している内容に関して、いろいろ言う会(ざっくり)
今回は山形県・鶴岡市で嚥下食(えんげしょく)に関して取り組んでいる料理人の延味克士さんをおったドキュメンタリー番組を拝聴いたしました。
口福の献立~お腹と心を満たす嚥下食~
老化や病気で食べ物をうまく飲み込むことができない人のための食事〝嚥下(えんげ)食〟。安全面が優先されるため、見た目は二の次、多くは食材の原型を留めていない。でも鶴岡市の料理人、延味克士さんの手にかかると嚥下食は劇的に変わる。寿司、肉料理、天ぷら、たけのこ汁など…。嚥下食を通して、食べる幸せを見つめる。
QOL(生活の質)とは、ただ命があればよいというわけでなく、治療や療養生活を送る患者さんの肉体的、精神的、社会的、経済的、すべてを含めた生活の質を意味します。 病気による症状や治療の副作用などによって、患者さんは治療前と同じようには生活できなくなることがあります。
〝嚥下(えんげ)食というと、どんなイメージですか?想像つくかな

そんな〝嚥下(えんげ)食の常識を変えた、料理人の想いや活動をおったドキュメンターン番組。

番組中に「高齢化率世界一の日本」という表現があって、そんな日本からQOL(quality of Life)といわれるものに関して考えさせられるテーマだと感じました。
番組の途中、延味さんの食事を食べたあとのおじいちゃんが
「生きていてよかった」と涙ぐんでおっしゃっていたシーンがある。
元々、食い道楽だった、いわゆるお食事が好きな方だったそうで、食道ガンを患ってから嚥下食を選択せざる終えなくなり、ずっと辛かったんだろうなぁ。。。
「生きていてよかった」と、この言葉には、逆を返せば「もう生きている意味はない」 そんな気持ちで食事の時はつらい状態だったんだろうな、と感じました。
QOLは福祉業界とかでもよくいわれる「生活の質」みたいなところで、ただただ命があればいいということではなく、治療とか療養生活を送るうえで患者さんの肉体的なところだけでなく精神的、社会的、経済的な面も含めたすべ ての質に関して問われる問題だと思います。
「嚥下食は、特別なものではない」
「嚥下食自体は特別なものではない」と延味さんもおっしゃっていたのもすごく印象に残っています。実は私の夫が料理人で、2歳と4歳になる息子がいるのですが、離乳食の時期にイタリアンの通常メニューにある『レバーペースト』を作って与えていました。そのレシピは離乳食用とか、特別なレシピではなく、今思えば、離乳食用でも嚥下食用でもないものを、普通に自然とあげていて「離乳食」とか「嚥下食」というのは、そう肩肘を張って作るものではなくて自然あるものなんだなぁ、と思いました。
『このレシピを広めたいが、安全性において嚥下食!として普及させるにはいろいろ難しい』などの意見がでました。
安全性に関して
コロナのこともありますし、近年 "安全性"において重要視されることも多くなっているのを感じています。その安全性のあり方も思うところがあります。
私の知っている保育園でも、現在は「すりリンゴ」をおやつや給食で与えるのは、できない。と聞きました。「園児の死亡事故があったから、危険である」との理由で不可能だとのこと。未満児・歯が生えてきた頃の子どもに”固いお煎餅”を与えることも危険なのだとか。『与えられる状態がかなり少ない』とちょっと嘆いていました。安全の基準がとても高いですね!
私の母が今年の2月にガンで亡くなったのですが、そういう安全性を優先し、最後はほんとに隔離された生活を余儀なくされ、余命宣告をされるまでずっと面会もできず、安全性を理由に私の息子たち(孫)にも会えずそのまま他界してしまったので、『安全性を優先することだけがすべて』ではない、とその時にすごく強く思いました。私にはそういうQOLというか、人間の生き方を考える上で逆に問いかけられる内容だと感じました。
他の委員がおっしゃった『レシピ本』にするというアイデアはすごくいいなと思い ました。嚥下食(えんげしょく)というのはそういう専門的の方だけが作るものではないと私も思います。
家庭で高齢になってきた家族とか、食事が少し不自由になった方に対して知識として、”おばあちゃんの知恵袋”のような形で共有され、そのリスクに関しては『その人が食べたいものを食べたい状態で食べられる選択』として、”シンプルに知識として”広がるといいなと思いました。以上です。
・・・・・・・・・・・・・・
舌と目でも楽しめる嚥下食は、海外ではほとんど浸透していないそうです。調理にかかる手間と時間は、通常の倍以上。低コストも時短も度外視。日本人の性格と価値観から作られる〝Japan Quality〟かな。この方の食事を求めて海外からお金持ちが集まってきそうですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
