
中山道“風の旅”2024〜第2ステージ、第3ステージ
旅を続けます。
第1ステージまでは↓
4月30日
【第2ステージ】岩村田宿〜下諏訪宿 53km
前回もそうだったが、夢を見ることもなく目覚める。100%ノンレム睡眠なんだろう。
夜はコンビニ弁当だったのでちゃんとした朝ご飯を食べれるのが嬉しい。しっかり食べる。食べられる間は大丈夫。昨日痛めた膝は完全には戻らないが、昨夜のケアはそれなりにリカバリー効果があったのか昨日ほどは痛まない。それでも若干の痛みとか違和感はある。今日は53kmと短い(?既に距離感覚が麻痺)ので何とかなりそう。とは言え難所、和田峠越えがあるので侮れないのだ。昨夜調達したロキソニンテープを右膝に貼ってサポーターで固定して朝8時頃にスタート。

塩名田宿に入る。


保存状態は良くないが関東平野の宿場町に比べれば面影は残っている。何よりも車がほとんど走ってないのでストレスフリーなのが良い。
舗装されていても、生まれ育ちからすると、新道(国道)は車の道、旧道は人の道なのだ。


時々、分岐があり気持ちの良いトレイルを通る。舗装路よりも格段に気持ちが良い。しかし歩く人がほとんどいないので踏み跡は細い。昔はもっと人が往来していて今よりもずっと道らしい道だったのではないかと思う。

望月宿を通過してしばらくして痛恨のロスト。
往復1.2km。

道標の矢印が切れていて何気に左側へ入ってしまった。道標はありがたいんだけどどっちを指しているんだか不明瞭な道標も結構ある。そもそも思考力が低下してるので何とは無しに先へ進んでしまって後で気づくなんてことはしょっちゅう。こまめに現在地位置を確認すればいいんだけどそれはそれでタイムロスになるので限度がある。ロストを気にして地図やスマホばっかり見てるのも何やってんだかって感じ。なので大ロストを旅の思い出の一つだと受け入れるのがイチバン。
笠取峠へ向かって何とか走れるレベルの緩やかだけど単調な登りがダラダラと続く。一番しんどいやつかもしれない。途中、笠取峠のマツ並木を通る。木は陽や風を遮って旅人を守ってくれる。もはや旅人としてここを通る人は僅かだけどいつまでもこの並木が残ることを願う。



ところどころトレイルへの分岐があるので入る。


やっぱりトレイルは気持ちがいい。
しかし調子こいて走ってると道が消えてしまう。

左にロードに降りれそうたもんだが崖になっていて降りられない。諦めて戻る。

左から来てUターンして右側へ行くのが正解。親切なことに真っ直ぐ進むなと言わんばかりに枝が寝かせてあるのにわざわざ飛び越えて直進してしまったようだ。こういったことはトレランや普通に登山していても経験のあること。焦って無理して崖から飛び降りないことが大事なのだ。“戻る”という判断に迷いは付きものだから。いついかなる時にも安全第一で。
笠取峠を越えると次は和田峠へ向かって登り基調が続く。

和田峠はこの谷筋の奥にあるのだろう。細長く続く山の斜面が、明るい緑の絨毯のようで見惚れる。
和田峠の前にある和田宿が近づくと家の形をしたバス停が次々と現れて楽しい。





水が豊富で道の脇にいくつもの水場がある。昔の旅人にとっては貴重な水だったろう。


飲むと甘い。ペットボトルのミネラルウォーターとは別物だ。
和田宿に入る。


ここで末房さんの移動エイド

食べなくても分かるこのクオリティー!
にんにくが効いてスパイシー。
絶品でした。

和田峠入口に到着。
もう17時半。明るい内に反対側へ降りたかったけど、峠に辿り着く頃には真っ暗闇だろう。でも半分くらいは景色を楽しめるので良しとしよう。



まるでこの道は生きてるみたいだ。アスファルトで固めた道とは異次元だな。
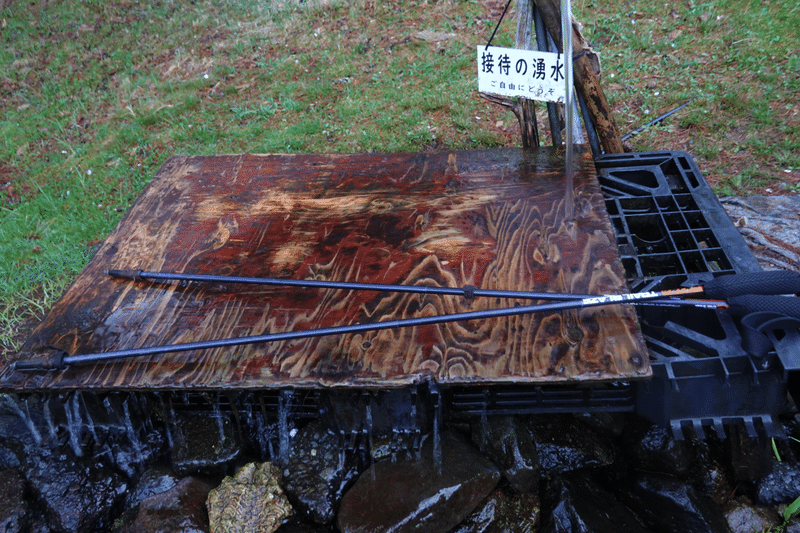
途中に接待の湧水があったので接待してもらいました。脚の状態はというと思いの外、痛くなくて一安心。ペースを上げると負荷が掛かるので、陽はどんどん暮れていくけど焦らずゆっくり進む。

峠のてっぺん近くは一面の笹の原なので広原と呼ばれる。その辺りに木は植ってないけどずいぶんと立派な一里塚がある。山の中は比較的保存状態が良い。


峠にある旧道のトンネルを抜けると下りが始まる。下りだから楽かというと脚への負担は登りより大きいのでそんなにペースは上がらない。



下りのトレイルにこんな説明書きに何回も出会う。辺りは真っ暗で何も見えないので看板を全部読む。中山道と言っても時代とともに変化があって一本ではないようだ。和宮の踏み跡は我々とは逆方向に進むが途切れることなく続く。これも中山道らしさの一つ。
トレイルが終わりしばらくロードを進むと諏訪の木落し坂に着く。前回の時はまだ明るいうちに通過したので急斜面を覗いてみたけど今回は真っ暗で恐ろしいのでパス。


下諏訪の街中に入ると道の脇に温泉が湧き出てる。

本陣を過ぎたところが中山道と甲州街道の合流地点だ。


ここは同じ末房さん企画の甲州街道“鳥の旅”のスタート地点なので懐かしさも感じる。

ほどなく本日のゴール、グリーンサンホテルに到着。
時刻は22:40。たった53kmなのにずいぶんと時間が掛かった。脚に配慮してペースを上げてないこともあるが、和田峠という大きな山越えがあったせいだろう。
温泉で身体をあたため、右膝をケアして眠りにつく。
5月1日
【第3ステージ】 下諏訪宿~木福島 54km
昨夜同様、夢を見ないで朝を迎える。
このステージも54kmと距離は短いが、今夜は木曽福島の宿で夕飯を一緒に食べることになっており期間中、唯一タイムリミットがある。18時には木曽福島駅に着かなければならない。脚が本調子でないし、なにしろ昨夜の宿到着が22時40分だったので18時に着ける気がしない。とにかく進めるだけ進んで状況判断するしかない。
朝スタートしてしばらくはロキソニンが効いてないのか、身体が冷えてるせいか脚の痛みが出てペースが上がらない。お天気は下り坂で雨が降り出す。


塩尻峠を越え、塩尻宿を過ぎ先へ進む。
鳥居峠の下りは痛みがあってペースが上がらなかったけど、下り切った辺りから痛みが消えたのでペースを上げて先を急ぐ。
意外と走れるので一安心。

途中、絵に描いたような立派な一里塚。

これより木曽路の標識。ここら辺に来るとさすがに「思えば遠くへ来たもんだ」と感慨深い。

左が鉄の道、真ん中は車の道、右が人の道。
やっぱ人は人の道がいい。

いいペースで贄川宿に着くと着いたばかりの末房さんに会う。顔を見合わせると驚いた様子。どうやら平出のエイドをすっ飛ばしていたみたいで自分が来ないの皆さん心配してたらしい。見落としてしまって申し訳ないことをした。

贄川宿の先、いかにも宿場らしい建物が並んでいて大勢の人が歩いてる。奈良井宿だ。

半ば観光地化されているが、旧道の旅らしくタイムスリップしたような空間はとても心地良い。

奈良井宿を出ると鳥居峠に入る。前回は奈良井宿も鳥居峠も深夜だったので、今回は景色の見える昼間に通過できて良かった。


しかし、鳥居峠を過ぎて林道に出た辺りで痛恨のロスト。そのまま西側へ下っていくところをなぜか南側へ続く林道を上がってしまった。峠を過ぎたら下がるのが当たり前なのに。何かしら先入観みたいなものがあって判断を狂わせる。あまりに登りが続くのでおかしいなと思って現在位置を確認したら、ルートから大きく外れていることに気づく。往復で2km近い。登って降りてなので時間的にも大きなロスだ。

鳥居峠を降りたところで末房さん移動エイドが待機してくれてたのだけど、先を急ぐあまり視野狭窄で気づかず、末房さんに呼び止められて気づく。先行する2人でギリギリ間に合うくらいで、頑張って走って間に合うかどうかは微妙なラインと言われた。間に合わなければ途中で切り上げてピックアップしてもらうか、夕飯に遅刻するか。とにかくやれるだけのことをやろうと思い走り出す。不思議と脚の痛みも消えたかのようにペースが上がる。まだこんなに走れるんだと少々驚く。しかし走ることに集中し過ぎて旧道への分岐を見落としてしまう。戻ろうかと思ったけど、夕飯最優先でこのまま国道を突っ走ることにした。車がひっきりなしに走る国道はその騒音がストレスなので本当は走りたくないけど致し方ない。国道を激増した結果、旧道と国道の合流地点に、旧道を先行した2人よりほんの少しだけ前に着いた。「頑張ったね。やればできる子やん」と自分を褒めてあげる。それでも木曽福島駅18時は僅かに間に合あず。18時をちょっと過ぎて着いたところ駅で待ってた末房さんが「夕飯の時間を30分遅くしてもらったから大丈夫」と言ってくれて一安心。みんな(と言っても3人ですが)完走できて良かった。
その夕飯はBBQ!



これ以上ないくらい超贅沢な夕飯。
頑張って走った甲斐があった!
体脂肪が減って低体温気味なので2回目の温泉に入って深い眠りにつく。
(第4ステージに続く)
〈参考〉

(走行距離58km)

(累積標高+1549m-1494m)
※最大ピークは和田峠、その手前の小さなピークは笠取峠

(走行距離60km)

(累積標高+1320m-1333m)
※最初のピークは塩尻峠、次のピークは鳥居峠、ただしロストしたので峠(標高1200m)よりかなり高いところまで上がってしまった^_^;
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
