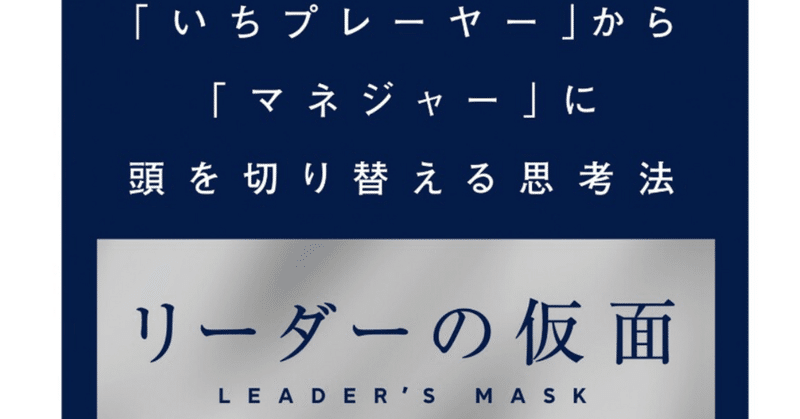
【Book Review】『リーダーの仮面』
『リーダーの仮面』
安藤広大(株式会社識学 代表取締役社長)
ダイヤモンド社.2020年
<本書のポイント 抜粋>
◎識学とは…
組織内の誤解や錯覚がどのように発生し、どのようにすれば解決できるか、その方法を明らかにした学問。
◎リーダーがフォーカスするべき5つのポイント
「ルール」「位置」「利益」「結果」「成長」
① ルール について
◎「姿勢のルール」
できる•できないが存在しない、誰でも守ることができるルール。
誰が何をいつまでにやるかを明確にする。
② 位置 について
◎ピラミッド型組織
高い位置にいる人は、未来を見据えて決断し、行動する責任を背負う。
指示は、上から下へ言い切る。報告は下から上に締め切りまでにする。
⇒ 仕事の任せ方とゴールを言語化する。
◎正しい「ほう•れん•そう」
上司から声をかけるのではなく、部下から時間を守らせて報告させる。
③ 利益 について
◎集団で大きな利益を獲得し、獲得した利益を分配する
集団でものごとを成したほうが、得られる成果が大きくなる。
良いリーダーとダメなリーダーの分岐点は、一人の部下に好かれるかどうかではなく、チーム全体のパフォーマンスに視点を置いているかどうか。
◎いい緊張感を醸成する
言い訳をなくしていくコミュニケーション
◎常に一定のテンションを保つ
指摘する時としない時のムラをつくらない。
④ 結果 について
◎自己評価よりも他者評価
◎プロセスへの介入,評価をやめて結果だけを管理する
⇒ 点と点の管理術
最初:目標設定をして仕事を任せる
最後:結果を報告させ評価する
※過去の自分のやり方や経験を押しつけるのはNG。目標さえ決めれば、途中のプロセスは、部下が創意工夫したり、失敗を繰り返して試行錯誤するはず。見かねて手を出してしまうことで、部下が失敗から学べるチャンスを奪う。
⑤ 成長 について
◎不足を埋めるから成長が生まれる
結果に対してリーダーが評価をする。そして、部下は、結果と評価のギャップを認識して、次の目標を「変えるべき行動」と一緒に設定する。そのギャップを埋めていくことにより、人は成長する。
◎人は経験とともにしか変わらない
知識は経験と重なることによって「本質」にたどり着く。つまり身体性(=経験)を伴わなければ、意味をもたない。まずは1回やらせてみる。
まだ経験していないことをいくら話されても、部下には伝わりようがない。
答えを与える組織は結果として成長の速度が遅くなる。長い目で見て部下が育つことを待つ。
<所感>
安藤広大氏の著書、識学の考え方をまとめ、累計100万部を超えた3部作の第一弾。
組織として働く(動く)上で、必要な考え方がまとめられており、個人的には過去の自身の経験の中で特に上手くいかなかったことと照らし合わせてみると、どれも納得できる内容だった。
つまり、部下の立場から、徐々にキャリアを重ね、後輩(部下)を持つ立場になって、さらに今の立場になって現在進行形で感じていることも含めて、考え方や立ち居振る舞いを見直すきっかけを与えてくれる内容となっている。
本書の中で特に好きな一節は、先の投稿でも引用したのだが、以下の部分。
知識は経験と重なることによって「本質」にたどり着く。
組織の課題は、人をいかに育てていくかにあると思う。それは、工房も例外ではなく、特に我々のようなノウハウを伝承し、それを人に伝え指導していくような仕事にあっては、いくら知識や情報を蓄えても「経験」を積まなくては能力は上がっていかない。
その経験を積む過程では、必ず大なり小なりの失敗が伴う。
しかし一方で、我々の仕事はほとんどの場合、先が保証された内容の契約は無く、1年ごとに契約でそれが更新されて結果的に複数年携わることになる。つまり、見方によっては失敗が許されない側面があることは確かだ。
これは、どの仕事においてもそうなのかもしれないが、そういったジレンマの中で仕事を発展させて続けていくのが会社(組織)なのだろう。
そのような組織体が動く際の行動指標のような役割を果たしているのが、識学であり、本書に綴られている内容であると思う。
一方、組織として徹底していくには、相互理解が必要であり、リーダーだけの理解では一方通行になってしまう為、組織として導入するには部下も含めた構成する人員全員で理解していく必要があるだろう。
なお、3部作のシリーズとなっている為、併せて読むことをオススメすると共に、第2弾,第3弾についても今後レビューしていきたい。
JPFストレングス工房
鬼頭 祐介
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
