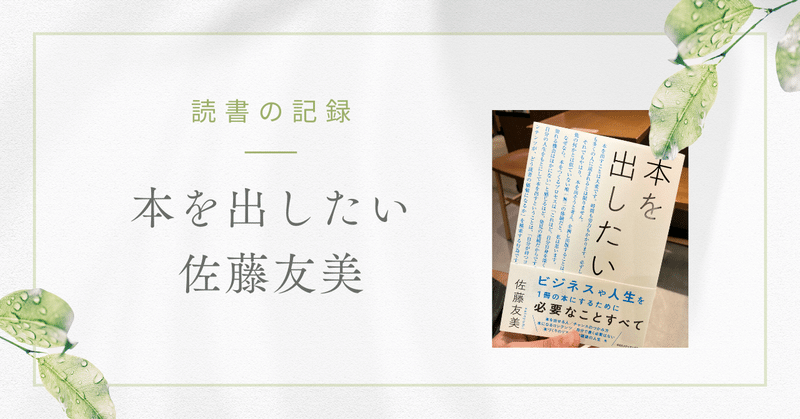
「本を出す」の裏側にある、広い深い世界:読書の記録『本を出したい』佐藤友美
前作『書く仕事がしたい』を読んだとき、すぐに「私もしたい!」と思い、著者さとゆみさんのライティングゼミに申し込んだ。
がっつり視野が広がったうえ、今、「ライター」という立場でレビュー記事を書く機会をいただいたりしている。自分の人生でこんなことが起こるとは考えたこともなかった。その間、2年。変化に驚いた。
先日刊行された姉妹本(?)『本を出したい』を読み終えた今、「私も出したい!」と思っているか?
実は、爽やかにYES!とは言えないのが正直なところ。
ほぼ人に言ったことはないけれど、本を出したいという気持ちは、何年間か、うっっっすらともっている。
でも、書けることないしな。テーマ見当たらないしな。私の人生そんなじゃないしな、と、ある意味いじけたような気持ちでいる。
だから正直、『本を出したい』を読むのには少しの勇気が必要だった。
私には手の届かない世界の話ばかりが書いてあって、完全に置いていかれるような気がしていたから。
誰でもない自分を改めて思い知らされるような気もしたから。
で、読んだ。私には関係ないけどねー、とか、まだそんなことを思いながら。
「こんな私に本は出せるのか?」という章で始まる本書は、あなたも本を出せ出せ出せ出せーと押し込んでくるものではなく、
「本を出す」ってこういうこと、
「本を出す」の周囲で起こっていること、
「本を出し」て読まれるための工夫、
「本を出し」た後のことが、
さとゆみさんが語るように書かれているものだった。
出版イベントで、さとゆみさんは「再現性」を大事に書いていると言っていた。読んだあなたが「本を出す」ために必要なことが丁寧に解説してある。
あとはやるかやらないかなんだ。←イマココ、私。
そして形のないところから本が生まれ、読者に届き、そのあとに起こることと、「本を出す」のプロセスがドキュメンタリーのように続く。これにはクラクラした。
一冊の本にはいろいろな人の強い強い想いや知恵や技術がつまっているのだと知った。本って途方もない空間なんだな。背筋をのばして本に向き合いたくなる。
驚いたのは、文章術までみっちり書いてあったこと。
10万字を最後まで読んでもらうための細かな工夫と思いやり。
言われてみれば確かに、誰かがただただ連ねた10万字を読むのは辛かろう。
読者には、初めの1ページでやめるという選択肢だってある。
本を読む=知識やアイデアを吸収する行為とした場合、一冊分の知識やアイデアをしっかりと受け取れるように、書き手は読み手のことをこんなにも考えて書いてくれている。って知らなかったよ。
本を書き終わったときに自分が空っぽになるくらいに全部書く、とさとゆみさんは言っていた。
出し惜しみせず、ご自身の技術や考え方、経験から得たことを共有してくれる。続きはLINE公式に登録を!とか言わない(言ってもいいと思うけど)。
著者・ライターとして60冊以上の書籍を生み出しているさとゆみさんの手と頭脳をこんなにコンパクトな形で受け取れるって、嬉しすぎませんか。
出版イベントのとき、参加者のおひとりがこんなことを言っていた。
自分は本を書くことはないけれど、読むことが好きで、いつも良い本に出会いたいと思っている。この『本を出したい』で背中をおされて著者になる人が増えるのは間違いない。それは世の中に本が増えるということ。だからさとゆみさんがこの本を書いてくれてとても嬉しい。
「人はみんな何かの専門家」と聞いたことがある。
まだ言語化されていないみんなの知恵や技術が本になって共有されたら、みんなで刺激し合ってよりエキサイティングな世界になる気がする。
上記の方が言うように、この本がそのきっかけになるのは間違いないなと思う。そこに、乗るのか、乗らないのか。
本を出そうが出すまいが、本をつくる壮大なプロセスを知れて、本との向き合い方が変わる1冊。
実用書と分類されるんだろうけれど、ものすごく心を動かされる、さとゆみさんのストーリー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
