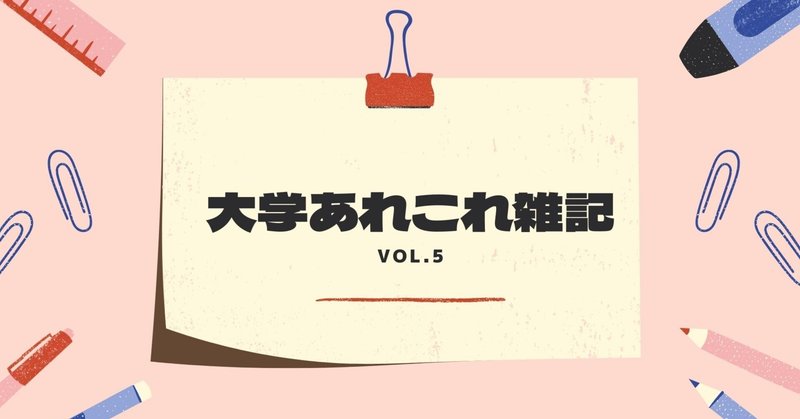
大学でどんなパンキョウをとる?①
4月に入り、大学では、入学式やオリエンテーションがひと段落して、新入生の皆さんは、授業に励みつつ、そろそろ新歓イベントもひと段落の時期ですかね。
大学のオリエンテーションは、単位履修から施設案内まで大学に関する諸々の説明を受ける行事ですが、筆者が今でも覚えているのは、「どうして、大学の授業は90分なのだろうか」という素朴な疑問。当時の担当職員が「大学の授業は、本当は 45 分なんだけど、自発的に行うだろう予習/復習等の(研究)時間を兼ねて90 分としており、だから、単位も、予復習時間分を含めているから2 単位なのだよ」という説明を受けて、わかったような、わかんないような気持ちにはなりましたが、「なるほど」と思ったのを記憶しています。
オリエンテーションが終わってすぐに、ほとんどの大学生が、シラバスと睨めっこで、専門科目や(一般)教養科目をどれにするか、場合によっては、友達と相談しつつも、決めたのではないでしょうか。
ところで、一般教養(通称「パンキョウ」と言われるもの)って、全部の大学で、だいたい同じものなのでしょうか?

こういう時は、【Twitter】さんと思い、「ぱんきょう」「一般教養」と調べたところ、無限にツイートが・・・。ちょっと調べきれないかも・・・。
ただ、調べていると、面白いことがわかりました。
そもそも、今は、一般教養科目と言わない大学もあるのですね!!!
たとえば、慶應義塾大学では、「総合教育科目」と言うそうで、早稲田大学では学部によって名称は異なるようですが、「(学部提供)全学オープン科目」「基盤教育、アカデミックリテラシー」という名称のようです。あとは、神奈川大学では「共通教養科目」、中央大学では「学部間共通科目」、関西大学では「共通教養科目」、香川大学では「全学共通科目(教養教育)」という名称があり、上智大学、立教大学をはじめ多くの大学で使われていますね。
ひとまず、「共通」「教養」を含んだものが、多くの大学で使われているようです。
ちなみに、一般教養って、ほとんどが1 年生(1 回生→ 関西ではセメスター制の関係で、こう呼ぶ大学が多いのです!)と2 年生(2 回生)に習得し、総習得単位1/3 程度を占める科目で、多くの大学では専門科目の倍近く設置されています。設置科目数など、取り決めがあるのかどうか、文部科学省のサイトで調べたところ、何やら難しい法規が書かれてありますが、「学校教育法」関連の法規(大学設置審査基準要項細則)のなかで、「一般教養的な教育内容と専門教育的な教育内容との量的バランスについては、学部、学科等の理念・目的等を勘案して、個別具体に判断する」とありました。
要するに、大学が好きに決めていいようです。
さて、「パンキョウの科目って、どの大学も同じなのか」という話題に戻りますが、たとえば、教養学部を有している東京大学を参考にすると、東京大学では、いわゆる1 ・2 年生は、「教養学部」の「前期課程」として、リベラル・アーツ教育として幅広い教養を学ぶカリキュラムとなっています。
そのなかで、「基礎科目」と呼ばれる必修科目があるそうで、文理を問わず、「外国語」「情報」「身体運動・健康科学」に加え、文科と理科に分かれた「初年次ゼミナール」等を組み合わせて学ぶそうです。また、「総合教育科目」とする慶應義塾大では、「人文科学系列」「社会科学系列」「自然科学系列」「系列外科目」から修得するとあります。また、明治大学を参考にすると、「学部共通科目」として、「情報関係科目」「全学共通総合講座」「学部間共通外国語」などがあり、「全学共通総合講座」を見ると、「初年次教育・リベラルアーツ講座」「キャリア教育講座」「国際社会講座」「時事講座」「ビジネス・専門実務講座」「明治大学講座」という体系にわかれており、それぞれの学部が提供する科目を、全学部共通で履修するというスタイルになっていました。
さきほどの「リベラルアーツ教育」を取り入れているかどうかということでも、大学によって、パンキョウのカリキュラムに対する考え方が異なっているのですね。
大学では、3 つのポリシー(「卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)」、「教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)」及び「入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)」)が設定され、それを基準に教育活動を実現していますが、まさに、ポリシーの数だけ、一般教養の体系がある、と言えそうです。
ところで、北海道大学のシラバスをみていると、1 年次の基礎教育としては「全学教育科目」という体系で開講されています。そこから、「一般教育演習(フレッシュマンセミナー)」とか「人間と文化・環境と人間・歴史の視座」といったテーマ別(学問別)の講座とか、「英語・独語・仏語・英語技能別演習」といった語学講座があったりします。
テーマ別(学問別)の講座は、さらに、それぞれのテーマに分かれており、例えば「環境と人間」というテーマの講座には、気候変動、生物の多様性、地球環境、共生システム、創薬、健康長寿・・・など、さまざまなテーマが設定された講座を履修することができそうです。
まだ2つの大学しかみていませんが、大学によって、設置の仕方が全然違う、ということがわかりました。授業の名称を見ているだけでも、知的好奇心を擽られるような刺激的な内容ばかりですね。
北海道大学で開講されている、このような講座群は、学問分野やテーマとしては、他大学でも同じような分野として設定されている感じがいたします。
もう少し掘り下げてみたいのですが、今回は諸々の説明で本当に
「お腹いっぱい」になってしまったので、次回に譲ります。

#大学 #大学生 #大学教育 #オリエンテーション #科目履修 #単位履修 #パンキョウ #一般教養 #共通教養科目 #総合教育科目 #リベラルアーツ教育 #東京大学 #北海道大学 #慶應義塾大学 #早稲田大学 #神奈川大学 #明治大学 #カリキュラム #ディプロマ・ポリシー #カリキュラム・ポリシー #アドミッション・ポリシー #代々木ゼミナール #代ゼミ教育総研
