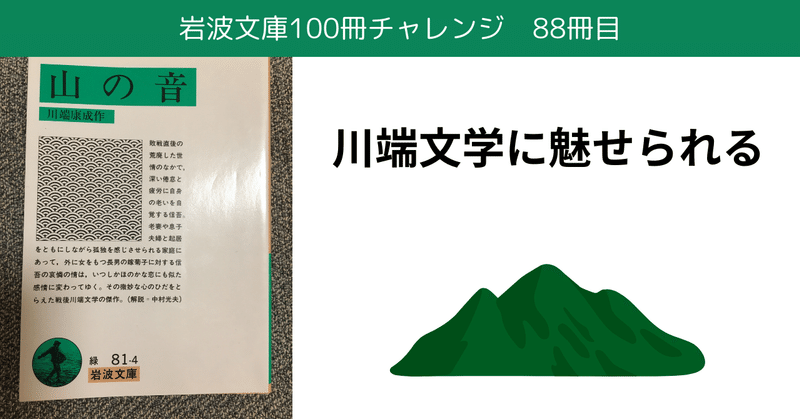
醜悪さえも美しく、川端康成【山の音】岩波文庫チャレンジ88/100冊目
太宰の後に川端康成を読む・・皮肉?(いえ、偶然です)。
川端康成と言えば、日本人で初めてノーベル文学賞を受賞した大人物。2人目は大江健三郎。カズオ・イシグロは英国籍のため、日本人受賞者はこの2人のみ。
1901年が第1回のノーベル文学賞は、存命中の人物が対象。川端康成の受賞も、「雪国」を「Snow Country」と翻訳したサイデンステッカーの名訳によるところが大きいとも言える。
太宰治が新人だった当時、すでに芥川賞の選考委員だった川端康成。太宰の薬漬けの私生活に苦言を呈した事が、少なからず落選要因とされており、その後2人の激しい手紙のやり取りが残っている。
太宰と川端康成。犬猿の仲のようにその作風、「美しい」とするものは違う。何を以て「美しい」とするかはその人の価値観の話。人間だから、好き嫌いはあるだろうけど、他人の価値観はそっとしておくのが良い。
「山の音」を読む理由
川端康成といえば「雪国」「古都」に「伊豆の踊り子」「舞姫」あたりが有名。
なぜ「山の音」か。
有名作は割と最近新潮文庫で読んだ事もある。岩波でも何か読んでみたいと思いあぐねていた所、こちらのYouTube「死ぬ前に読んでおきたい100冊」で「山の音」を見かけたのだ。
海外のランキングだが、わずかに日本作も入っていて嬉しくなる。といっても「源氏物語」と「山の音」の2作(カズオ・イシグロは除く)だけ。
自分は知らなかった作品。なぜ「雪国」ではなく「山の音」なんだろう。一体どういう作品なのだろう、と。
ちなみに、先のYouTubeで挙げられた作品をこちらで一覧にしているので、宜しければご参考にどうぞ。
こういうお話
大戦後のある家族の一コマを、美しく繊細に描き出したもの。今のように核家族ではなく、昭和の時代は大家族。長男夫婦は老齢になりつつある両親と共に暮らしている。
親と子、夫と妻、父親と息子の妻、母親と息子、などなど一緒に住んでいればそれだけ話題(問題)も多くなる。
物語の主人公は、ここでいう父親の尾形信吾。人や物の名前が思い出せない時があり、「老い」を気にし始めている。長男夫婦と暮らしていて、長男・修一が外に女があるのを知っている。修一の妻・菊子を不憫に思いながら、密かに恋心を抱く。
恋心と言っても、信吾本人はそれと気づき始めるのは終盤。終わりがけに、嫁・菊子も同じ気持ちを抱いていたのでは?と思わせる節も出てくる。
「嫁と義父の醜悪な恋」
それを「美しく魅せる」のが川端文学だった。
崩れていない綺麗な日本語の会話を読むのはとても気分が良い。昭和チックとかレトロと言ってしまえばそれまでだが、今の言葉づかいとは全然違って、なんとなく憧れる。
それだけ言葉が変わってしまったのか、川端康成がすごいのか、それはよく分からないけれど。
話言葉も美しれば、会話の内容も奥ゆかしくてなんと含みの多いことか。あれ?言いたい事は何だった?と一瞬頭が止まって考えさせられる会話も多い。
「嵐が丘」の激しくストレートな、狂気の物言いを読んだばかりなので、両極端が過ぎる事も、個人的に面白かった(笑)。はっきり物を言うよりも、何か含んでいる方が日本語らしいと思ってしまう。
個人の問題ではなく、家族の問題として、なんとか不和を解決しようとする父親・信吾。時代の転換期でもあり、個人か家庭か、で思い悩む姿も慎ましい。
登場人物それぞれの思いもあるが、敗戦後の物悲しさも漂う。修一が外に作った女は戦争未亡人。同じく未亡人となってしまった女性と共に励まし合って暮らしている。そんな修一も、戦争の経験を引きずっている。
それぞれの悲しみを背負いながら、
それぞれの道を生きて行こうとする姿がある。
全17タイトルの長編で、当時は短編のようにして各話にタイトルをつけながら、色々な雑誌に掲載していたらしい。
「山の音」というのも1話に限った話のため、小説のタイトルとしてはやや違和感もあるが、1冊にまとめるとこういう形になるのだろう。「亡くなる前に山の鳴るのを聞いた」というエピソードから、主人公の「老い」と繋げる事もできる。
物語は、なんとなくまだ続きがありそうな形で終わってしまう。
家族の抱える問題に「解決」はなく、これからもきっと続いていくのだろうな。
岩波文庫100冊チャレンジ、残り12冊🌟
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
