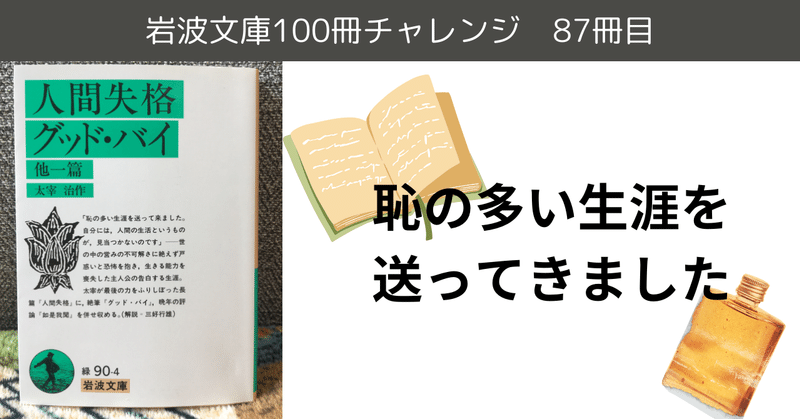
180度転換、再読のススメ【人間失格・グッドバイ】岩波文庫チャレンジ87/100冊目
自分の読書人生からは避けてきた。あえて読もうとしてこなかった太宰治。近年のマンガ・アニメ・映画化などあってか、若い世代に人気と知って、チャレンジ中に1冊読んでみようと思い立つ。
代表作「人間失格」
何となく知っていている程度で、ちゃんと読んだのは初めて。
暗い・陰鬱な印象は表面的なイメージで、きちんと向き合えば、太宰治が残した1つの文学作品だという事が分かった。
芥川を読んだ時も思った事だが、教科書で習う文学を大人になって再読するのはとても良い。学生時代と今とでは、本から拾う内容も量も、全く違う。
本書には代名詞「人間失格」、未完の「グッド・バイ」、文壇批判「如是我聞」、いずれも晩年の3編が収録。後でも触れるが「如是我聞」で展開されるのは凄まじい悪口。
よっぽど心に溜めたものがあったのだろう…。自ら生涯を閉じてしまった太宰治を知るには外せないか。憤懣だらけの当時とは比べものにならない名声を得た今。有名人は悪口すら世に残る。
人間失格
英語版は「No Longer Human」、海外の著名なYouTuberやBookTuberが好きな作品に挙げているのを聞く。若い世代というのは海外の人も含めて、何か心に刺さるものがあるようだ。
太宰を自◯に追い込んだ原因が書かれているのかと思い込んで読んだため、心の動きや変化を見逃さまいと気をつけていた。
本作の主人公は命まで絶たない。
調べてみると、
遺作になったため、自伝的小説と考えられているものの、真偽は不明。遺書には「小説を書くのがいやになつたから死ぬのです」と残されていたらしい。「人間失格」で見られる太宰の性格に「如是我聞」から分かる環境が関係して・・と憶測するのはあまりに短絡的か。
さて本作。
物語は、第三者による最初と最後のはしがき・あとがき、主人公・大庭葉蔵の3つの手記で構成される。
有名な書き出し
「恥の多い生涯を送って来ました」は、第一手記の出だしに過ぎない。
あとがきまで含めて本作だという事が最後のセリフでよく分かるので、厳密には「作品の書き出し」ではないのだろう。
以下、自分なりの要点(心の動き)と、印象的なセリフ(★)。
①子供時代、実家、父が議員のお坊ちゃん
・隣人とほとんど会話できない
・道化でわずかに人とつながっている
・欺き合いながら清く明るく朗らか、生きる自信を持っているみたいな人間が難解(この辺が若い世代の共感を呼ぶのか?)
②学生時代、東京、親の金で遊ぶ
・悪友、堀木正雄から遊ぶ事を覚える(酒、女、自堕落)
・合法より非合法が心地良い
・生まれて初めて恋心を頂いた貧乏くさいだけの女ツネ子と入水
・自分だけ助かり罪人扱い
「生まれた時からの日陰者」
「弱虫は幸福をさえ恐れる、綿で怪我をする、幸福に傷つけられることもある」
「人間のいざこざにできるだけ触りたくない、その渦に巻き込まれるのが恐ろしい」
「罪人として縛られると帰ってほっとして、そしてゆったり落ち着く。本当にのびのびした楽しい気持ちになる」
★鷗が「女」と言う字みたいな形で飛んでいました
③居候時代、お金に困る
・悪友のはずの堀木が家ではしっかり者
・内と外を区別しているのを見せつけられ、自分だけ取り残されたような気分
・「世間は個人」と言う見解に辿り着き、以前ほど心遣いする事がなくなる
④結婚生活
・堀木訪問中、妻ヨシ子が小男に姦通されるのを目撃
・致死量の催眠剤を飲む、薬漬け、酒びたりの毎日
「すべてに自信を失い、いよいよ人を底知れず疑い、この世の営みに対する一切の期待、喜び、共鳴などから永遠に離れるようになりました」
「男に対する憎悪よりも、最初に見つけたすぐその時に何もせず、そのまま自分に知らせに来た堀木に対する憎しみと怒りで呻きました」
「ヨシ子が汚された事実よりも、ヨシ子の信頼が汚されたということが、自分にとって生きておれないほどの苦悩の種になりました。ヨシ子の無垢な信頼心は、青葉の滝のように清々しく思われていたのが、一夜で黄色い汚水に変わってしまいました」
★罪の対義語は何?
★信頼は罪なりや?
⑤病院へ
・脳病院へ連れて行かれる、狂人というレッテル
・「人間、失格」
・兄が迎えに来て老女と田舎暮らしを始める
「自分には幸福も不幸もありません。ただ一切は過ぎて行きます」
「阿鼻叫喚で生きてきたいわゆる「人間」の世界において、たった1つ真理らしく思われたのはそれだけでした」
★ただ一切は過ぎて行きます
大庭葉蔵の手記はここまで。続くあとがきは、手記を読んだ第三者が、葉蔵を知る人物に話を聞く場面。「人間失格」は、最後次の文で閉じる。
「私たちの知っている葉ちゃんは、とても素直でよく気が利いて、あれでお酒さえ飲まなければ、いいえ、飲んでも神様みたいな良い子でした。」
・・・重い
外の顔である道化の自分と、内に秘めた人を恐れる自分。本当の自分を世間は理解しない。それを望むべくもない。(と、自分には聞こえた)。
他2作は軽く触れる程度に。
グッド・バイ
妻子がいる雑誌編集者、田島には愛人が10人近くいる。ヤミ商売から足を洗い、愛人とも別れて、田舎暮らしを志す。
愛人たちときっぱり別れるにはどうすれば良いか。
闇仲間で声は悪いが美人のキヌ子を連れて、妻だと偽り、愛人を歴訪、女が自然引き下がる計画を実行していく。
1人目、美容室の青木さんに「グッド・バイ」
2人目、軍人の兄がいるケイ子。
導入だけで、筆はここで途絶えている。
構想では「グッド・バイ」するつもりのなかった女房に「グッド・バイ」されるという結末。ひたすら苦しい「人間失格」とは違って、内容は軽妙でコミカル。
コミカル代表として「おそれいりまめ」という言葉を置いておく。響きが面白くっていつか使ってやろうと心に決める。
如是我聞
強烈な文壇批判。自分でどうこう書くよりも太宰の思いをそのまま引用したい。
弱さの美しさを知らぬ。
世の学者が自分の作品にとやかく言う言動に対しての自衛の抗議
文学においてもっとも大事なのは「心づくし」。料理が量でなく美味しい不味いでなく、料理人の心づくしが嬉しいように。
特別志賀直哉への文句は凄まじい。
「暗夜行路」はハッタリ。この作品のどこに暗夜があるのか。ただ自己肯定の凄まじさだけ。
もう少し弱くなれ。文学者ならば弱くなれ。柔軟になれ。お前の流儀以外のものを、いや、その苦しさをわかるように努力せよ。どうしてもわからぬならば、黙っていろ。
私は若い者の悪口は言わぬ。私に何か言われると言う事は、その人たちの必死の行路を無益に困惑させるだけのことだと言うことを知っているから。
芥川の苦悩が、まるでわかっていない。
など。
太宰にとっての「先輩」たちが、インタビューや雑誌で答えた内容に対する猛反論。「記事」になっている時点で話半分としてはいるものの、太宰の怒りは収まらない。
もしも、インタビューでなく対談形式であったなら、凄まじい文句が出てくる事もなかっただろう。本人を目の前にしたら太宰を傷つけるような言葉は出なかったはずだ。「記事」を面白おかしくするために舌鋒鋭くした事だって考えられるる。こういう批判に晒されていなければ・・とつい考えてしまう。
総じて、
自己肯定感が少しでも高ければ…今風な考えで言えば、自分の「弱さ」を認めている太宰こそ強いとも言える。真の自分と向き合い、目を背けず、自らはありのままの姿で、着飾った人間たちと戦った人。
どうかもう他人の悪口が聞こえませんように。
今の名声が届きますように。
そして私はあなたの他の作品を全部読んでみたいと思いました。
岩波文庫100冊チャレンジ、残り13冊🌟
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
