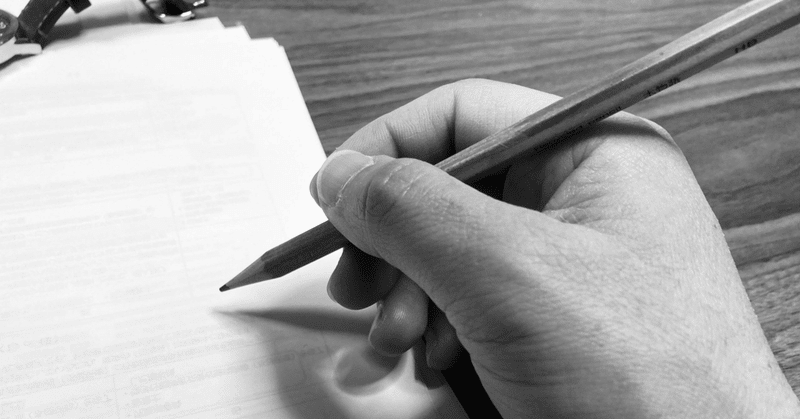
「うまい文章」と「惜しい文章」の違い
「文章がうまい」とはどういうことなのか。この2年間、様々なライターさんへの添削を続けるなかで、見えてきたものがある。もちろん「文章がうまい」にもいろんな要素がある。日本語がきれい、簡潔でわかりやすい、構成が良い、表現が素晴らしい、リズム感がある、切り取り方が見事、などなど。
ただ、あまり言及されないけど、添削者目線からは「これも大きいな」と思う要素がある。それは「突っ込むポイント」の有無である。
記事の添削をするとき、ぼくはまずはじめに全体を一読する。この際、たとえば同じ「4000字程度のインタビュー記事」でも、文章の質や書き手によって、読み終えるのにかかる時間がまるで異なる事実を発見した。単に「読むだけ」なのに、ある文章は10分で読めて、ある文章は15分かかったりする。これは一体どういうことだろうか?
おそらくこの違いが、まずもって「うまい文章」と「惜しい文章」とを分けている気がする。もう少し具体的に書いてみよう。
「惜しい文章」は、読み進めるなかで、「ん?どういうこと?」「え?何でこの人はこういう行動をしたの?」など、思わずツッコミをしてしまうことが多い。そこで考えてしまう分、タイムロスが発生するのである。あるいは、ある一文が一度ではパッと理解できず、2回3回と読み直してようやく「ああ、そういうことか」とわかったり。また、抽象的な表現や漠然とした表現が多く、読みながら「映像化」しづらいと感じることもある。映像化できるかどうかは、文章を読むスピードにも関わってくる。
一方、「うまい文章」には、突っ込むポイントがない。書き手によって、手際よくリスク回避されている。要するに、「こう書いたら読者はこういう疑問を抱くだろうから、手前にこの一文を入れておこう」とか、「聞いたままの流れで書くと読者は混乱するだろうから、こっちの話を先に持ってこよう」とか、そのような「見えない気配り」がなされているのである。この類の細かな努力が、読み手に気付かれることはほとんどない。せいぜい読み終えたときに、「良い記事だったな」と漠然とした好印象を持たれる程度だ。でも、ぼくはこういうところにライターの「職人性」や「奥ゆかしさ」を感じていて、「書く仕事」を誇りに思っている理由でもあるのだ。誤読されるリスク、意味が正確に伝わらないリスク、インタビュイーが悪く思われてしまうリスク(炎上するリスク)など、「読者視点」からあらゆるリスクを想定し、先回りして「読みづらさ」「わかりにくさ」「印象の悪さ」などの芽を摘んでいる。
だから、「うまい文章」は速く読める。「引っかかり」がないからスルスルと。まるで流しそうめんのように。余計な頭を使わないから、文章が長くても疲れない。そうした技術に裏打ちされているからこそ、川内イオさんや池田アユリさん(自慢のコンサル卒業生)が1万字以上のインタビュー記事を書いても、「おもしろかった。気付いたら読み終わっていた」と感じられるのである(素人が1万字書いても、普通そうはならない)。「映像化」もしやすいから、映画を観ているときのような没入感が得られる(こうなると読者は途中で離脱しない)。
一方、「惜しい文章」は、ところどころで立ち止まって考えてしまう箇所があるため、読むのに時間がかかる。そうめんが流れてこない。よく見ると途中の竹の接続部で麺が落ちてる。文章が短くても、頭を使うから疲れるし、集中力も途切れやすい。「ん?これは何のこと言ってるんだ?(少し遡って)ああ、これのことか。わかりづらいな」みたいな感じ。それが続くと、もう読むのが億劫になってくる。内容は良いはずなのに読了率が低いとしたら、このような原因で離脱されているからだと思う。
もう少し、ぼくが添削する際のことも振り返ってみよう。はじめに全体を一読したあと、また冒頭に戻り、そこから細かく赤字やコメントを入れていく。
このとき、ぼくは「書き手」の視点ではなく、「シビアな読者」の視点で読んでいるから、遠慮はしない。率直に思ったことをコメントする。
・(「具体的には」と書いているのに、後ろの内容が全然具体的じゃないです)とか、
・(この「それ」は何を指していますか?)とか、
・(普通の感覚の持ち主であれば、この場面でこういう行動は取らないと思うのですが、なぜ彼はこうしたんでしょうか?)とか、
・(論理が飛躍してます。「AだからB、BだからC」と説明すべきところを、「AだからC」とすっ飛ばして書いています)とか
読み手の自分が率直に「意味わからん」「どゆこと?」「わかりづら」と感じることを、(もちろんそんな乱暴な言葉ではなく、)できるだけ丁寧に言語化して、相手にお伝えてしている。「テキストではうまく伝わらないかも」と思うことは、お電話での添削フィードバック時に、相手の理解度を確かめながら口頭で伝える。それでだいぶ腑に落ちてくれるし、実際、改善点を意識することで次の文章がグッと良くなっている。
ライターならば、自分がイメージしている物事、イメージしているニュアンスを、文章で正確に読者に伝えること。「当たり前のことじゃん」と思うかもしれないけど、できていない人は案外多い。ひとつの書き方で二通りの読み方ができてしまったら、そこでズレが発生しかねない。誤読される可能性をゼロに近づける書き方が大切だ。
文章を書き終えたら、「読者視点」からよ〜く点検すること。難しく考える必要はない。シンプルに、「読者がこう捉えてしまうかもしれない」というリスクを、ひとつひとつ潰していけばいいのである。それで文章はだいぶ良くなる。神は細部に宿る。せっかく書いた記事をひとりでも多くの人に読んでもらえるよう、読者ファーストで。
いつもお読みいただきありがとうございます! よろしければ、記事のシェアやサポートをしていただけたら嬉しいです! 執筆時のコーヒー代に使わせていただきます。
