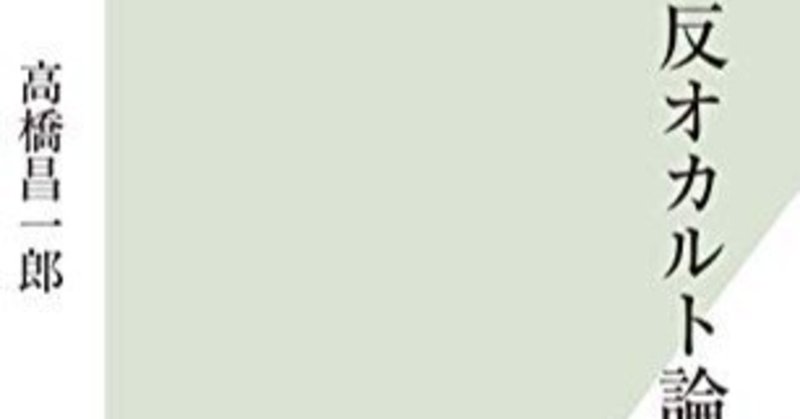
「反オカルト論」 高橋昌一郎 著 光文社新書
コナン・ドイルも、原子タリウムを発見したウィリアム・クルックスも、ノーベル生物学・医学賞を受賞したシャルル・リジェも、インチキ霊媒師にころっと騙されました。一方、当時の奇術師ハリー・フーディーニは、すぐにトリックを見破りました。「理性的」と思われる人たちは、実は神秘的なものに騙されやすいのかもしれません。
これは、少しわかるような気がします。僕は、もともと理系ですが、「現在の」数式や論理で見落とされる何かがあるのではないかという気持ちを常に持っていました。再現性があり、結果を予測できれば、科学としては成功なのだけど、そうなると、もうそれは興味の対象外になっていくということもあります。次の予測不能な事象のパターンを解明しようとする気持ちも起こりますが、実は、科学というやり方ではわからないものがあるのではないか?と考えたものです。多分、そうした思いが極端になったら、「理性的」な人をオカルトに向かわせる力になるのでしょう。
この本は、途中から、小保方晴子さんのSTAP細胞問題をオカルト的として取り上げています。小保方問題は、確かに妄信者が暴走するという点で、オカルト的なプロセスがあったと思います。
STAP細胞は、なかったのだろうと、今では僕も思います。しかし、あの事件当時、僕も騙されたおじさんの一人でした。しかし、騙されたのは、この本の中で指摘されているような、おしゃれで、ばっちりメイクをしていて、胸元の開いた服を着た若い女性だから・・・ではありません!断じて違うのです!・・・というあたりが怪しいと思われるかもしれませんが、天地神明に誓って違います・・というあたりがますます怪しい・・・と永遠に続いてしまうので、ここはストップしますが・・・。
僕が小保方さん側の意見を積極的とは言わないまでも支持していたのは、以下の理由によります。
1)論文を捏造するなんて勇気は、普通ないだろうと思ったこと。
僕自身、機械工学や臨床心理学の学会誌に投稿したことがありますが、不正をしたら、たとえそれがうっかりミスでも大変なことになると思ったので、相当ビビりながら投稿したからです。とてもデータを捏造する勇気なんてありませんでした。
2)査読論文であること。
一流誌になると、相当徹底的な査読が行われます。アメリカの心理学のジャーナルに投稿したとき、提出から掲載まで2年かかりました。その間、何度もやりとりがありました。そこで、誤魔化すことなんて、とてもとても恐ろしくて・・・という感じでした。
3)華麗な経歴
なんたって、早稲田大学で博士号、ハーバード大学で研究し、その後理研に雇われプロジェクトをリードしているのです。元理系の僕からすれば、キラキラに輝いている経歴です。こうした経歴を経て超一流の科学者のサポートを受けて世に出たSTAP細胞です。おかしな捏造があるわけないと、僕は思ったのです。
4)マスコミの手のひら返し
最も僕の判断を狂わせたのかもしれないのが、マスコミの対応です。そもそも、最初のニュースから、小保方さんの着ている服がなんとかかんとかだとか、割烹着だとか、ムーミンだとか・・・。あの持ち上げ方が気味悪かったです。それより、STAPとは何かもっと説明してほしいと思いました。それなのに、STAP細胞に疑惑が生じた途端、手のひら返しです。あまりに無責任だと思いました。マスコミは信用できないと思ったのです。
5)出る杭は打たれる。
僕も一応、日本のアカデミズムの世界にいました。そこでは、出る杭は打たれるという例もありました。小保方さんも出る杭扱いされてしまったのではないかという、同一化が起きてしまっていたのだと思います。
こうしたわけで、かつて僕は小保方さんを支持していましたが、それがオカルトの信者になるメカニズムと同じだと言われたら、反論できません。
僕は、今STAP細胞はおそらくなかったのだろうなと思っています。偶然ES細胞が混入し、それをSTAP現象だと勘違いしたのが最初なんじゃないかな?その後、後に引けなくなってあそこまで行ってしまったのではないかな?と想像します。そのプロセスの中で、小保方さんが意識的に捏造したのかどうかは、わかりません。
普通は捏造するなんて信じられませんが・・・。しかし、中にはやってしまう人もいるのだそうです。そうした人たちが、なぜそこまでのリスクをとりながら捏造するのかは、僕には理解不能です。
仮説はあります。もし、自己愛的な傾向が非常に強く日常的に合理化・否認の自我防衛機制を行なっていたのなら、あり得るでしょう。でも、小保方さんと会ってお話もしたことないのに、その判定をすることはできません。
この本を読んで思ったのですが、僕が工学(破壊力学)から心理学(臨床心理学)に方向転換したのも、オカルト的とも言える神秘現象に憧れるのと同じような心理が働いた結果なのかもしれません。その根底には、科学の向こう側にある何かに対する関心、内田樹さんの言う「超越的なものに対する敬意」があったと思います。
人間の心理は、複雑怪奇で、探究すればするほどわからないところが見えてきます。うつや不安になるメカニズムはある程度わかるのですが、どこで回復が起こるのかは、なかなか予測できるものではありません。ある種の偶然がクライアントの回復に大きく寄与することも数多くあります。僕は、その偶然性は「偶然」とそのまま残しておこうと思います。「偶然」に短絡的に説明をつけようとすると、それはオカルト的になってしまうかもしれません。
「偶然」を「理論化」するためには、地道な研究を続け、再現性が証明されなければなりません。それができなければ、あらゆる「説明」は、仮説に過ぎないという意識は持っておこうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
