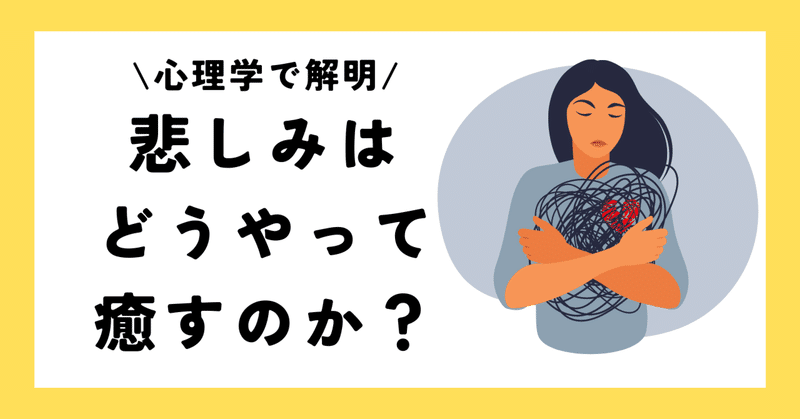
悲しみや喪失感などの感情は、どうすれば癒されるのか?
こんにちは、野口嘉則です。
悲しみや喪失感のような
とってもツラい感情って
どうすれば癒されると思いますか?
この問いに対して、
僕がライブの中でお答えした内容を
今回は公開します。
<質問:どれだけ味わえば悲しみは消えるのか>
視聴者さんから
こんな質問がありました。
【質問】
「悲しい・寂しいなどの感情は
受けいれて感じれば消える、
と心理学の本に書いてあり、
それをやっているのですが、
なかなか消えてくれません。
一体どのくらい感じれば
消えるのでしょうか?
最近は、悲しい感情を感じながら
『そんなに悲しむほどの
ことじゃないよ』とか、
『自分が恵まれていることにも
目を向けようよ』などと
自分に声をかけることも
やってみていますが、
これも効果がありません。
なにかアドバイスを
いただけないでしょうか?」
実は、昔の僕も
「感情をやわらげるためには
しっかり感じなければ!」と
感情を必死で味わっていました。
ところが当時、
いくら感情を味わっても、
それがやわらいでいく感じが
全然なかったんですよね。
どのとき僕も
「どんだけ味わえばいいんだろう・・・」
って思いました。
<悲しみは宝物になっていく>
たしかに
感情というのは、
受けいれ
じっくりと感じ
味わっていけば、
やがてやわらいでいきます。
ご質問の中では、
「どのくらい感じれば
消えるんでしょうか?」って
質問してくださっていますが、
実は感情というのは
消えるわけではないんです。
消えるんではなく
やわらぐんですね。
やわらぐっていうのは、
自分で対処できるくらいの
大きさにまでなる
ということです。
ツラい感情なんて
消えた方がいいのにって
思われるかもしれませんが、
そうじゃないんですよ。
自分を振りまわさないくらいの
大きさになったときに
それは「宝物」になるんです。
たとえば
大切な人を亡くしたとき。
最初はとてもとても
耐えられないくらい
悲しいですよね。
だけど年月が経つと、
その悲しみもやがて
やわらいできます。
悲しみにともなう
後悔の気持ちとか、
虚しさ・切なさ・やるせなさ、
そういう感情をしっかり
味わうというプロセスを
きちんと全うすると、
自分を振りまわない程度の
大きさにまでなります。
そうすると、
「自分の中にたしかに
残っている大切な悲しみ」
その悲しみがあるからこそ
自分はあの大切な人のことを
ずっと忘れないでいられる。
その悲しみがあるからこそ
自分は人に優しくできる。
その悲しみがあるからこそ
自分は謙虚になれる。
とそんなふうに、
大切な宝物になっていくんです。
こんな風に
大切な人を亡くすような
大変ツラい経験をすると、
僕たちはすごく
大きな悲しみに襲われますが、
その悲しみが
癒されていくプロセスのことを、
悲嘆のプロセス、
悲哀のプロセス、
喪のプロセス、
喪の仕事、
喪のワーク、
モーニングワーク、
などと呼びます。
このプロセスの間に、
悲しみをはじめとする
さまざまな感情を
ちゃんと味わい
自分のものにしていくと、
やがてそれらの感情はやわらぎ、
ある意味、宝物にもなる
ということなんですね。
<悲嘆のプロセスと受容の大切さ>
この悲嘆のプロセスを
過ごすあいだに重要なポイントは、
「その感情を受けいれて感じる」
っていうことです。
受容というと
大きく2つあって、
「自己受容」と、
「他者受容」があります。
「自己受容」は
自分を受けいれること。
「他者受容」は
相手を受けいれること。
ではいったい、
なにを受けいれるのか。
これは、
Doing 《ドゥ―イング》や
Haing 《ハビング》ではなく、
Being《ビ―イング》を受けいれること。
それを、受容と言います。
Doing は、
その人あるいは自分の行為です。
頑張ってるとか頑張ってないとか、
いい子にしてるとかしてないとか。
そして、
Doingの結果
手に入れるものを
Havingといいます。
成績とか業績とか学歴とか、
肩書きとか評判とか。
元々持っている才能なども
Doingに含めます。
自己受容や他者受容って、
このDoingやHavingを
受けいれるのではないんですね。
受けいれるのはBeing。
Beingとは存在そのもののことです。
それが自己受容であり、
他者受容なんですが、
この存在を受け入れるって
非常にわかりにくいですよね。
これをさらにわかりやすく言うと、
感情を受けいれるってことなんですね。
自己受容とは
「自分の感情を
自分が今感じてることを
あるがままに受けいれる」
ということ。
他者受容とは、
「相手が感じていること、
相手の感情をそのまま
あるがままに受けいれる」
ということです。
受けいれるっていうのは
「良い悪いの判断」
を下さないということです。
悲しい・不安・寂しい・むなしさ、
様々な感情がありますが、
それらに対して
「悪い感情」
「取りのぞいた方がいい感情」
というような判断を下すのではなく、
その感情をあるがまま受けいれること
を受容と言うわけです。
悲しいときは
悲しんでいる自分を受けいれる。
悲しみをそのまま受けいれる。
それが、悲嘆のプロセス中に
大切なポイントなんです。
<意外と知らない本当の受容の仕方>
さて、この自己受容、
すればするほど自己肯定感が高まる、
ということがわかってます。
あるいは、
親から子など、他者に対しても、
受容してあげればあげるほど
自己肯定感が高まるわけです。
ここでひとつ例をあげましょう。
子どもが不登校になっている、
とある親御さんがいます。
子どもが学校に行かなくなって
1年が経ち、非常に心配しています。
「できるならば学校に行ってほしい」
と思い、親として色々と努力しています。
あるとき心理学の本を読み、
子どもを受容してあげると
自己肯定感が育つと学びました。
その日から、
子どもがどんな気持ちを訴えてきても
それを否定せずとにかく受容しようとし、
「不安なんだね」
「怖いんだね」
といった言葉をかけ続けたました。
でもこの親御さん、
何ヵ月もそれをやっていくうちに、
こんな疑問を抱きました。
「一生懸命受容しているのに、
子どもの自己肯定感は
いつまでたっても上がらないし、
学校にだって行ってくれそうにない。
いったいどのくらい受容すれば
効果が出るんだろう・・・。」
こういうご相談を僕は何度も
受けたことがあるんですが、
あなたはお気づきでしょうか?
この親御さんは
子どもを受容できていないんですよね。
今のままの子どもでは受容できない。
自己肯定感が高い子どもになってほしい。
なんとか不安をゆるめてほしい。
なんとか学校に行ってほしい。
これは当然の親心なんですが、
ただ、子どもを受容できていない状態でも
あるですね。
あるがままの子供は
「不安、怖い、寂しい、
だから学校は行きたくない」
って言ってるわけです。
それを受容するってのは
めちゃくちゃ難しいことだって
きっと想像はつきますよね。
だけど、受容するってのは
そういうことなんです。
受容してるふりをして
受容してるかのような言葉をかけながら、
早く子どもが学校に行ってること、
つまり子どもが変わってくれること
を望んでいるのは、
実は受容していないわけです。
だけどこれは、
親御さんが悪いって話じゃないんです。
簡単にできることじゃありませんからね。
これが実は、
自分の感情についても同様なんです。
例えば、
自分の中に湧いてきてる
不安という気持ちがあったときに、
「不安だよね、不安でいいんだよ
私はあなたの事を受容するよ」
とどれだけ声をかけたとしても、
「どのくらい声かけたら
この不安は消えてくれるんだろう」
ってどっかで思いながら、
声をかけてるとしたら、
それはその不安を受容していないわけです。
<インナーチャイルドへのメッセージ>
この心の中の感情を
インナーチャイルド(内なる子ども)
っていうふうに例えることがあります。
不安やツラい気持ちを受容するとき
「早くこの不安が消えますように」
って思っているとですね、
自分の内なる子どもは
受容されてないって感じちゃうわけです。
「言葉では優しくいってるけど、
はやく私が消えていけばいいと思ってるんだ」
「僕がいなくなればいいと思ってるんだ」
「このままの自分ではダメだと思われてるんだ」
ってことが伝わってしまうということです。
なので、
はやくこの感情をやわらげよう
ということを目的に味わおうとすると、
本当の意味で受容的に味わうことが
できないんですね。
他にも
「そんなに悲しむほどのことじゃないよ」
「恵まれてることにも目を向けよう」というのも、
やはり感情を取りのぞこう・やわらげよう、
とする言葉ですので、非受容なんですね。
感情を受容するっていうのは
確かに簡単ではないんですが、
これは練習していけば、
誰もができるようになっていきます。
これは自分の大切な一部なんだ。
と、本当に認めて、
その感情と一生大事に付き合っていこう。
という覚悟で、感情をじっくりとあじわうと
いずれその感情がやわらいでいく
っていうことが起きるんです。
人のこころというのは逆説的ですよね。
「あなたは私の大切な一部なんだね」
「あなたの声を聞かせてね」
「これからずっと仲良くしていきましょう」
っていうふうにあじわってあげると、
結果的には逆にやわらいでしまう
ということが起きるわけなんですよね。
なのでやはり、
受容的なアプローチをするのであれば
こういった言葉で感情を抑えこんだり、
取りのぞこうとするのではなく、
その感情とともにいる。
その感情をしっかり味わう。
ということがカギになってきます。
ただし、
感じるのがあまりにもきつい感情は
無理してあじわわないほうがいい、
というのも覚えておいてくださいね。
<まとめ>
今回の話を
あなたの人生に役立てるとしたら、
どのように
役立てることができそうですか?
僕のnoteでは、読めば読むほど
「自己肯定感が高まり」
「人間理解が深まり」
「人間力が養われる」
コンテンツをお届けしています。
これからも確実に
自己実現へ向けて進みたい方、
ぜひフォローして
たくさんのヒントを
受け取ってくださいね!
また、今日お話しした自己受容について
より詳しく解説した記事をあげています。
ぜひぜひ読んでみてください。↓
ではまた、
次回の更新をお楽しみに!
動画で観たい方はこちら↓ (ライブ配信もこちらで行っています)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
