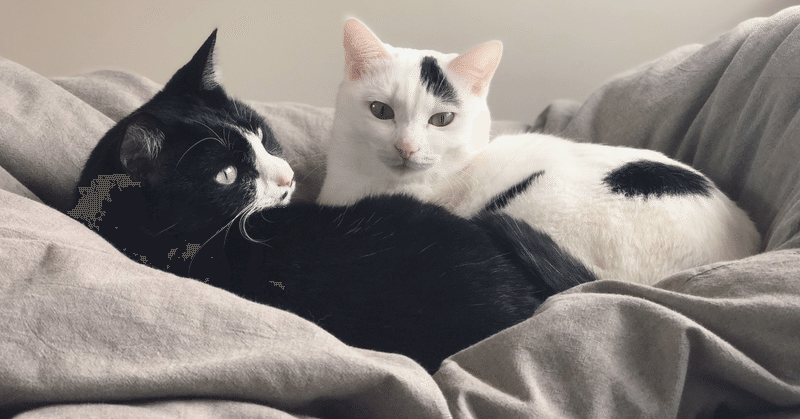
猫トレーニングのススメ
Karen Pryor Academy ライブエピソード#61では、ザジー・トッド氏の2022年5月に出版された「Purr」から抜粋して、猫が豊かな生活を送るための秘訣と、保護者のためのヒントを紹介しました。
ザジー・トッド氏(Zazie Todd, Ph.D.)は、犬を幸せにする科学を解説した本「Wag」とその猫バージョン「Purr」の著者です。Companion Animal PsychologyでブログとThe Pawsitive Postニュースレターで日々動物のトレーニングに関する科学に基づいた情報を発信しています。Blue Mountain Animal Behaviourのオーナー経営者であり、American Veterinary Society of Animal Behaviorのアフィリエイトメンバーでもあり、心理学の博士号を持ち、権威あるアカデミー・フォー・ドッグ・トレーナーで優秀な成績を収め、インターナショナル・キャット・ケアから猫行動学の上級証明書(優秀賞)を授与されています。英国出身で、現在、夫、犬1匹、猫2匹とブリティッシュコロンビア州メープルリッジに住んでいます。
なぜ猫は誤解されやすいのか?
多くの人が猫に対して固定観念を持っています。猫は扱いが簡単な動物である、猫は単独行動を取るなどなど、これらは一般的に認識されている猫の知識は本当ではないことがほとんどです。そして猫が本当に必要としているものを理解されていないことも問題です。当然のことですが、猫が必要としているものを与えてあげることで、猫をより幸せにすることができるし、飼い主との関係も向上します。
トレーニングすることの素晴らしさ
多くの人が猫をトレーニングするのは不可能だと思い込んでいます。トッド氏は本の中で猫がトレーニングを受けること有益性を解説しています。
一番大切なトレーニングとしてあげているのが、キャリートレーニングです。猫の飼い主の多くは、猫を動物病院に連れて行く時になって大捕物劇が始まり、姿を消してしまった猫を探し出すことも、見つけてもベッドの下や本棚の上の猫を確保する事ができません。動物病院に行くことを前提にしなくても、キャリーに入ることに慣れておくことで、安心できる場所としてキャリーを使う事ができます。猫は隠れるのが好きなので、キャリーにはいることは自然な行動として強化する事ができます。
もちろん練習は子猫の時から始めるほうが上手くいきます。しかし、たとえ成猫であっても、すでにキャリーにはいることを怖がる猫であっても、トレーニングは可能です。ただ少し余分に時間がかかるだけです。そして時間をかけても猫の幸せな日常を得るためにも練習する価値はあります。
またキャリーに入るのは病院に行くための運搬を楽にするだけでなく、病院内でのストレスを軽減できます。キャリーに慣れている猫はより少ないストレスで診察を受ける事ができるのです。

間違いを犯さない為の理解
正の強化を使ったトレーニング理論はありとあらゆる動物種に適応可能で、人間同士の関係にも使えます。しかし間違えてはいけないは、学習の土台にある科学はおなじであっても、対応する種や状況によって、行動のタイプや強化子が変わる事です。
猫は犬同様、とても人気のある4つ足の伴侶動物であるため、特に犬の知識を持っている人は猫を間違って扱ってしまうことがあるようです。猫の性質をよく理解して接しなくてはなりません。ここではわかりやすいように犬と比べながら、猫のトレーニングに際して考慮しなければならないいくつかの例をみてみましょう。
1. トリーツの種類とデリバリー方法
猫は小型犬サイズなので、トリーツの大きさはごく小さいものを選びます。犬は小さいトリーツなら飲み込んでしまいますが、猫はゆっくり咀嚼したり時には受け取ったトリーツを一度吐き出して再度食べたり、トリーツを受け取ってから飲み込み次の行動に移るまで時間がかかることもあります。
また、犬の場合はハンドラーの手が直接犬の口にトリーツが運ばれる事がほとんどですが、猫は人の手から食べない事もあります。スプーンや柄杓を使ったり、床においたり、床にあらかじめ設置したお皿に置くなどの工夫をします。
犬のようにおやつをせがんだりせず、固形のトリーツを好んで食べない場合もあり、トリーツの品質や形状には注意を払う必要があります。固形のトリーツが上手くいかない時は、チューブに入ったペースト状のものや、自分で用意したピュレー状のものをシリンジで与えるがいいでしょう。
2. 猫の触り方
犬がお腹を見せた時、そのお腹を撫でてあげるととても喜ぶ。おなような感覚で、猫のお腹を撫でると次の瞬間噛まれたり引っ掻かれたりする事があります。犬を飼っている人が起こしやすい間違いです。
猫がお腹を見せるのは、「あなたなら私のお腹を触らないでしょう」と信頼されたからなのです。通常猫はお腹を触られるを好みません。猫を触るのなら、頭や顎、頬がオススメです。そこを触る事でホルモンが分泌されるからです。 尻尾の付け根を触られることも好みません。
触られるのが好きで自ら撫でてもらうことを望んでくるのに、触っていると突然噛まれたり引っ掻かれたりする「ペッティング関連攻撃性 Petting Related Aggression」は、触る場所に関連する事が多いですが、触る時間の長さにもよります。猫は犬と違ってあまり長く触られることを好みません。触れ合う時間を短めにして猫の様子を伺うようにするのが賢明です。たくさん触れ合いたい時は、触る時間を短くして、回数を増やすことをお勧めします。時間を短くすることで、猫が興奮してしまう前に終える事ができ、また猫が触れることに同意を示しているかを確認する事ができます。もし同意していれば触るのをやめてもその場に止まるでしょうが、同意しなかったら、もしくはもう十分だと思っているのなら猫は立ち去るでしょう。

3. 猫のコミュニケーション・シグナル
猫が人に向かって鳴くことはよく見受けますが、鳴くという行為は大人の猫同士がすることではありません。猫が鳴くのは通常、人に何かをお願いする時です。時に人が猫の鳴き真似をして猫の気を引こうとしますが、猫には何も伝わっていないのであまり賢明だとは思えません。
鳴き声よりも特徴的で興味深い猫のコミュニケーションは「ゆっくりとした瞬き Slow Blink」です。これは猫どうしてもする行動で、身体を相手に擦り付ける「すりすり行動 Affiliated Behavior」と同列のもとみなされています。ゆっくり瞬きをすることで、攻撃性がないことを示し相手に安心をあたえる作用があるようです。これはそもそも、猫は見つめられるのを好まない習性からきているようです。余談ですが、数人の人がいる中で猫は一番ネゴ嫌いな人を選んで側による傾向があり、それは猫嫌いな人ほど猫を見つめないからなのです。
猫の社会化
猫の社会化時期は犬よりもとっても早くて短い。犬が生後3週から14〜15週の12週間であるのに対して、猫は生後2週から7周と言われています。よって、子猫をもらいうけて自宅に連れて帰った時点で、すでに適切な社会化時期は終わっているのです。故にブリーダーや子猫に関わっている環境がどんなものか、適切な社会化のトレーニングが行われている環境で生まれ育った子猫がどうかを確認することをお勧めします。
もちろん社会化時期を過ぎてしまった猫を社会化することは可能であり、適切な社会化訓練を受けてきた猫でも引き継き社会化を続ける必要はあります。それはポジティブな経験を積むことでなす事ができます。
野良猫と飼い猫の違い
野良猫と飼い猫の違いは動物福祉の観点から語られるべきでしょう。飼い猫は室内で暮らす故に、もちろんそれは全て人に頼ったものではありますが、安全が確保されています。それに対して野良猫は過酷な生活を強いられますが、自由に振る舞う事ができます。飼い猫には自由度に制限があるようですが、本当に自分の住む環境が嫌なら出て行ってしまうこともあります。室内にいるから安心できるとは限らず、飼い猫の幸せを願うなら飼い主は環境設定を丁寧にする必要があります。
通常野良猫は一日12〜14匹のネズミを確保し食べます。つまり、一日中食事を求めて探し回っていることになります。反して飼い猫は食べ物のを捕獲する必要がなく、食事が定時間に一定量与えられます。捕獲行動という猫の自然な行動をサポートしたいなら、食事を数回を増やしてみましょう。野良猫の食事回数のように一日10回に分ける必要はありません。せいぜい5回が良いところでしょう。回数が少ない分、フードパズルなどを使うことをおすすめします。
猫は飼いやすいと思いエンリッチメントを与えない飼い主さんも多いようですが、猫も犬同様、たくさん遊んだほうが問題行動を取りにくくなります。野良猫を違って刺激の少ない家屋で過ごす飼い猫にはエンリッチメントが必要です。おもちゃは自分一人で遊べるものを与えるのと同時に、飼い主と遊ぶ時間もふんだんに設けることで猫を退屈というストレスから解放する事ができます。

後記
ここで紹介したことは、本の内容のほんの一部です。ご興味のある方は、是非本を手に取ってみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
