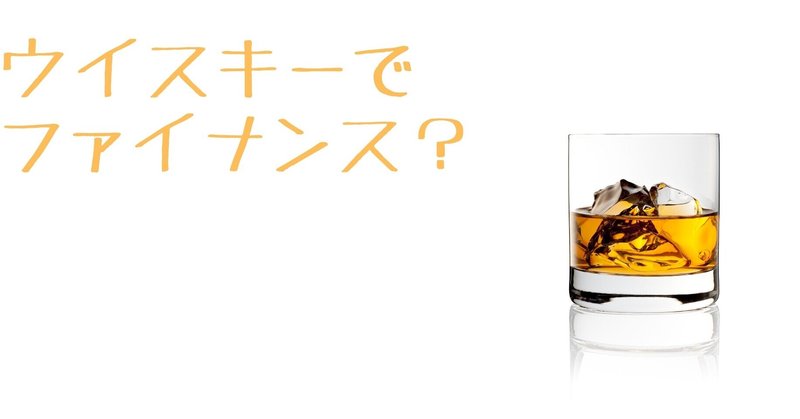
ウイスキーでファイナンス?
どうも、木村 義弘です。
先日までエモいファイナンスシリーズを書いて、「エモくないファイナンス」(つまりマジメなファイナンス)シリーズを書くという案もあったのですが、最近よく雑談で話す中で評判のよいテーマを書きたいと思います。
ずばり、
ウイスキー×ファイナンス!!!
世の中に、
・ファイナンスを深く語れる専門家
・ウイスキーを深く語れる専門家
はそれぞれ数多くいらっしゃいますが、この2つを絡めて話せる人は日本では少ないだろう!(ドヤ顔)
ひょっとして僕だけ?と思ってたりもします。

ウイスキーブームと原酒不足
とりあえず生!から「とりあえずハイボール」が定着した昨今。わたくし、醸造酒系(ビール、日本酒、ワイン等)はどうやら酔いが回りやすいようで、中ジョッキ1杯で顔真っ赤になります。
協調性マシマシのわたくし(起業してるのに?)としては「とりあえず生」の同調圧力が低下しただけでも大歓迎でございます。ダイバーシティ最高!
そんなハイボールブームと重なってか、先行してか、日本でも有名な白州・山崎・響といったジャパニーズ・ウイスキーが酒屋さんで手に入りにくくなって久しいですね。
これにはいくつかの背景・原因がありますが、どの原因も突き詰めれば「原酒不足」に行き着きます。
なんで原酒が不足するのか?需要を見込んで作れないのか?というとそりゃ無理なんですね。
なぜならウイスキーは「(樽で)熟成させる」必要があるからです。今年、ウイスキーの需要が高まる!と予測して10年前から多めに造っておく、なんてことは正直できないですよね。
ウイスキー事業はファイナンスを意識せざるを得ない
これをファイナンス観点で見ると、ウイスキーという事業は「支出(キャッシュアウト)超先行型」であるといえます。
先に原料を仕入れて、蒸留し、そのあと数年に渡って樽で熟成。
原料仕入れ、蒸溜所維持についてはキャッシュアウトし続けるわけですね。しかし熟成期間中は普通に考えるとキャッシュインがないわけです。
さらにさらに、新規に蒸溜所を立ち上げるとなるとどうでしょうか?
もちろん超絶設備投資が必要となります。大きいのは「スチル」と呼ばれる蒸留器。
蒸留器は1基でだいたい、3,000~4,000万円。通常、蒸溜所として稼働させるには少なくとも2基は必要となります。(ちなみに世界最大のスチルメーカーであるフォーサイス社に発注すると完成まで「4年待ち」とのこと。日本の老舗メーカーである「三宅製作所」に発注すれば1年程度で納品してくださいます。)
さらにさらに、その前処理の発酵をするための発酵槽等の設備も必要です。蒸留した後は樽で熟成しなければなりませんが、樽も空き樽1樽あたり10万円弱。さらに保管スペースも・・・というと設備投資だけでも2~数億円必要となりそうです。熟成期間を考慮して、その間の運転資金を含めると1桁億円後半から10億円くらいは手元資金として持たないといけないかもしれません。
初期の設備投資資金をどうするか?蒸溜所操業開始後、熟成させたウイスキーを販売するまでの資金繰りをどうするか?
うーん、なかなかにファイナンス。ワクワクします。(これは僕だけ)
こんな話を今後つらつらと書いていこうと思います。
過去の連載「エモいファイナンス」から派生した本シリーズは「ウイスキーとファイナンスと私」(なんか昭和っぽいですね)。
ゆるりゆるりと書いていきますので、ご関心あればお付き合いくださいませ。
【今日のウイスキーの「へ~」】
2019年のスコッチウイスキー規制の改正で、「焼酎樽での熟成」も認可されました。スコッチウイスキーで「Shochu Cask Finish」がリリースされる日も近い?
*本稿は100%趣味で書かれています。できる限り正確な情報でと思っておりますが、仕事の合間の息抜きに書いているので、もし間違いなどありましたら優しくご指摘ください笑
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
