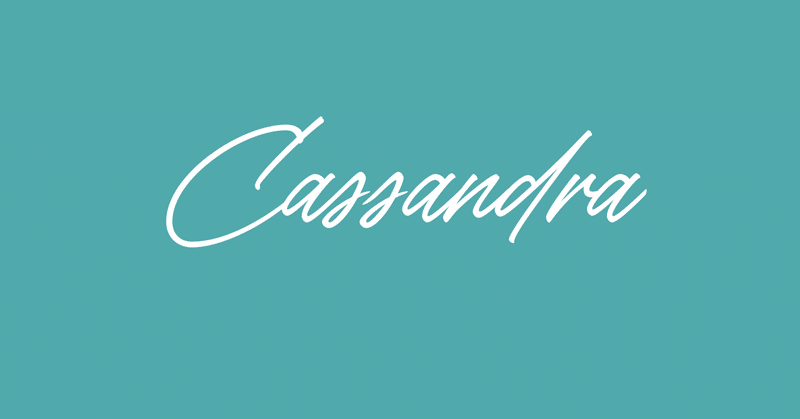
言葉あれこれ #5
最近、音声配信が増えた。
noteでもstand.fmなどを通してプロ顔負けのお話を沢山聴くことができる。YouTubeのような動画配信もある。
聴衆が目の前にいるかのように、みなさんとてもお話が上手だ。
以前も書いたことがあるが、私は文章では饒舌だが、話すときは口が重い。家族や気の置けない友達と少人数で話すときはお喋りなくらいだが、正直「話す」ことが好きになれない。
出ていった言葉は取り返しがつかない。心の奥底では「言葉を使って伝えること全般」が怖いのかもしれない。実際、ここ何年かブログやnoteで文章修行をしていても「言葉」の恐ろしさ、「伝える」困難さは日々、痛感している。
口から出た言葉は消えるが、文章はしばらくは残る。どちらも一長一短あるものだが、心に傷となって残る時に、どちらにも違いはない。言葉を大切にする意味で、畏怖を感じることはとても大切なことだ。でも、だいぶ年嵩になった今、いまだに人前で話すことに躊躇を感じるというのは、コンプレックス以外の何物でもないように思う。
カサンドラ症候群というのがある。
カサンドラというのはギリシャ神話に出てくるトロイアの王女だ。太陽神アポロンに見初められて彼から予言の力を授かったが、そのとたんアポロンが自分を捨てる未来が見えてしまったため、アポロンを拒絶する。それに怒ったアポロンは、彼女が予言をしても誰も信じないという呪いをかける。そのせいで、彼女が何を言っても、誰も信じてくれなくなった。兄のパリスが美女ヘレネを連れてきたときも、傾国のもとになると忠告したが、もちろん聞いてもらえなかった。そしてトロイアは滅んだ。
その神話から「パートナーや家族との日常のコミュニケーションに困難を感じ、その結果不安や抑鬱や身体症状が現れる」ことの総称として「カサンドラ症候群」という通称が用いられるようになった。一見、外からは何の問題も見えない。それゆえに窮状を周囲に訴えても誰も信じてくれないことから、その名がついたらしい。
私は一時期自分が「それかな」と思うことがあった。意識したのは夫との関係が上手くいかない時期だったが、おそらくは幼少期の体験が、根底にあるような気がしている。
小学生女子のいじめといったら、定番は「無視」だ。
これは結構、人格形成に悪影響を及ぼすぐらい、ボディブローのように後々まで効いていくる。極めて悪質ないじめだと、私は思う。
今の時代はどうなのかわからないが、昭和のころはリーダー格の女の子たちがターゲットを決めて、それが順番に回っていくのが常だった。だからリーダーの仲間に属さない女の子たちはいつ自分の番が来るかと怯えていた。リーダーの仲間でさえ、リーダー自身でさえ、何かの拍子にコインの表裏がひっくり返る。女子の世界とはそんなものである。でもそう思えるようになるまでには相当な時間を要した。そして私は、その「順番」がよく回ってきた。
みんな子供で成長の途中だから、当然価値観のぶつかり合いはある。でも女子は徒党を組み大人にばれない程度に相手を痛めつける巧妙さを持っている。エスカレートすれば出来心では済まされない悲惨な事件も起きる。
無視は暴力と見做されることが少なく相談された大人もなす術がないことが多いが、全ての暴力の根源だと思う。本当に興味がなければ無視もしない。無視というのは明らかに気に入らない相手を懲らしめその反応を得るための手段なのだ。それを暴力と言わずして何といおう。
とはいえ後に学ぶ「ぼっち上等」にはこちら側からの無視も必要になる。目には目を歯には歯を無視には無視を。互いに興味が無くなればよい。相手のフラストレーションが過剰になる前にできるだけ物理的に遠ざかる。相手の目の前から消え、自ら「ぼっち」を選ぶ。昨今言われるようになった「学校に行きたくないときは行かない」は命を守るために正解だと思う。
確かに私自身にも問題はあった。私はどういうわけか土地の言葉より標準語に近い言葉を話すことが多かった。そのうえ、残念ながら周りが見えないまま自分の意見を主張したり、「正義」を振りかざす発言はしていたように思う。あんたはお母さんか先生かというようなジャッジを、相手にしていたのではないかと推察する。
固まって楽しそうに話しているところに近づくとパーッと散るとか、場所を移して聞こえよがしに何か言うとか、こっちをちらちら見るとか、話しかけても答えないとか噂を流すとか。
研修や修学旅行などグループを作る、という活動は最悪だった。毎回、恐ろしい速さでグループが出来上がり、いつもあぶれた。学校には行きたくなかったし、楽しいと思ったことなど一度もない。それでも当時は学校に行かねばならないと思い込んでいた。
今思い出しても、子供心に傷ついた思い出がよみがえってきて胸がドキドキして冷や汗が出てくることがある。
学年が上がるごとに、そんな光景が多くなっていった。
原因、といって特定できるものではないが、やはり少し思い当たるのは「ことば」をめぐるすれ違いだ。土地と人と言葉とは密接に関係していて、同じ共同体の中での異質な言葉は排除されがちだ。関東と関西の差異や、留学先で言葉が出来ず苦しんだといった話はよく聞く。いつしか馴染める人と、どうしても駄目な人がいる。
特に低学年の頃は、私にとって「ことばをめぐる事件」というのがよく起こった。
ある時、内容は覚えていないが何かの発表させられたことがあった。
私は最後に「機会があったらまたやってみたいです」と締めくくった。
そうしたら、男子の何人かが突然笑い出したのでびっくりした。
「機械があったらだって」「バカだ」。そう言って笑われたのだった。
小学校の二年生くらいだったと思うが、大勢の人の前であざけられ笑われて恥ずかしさですくみ上がった。
今の子供たちは、バラエティーのコメントや動画慣れしているせいか、都会の子でなくても、年端もいかない子でも、テレビで流暢なコメントをしているのを見かける。私の発言など、あの子供たちの足元にも及ばないようなものだったと思うのだが、当時の地方の小学生の排他性というのはかなりのものだった。ちょっとでも異質とみるや、ある意味無邪気に攻撃をするのが当たり前だった。
さすがに先生が「今みらいさんが言ったキカイ、というのは、今度そう言うときが来たら、という意味ですよ」とフォローしてくれたが、結局はおかしなことを言った私が悪いのだった。さすがに本当にキカイを機械だと思ったのはほんの一部の子だっと思うし、今となってみれば恥ずかしいのは彼らだが、おそらくその時は、気取って小難しいことを言った(と思ったのだろう)私に、なにか難癖をつけたかったのではないかと思う。
またあるとき、東京から男の子が転校して来た。
話す言葉が似ていたから、私は外国で同国人に巡り合ったときのように嬉しかった。彼は彼で、周りの子となかなか打ち解けられずにいた。昭和時代は、東京と田舎では結構な言語的差異があったのだ。
その子は、ストレートに私に好意を向けてくれた。もちろん、変な意味での好意ではなく、なにしろ転校して初めてできた友達だから、無邪気に屈託なく話しかけてくれた。でも、悲しいかな、男の子と女の子が仲良くなると、子供たちは子供らしくからかったし、大人は「東京から来た子はマセてる」というような言い方をした。なにかそれが、私はとても嫌だった。
私は少しずつ、彼を避けるようになった。
本意ではないけれど、何か言われるのが嫌だった。
そのうち彼は、また転校していった。
そんなことがあって以来、私は東京というところがよほどいいところだと思うになった。あの子のように話の合う子がきっと沢山いるに違いないと思った。一刻も早く、ここではないところへ行こうと心のどこかで思うようになったのはその頃からだ。
中学ではサトちゃんと出会えたし、私も少しは上手く立ち回れるようになり、回避する術を覚えた。皆が同じように苦しんでいることも知った。他人の苦しみを喜ぶ人がいるのも知った。回避できないときの「ぼっち上等」も学んで、小学校ほどのことはなかった。高校は少し地元から離れたし、大学は県を離れた。
そして何より、私は書くことを覚えた。
誰にもさらされない言葉を書くことで、私はどんどん、楽になっていったように思う。
幼い頃は息苦しかった。
自分が心を開かなかっただけなのかもしれないし、閉鎖的な土地柄だったのも事実だろう。どっちが要因かは今はもう、わからない。どちらもだったのだろう。俗にいうHSP気味なところもあったのかもしれない。
いまなら、子供時代の私が幼稚だったことも、土地のせいばかりではないこともわかる。なんとか折り合いをつけながら成長したものの、「私が何かを言ったところで聞いてもらえない」という感覚はたぶん今でもまだ消えていない。
そんな私がnoteをすることになるとは、全く隔世の感がある。中年になってようやく、心の枷を外そうという勇気が持てた。noteは私を癒してくれる場所だったのだろうと思う。とはいえ、依存には要注意だ。
果たして独りよがりではなくきちんと伝えられているのだろうか。
伝わる言葉になっているのだろうか。
話し言葉でも文章でも、そんな風にふと思うと、例の思い込みが首をもたげてくる。カサンドラがそっと背後に立つ。
そもそも何を言っても無駄なのだ。
人は私の話を聞かないのだから――
これにとりつかれると厄介だ。
冷静に振り返りができず、自嘲したり卑下したりと変な方向に行きがちになる。
大人になってカサンドラの神話を知った時、シンパシィを感じた。
声は聞こえても言葉を無視されるということは、あなたをを信じないと他人から表明されることだ。とても、つらい。
みんなが自分の言葉に耳を傾けよ、などと思うならそれはサイコパスだし、現実にはありえない。でも発信に重みがある人と無い人があるのは事実で、私は圧倒尾的に「重みがない」部類に属する。そういう思い込みのブロックがなかなか外れない。それで必死に言葉を重ねてしまう。
だいたい私の伝えたいことなど、たいしたことではない。にもかかわらず、思いや出来事を言葉に変換し、なんとかうまく伝えなければならぬという使命感がどこから来るのか謎である。
私はなかなか、カサンドラの呪いから自由になれないようだ。
もう、充分に時は経ち、理は理解したというのに。
書いて届かない思いを感じることも多々あるが、それ以上に言葉を口から出すときに、強い諦念に苛まれる。
私が書くことに執着するのは、きっとそんな理由なのだろうし、そして書くことはやはり、私にとって執着なのだろう、と思う。
