
治療は足し算?それとも掛け算?
いつかはどこかで取り上げようと思っていたトピックですが、今、私の関係するアスリートとそのチームにおいては、たまたま道具がそろっていることと、活動時間・場所によって私の手の届かないところでのセルフケアに依存せざるを得ない、という側面もあって、ひとまずここに記しておこうかということで書いてみます。
ビフォー?それともアフター?
治療にはいろいろ手法がありますよね、思いつくだけでも、
超音波
低周波
マッサージ
ストレッチ
テーピング
エクササイズ
マイクロカレント
アイシング
ホットパック…全部書こうとしたらキリがないのでここで止めますが。
で、上に書いたものが一度に全部使えるとして、それらの手法の効率の良い順序ってわかりますか?
「順序なんて無い、空いているモノからやればいい」
って治療院、何軒も見てきました(涙)。特に保険で施術する接骨院・整骨院で、来られた患者さんを待合室で待たすわけにはいかない、という理屈で(そんなところに限って「XX(外国)で絶賛の最新の治療機器を…」とか謳ってたり… ええ、一部の方々を挑発してます)。
はっきり言います。「それじゃ治るものも治りません」
アスレティックトレーナーとしてチームで働くならとくに、練習(試合)前・練習(試合)後と同じ日で2回ケアできる立場にあるわけで、なおのことビフォー・アフターが大事です。ある手法を間違ったタイミングで施術したら、効果がでないどころか、マイナスに働く可能性がある、治療は足し算ではなく、掛け算。現状にマイナスを掛けてしまうと結果がマイナスになる可能性が大いにあるということです。
いつかちゃんと本にまとめようとは思うので、差し当たってここではざっくりと分類・順に列挙しますが、もしそこに興味を感じてくれたら、この続きを読んでみてください。
「ビフォー(練習・試合前のケア)」
基本、血流の改善をはかり、2次的に筋の収縮や関節の可動域を改善することと、練習(試合)での外傷予防を目的として
ホットパック(あるいはジョグや自転車エルゴなど自分で…)
超音波(局所に温熱と振動を)
マッサージ(ISTM器具やカッピングを用いた施術も含む)
ストレッチ(スタティック→ダイナミック)
テーピング(まぁ、当然ですわね)

「アフター(練習・試合後のケア)」
練習や試合で傷ついた組織が発する痛みへの対処と、その組織の損傷を拡大することなく、修復に向けての環境を整えることを目的として
リンパ刺激のための軽いマッサージ(とも呼べない程度の施術…必要に応じて、私が「やる」としたらよほど…笑)
低周波・干渉波(いわゆる「電気治療」…この呼び方嫌いです。*パルス周波数を100-150pps "High"のレベルに保って行うもの限定です)
アイシング(低周波・干渉波治療と同時に…アイスカップマッサージもこのタイミングで)
マイクロカレント(商品名「AT-Mini」など。知覚できないレベルの電気刺激によって組織の修復環境を最適化するため、就寝時など長時間にわたって施行可能、持ってるならやれば?という感じ)

例外1「クライオセラピー」
はい、いわゆる「ビフォー」の施術として、確かにアイシングを先にして、代謝を下げ、痛みが軽減した状態でストレッチをし可動域の拡大をはかる、などの手法があるのは存じております。MLBのニューヨーク・メッツやインディアナ州立大学、あるいはユタのブリガムヤング大学のアスレティックトレーナーとして3年以上お勤めになられた方なら朝飯前の仕事かもしれませんが、柔道整復師免許取得後27年、BOC-ATC資格取得後20年経っても私の知識、経験では練習や試合の何時間前までにそれを行うとよいのか、まだまだ分からないことだらけです。
例外2「低い周波数帯での低周波治療」
上記「アフター」の中で*を付けて示したところですが、低周波・干渉波治療器のセッティングの仕方によっては、2‐10ppsの”Low”に保ち「ビリビリ、チクチク」だけでなく筋肉が外から見てわかるくらい「ピクピク」する波形を用いてエンドルフィンを放出させる刺激が可能になります。「ビフォー」としてもしやるのであれば、ホットパックで全体的に加温する際に同時に、でしょうか。不随意運動でも疲労はあるので、どれくらいの刺激を入れるか、はトライ&エラーが必要になるでしょうね…。私は使うことがありますが、他に手段がなくなった時、ですかね。

以上ざっくりと今の私の考え方を述べてきましたが、この辺の実践に近い話は学校では学べないことですよね。どの物理療法が何を目的としているか、どのような機序で効果を発揮しているか、を理解できていればそんなに難しい話ではないのですが…そういえば、こんなの書いてましたわ、2年前でしたけど。
そういう私も来年には全く違うことを言っているかもしれませんし。今後加筆、修正をしていくことになるかと思いますので、これからも時折このページを覗いてみてくださいね。
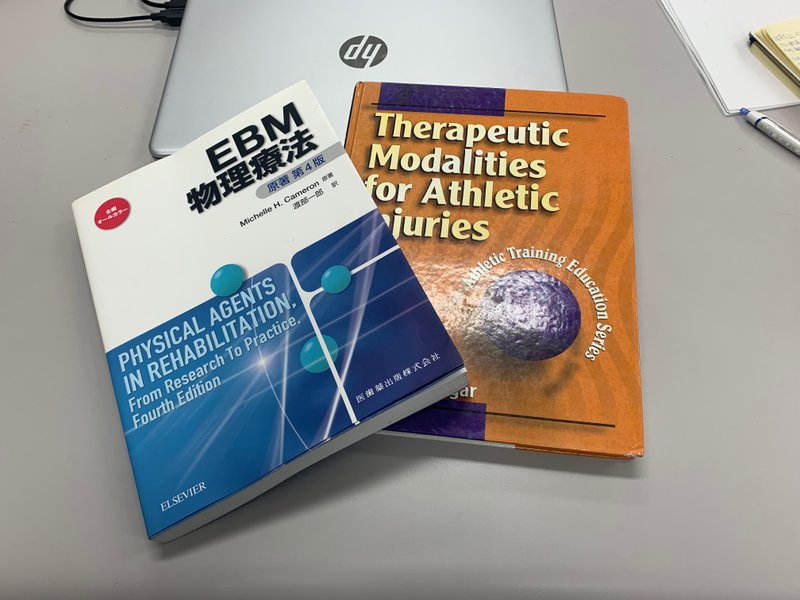
このnoteをご覧くださりありがとうございます。サポートいただけた際には子供たちが安心してスポーツに打ち込める環境づくりに使わせていただく所存です。よろしくお願いいたします。
