
「自分の顔が許せない!」を読んでの感想
「自分の顔が許せない!」は2004年に発行された新書です。少し前、時々通っていた町の銭湯で古本として売られていたところ、タイトルや帯が目につき、ついつい買ってしまった本です。
エッセイスト・作家の中村うさぎ氏とジャーナリスト・評論家の石井政之氏が著者です。
中村氏は美容整形を繰り返し、その過程も含め赤裸々に公表し世間の注目を集めました。石井氏は顔の右半分に生まれつき大きなアザを抱え、自らの顔にまつわる体験を語りつつ、顔や身体に目立つ徴(しるし)がある人への取材や交流をしている方です。
本書は、その二人の対談記録です。
以下、読み終えての雑感を2つ書きます。
まず、中村氏は、自分の顔と、自分の内面とにギャップがあるという思い込みから、美容整形を繰り返しているといい、同質性が強い環境により、わずかな違いに神経質となり、人から見ると大した違いがないことが、本人にとっては、大きな違いに思え、そこに対するコンプレックスは、明らかな身体的差異を持つ人と比べて大きいかもしれないと述べている点が印象に残りました。
内面にあるコンプレックスの大きさについて、比較するすべはないですが、わずかな違いに神経質になり、それが自意識の肥大化につながるというのは、なるほど、と思えます。「自意識の肥大化」という言葉を得たことは、その現象を僕自身もたびたび経験することで、自分を俯瞰してみるために、また、世間を見る上でも大事な視点であると思えるため何よりも大きかったです。
人は心身に何らかのコンプレックスを抱えています。本書では顔・外見とコンプレックスがテーマでしたが、昨今ほど「コミュニケーション」が、コンプレックスとなる世の中は今までなかったのではと、考えました。(実際のところ、ただ、自分自身を投影しているだけかもしれません。)以前「友人の社会史」や「オルタネート」のブックレビューとして、コミュニケーションをテーマにした内容を書いたことがあります。
「友人の社会史」では、集団主義から個人主義が主流化する中、多くの関係性が内容により規定されるようになった社会では、関係性の喪失による孤立を恐れるがゆえ、関係性が持つイメージが内容を支配するようになった。そのため人々は、友人の「美しさ」を求め、私たちは、そこから生まれる空虚感、神経質な気遣い、ストレスに、息苦しくなっている、というようなことが書かれていました。「オルタネート」はSNSでのコミュニケーションが場面中心の小説です。何人にフォローされているのか、「いいね」が何個ついたか、それらにやきもきする若者の姿が描かれていました。テレビやYOUTUBE、ネットニュースを見て、たびたび目にする謝罪シーン。発表だけならまだしも、その姿や内容がどうこうと評価や揶揄する声が、最近やたらと増えた印象を受けます。
人と人との関係性がまさに、「生存」がかかるほど重要であり、そのため他者からの評価が判断の中心となる風潮が現代ではないかと思われます。中島氏は本書で、整形して分かったこととして、整形は、理想の顔を手に入れる行為でなく、自分の顔を手放す行為であったと語っています。理想を追求するつもりだったのに、いつの間にか自分をなくしていたというのは、「コミュニケーション」全般で共通するものではないかと思いました。
対談の最後のほうで、思想を形作るのは人種でも、階級でもなく顔であるという石井氏の発言に呼応する形で、人間はどうにもならない身体的異形を持つものと、規格内にいながら、小さな違いに苦しんでいる人と、タイプは2極化しており、言葉狩りにより、その二つの世界が混じることがなくなっている。そのため、当事者が差別語を使って自分を語ることは、二つの世界をつなぐ上でも重要だと語られているところが印象的でした。
解離した世界をつなぐのは言葉。その言葉がどんどん規制されれば、何も語れなくなり、解離した世界はつながらず、規格外にいる人たちは、存在しないものとされかねないということが語られています。
私には「顔」だけに限った話には感じません。コンプライアンスが一層問われる世の中になりました。最近ではSDGsがいたるところでスローガンとして掲げられるようになりました。さして現実は変わっていないのに、あるいはその不可視化を図るべく、率直な言葉で語らず、言い方で「印象操作」を行い、私たちは知らず知らずの間に社会の分断を引き起こし続けているのかもしれません。
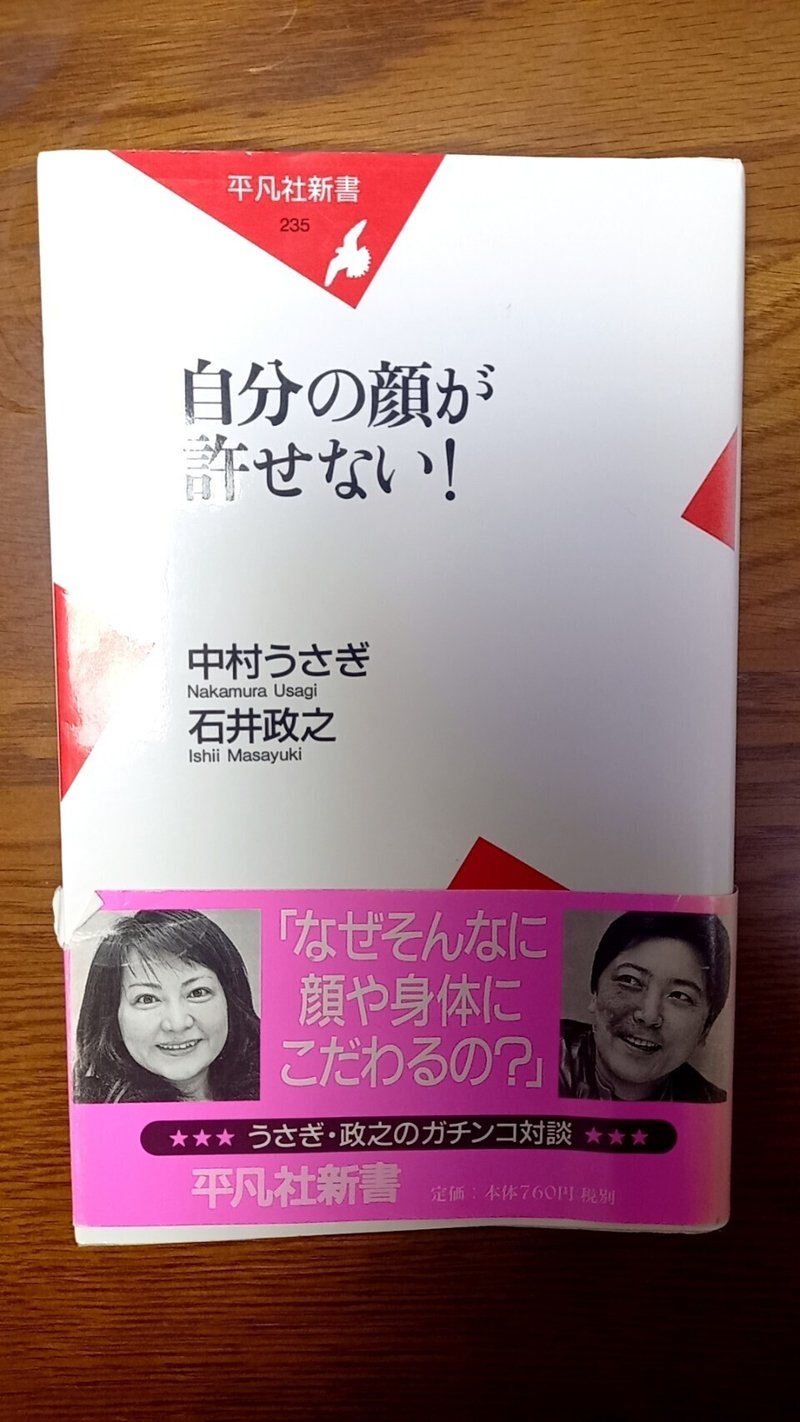
#自分の顔が許せない !#中村うさぎ #石井政之 #ブックレビュー #読書感想文 #コミュニケーション #美容整形
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
