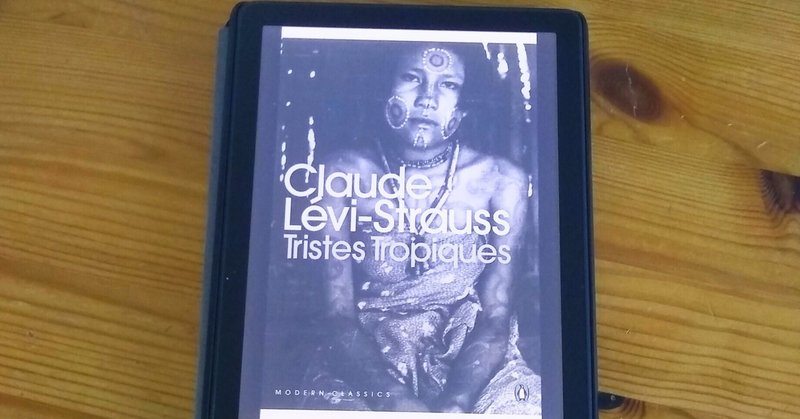
レヴィ=ストロース『悲しき熱帯』読書メモ
積ん読解消に専念していたら、また間があいてしまいました。
読了した本の一つがクロード・レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』。2年ほど放置していたのをまた手に取ったのは、宮本常一さんの『忘れられた日本人』を再読していて、「なんか似てるな…」と思いだしたからでした。
以下の文章の「東京」を「西洋」に入れ替えるとそのまま『悲しき熱帯』の雰囲気と重なります。
(略)これは今の日本の学問では日本の首府が東京にあり、また多くの学者が東京に集うており、物を見るにも東京を中心にして見たがり、地方を頭に描く場合にも中部から東の日本の姿が基準になっている。たとえば姑の嫁いじめが戦後大へん問題にされた。たしかに問題にしなければならないのだが、それは家父長制のつよいところにあらわれる。
(中略)
婚姻の問題にしても、明治中期以前親の言いなりに結婚したのと自分の意志の力で結婚をきめた娘の割合はどうであっただろうか。後者の例は西日本では前者より多かったのではなかろうか。
一つの時代にあっても、地域によっていろいろの差があり、それをまた先進と後進という形で簡単に割り切ってはいけないのではなかろうか。またわれわれは、ともすると前代の世界や自分たちより下層の社会に生きる人々を卑小に見たがる傾向がつよい。それで一種の悲痛感を持ちたがるものだが、ご本人たちの立場や考え方に立ってみることも必要ではないかと思う。
この2冊は構成も似ているんです。両者とも人類学(民族学)者によるフィールドノートをまじえた回想録で、第二次大戦前に訪れた各地――レヴィ=ストロースはブラジルのアマゾン、パキスタンやインド、宮本さんは日本各地の農村――について戦後に自分の考察や内省を加えながらつづったものです。
レヴィ=ストロースは構造主義の祖として有名ですが、この本には論文のような趣きは無く、ちょっとセンチメンタルな旅行記といった感じです。
* * *
さて、そんな感じで再度読み始めた『悲しき熱帯』でしたが、とても面白かったです。
一般読者が人類学者のエッセイに期待するようなエピソードはもちろんたくさん紹介されています。
例えば、アマゾンのある部族の村に滞在中、グループで遊んでいた女の子たちが仲たがいを始めて、やがて一人ずつレヴィ=ストロースのところにやってきて何やら耳打ちするのです。実は彼女たちの部族では名前を他人に知られるのは一種のタブーで、女の子たちは嫌がらせのために喧嘩相手の名前を彼に告げ口していたのです。日本や中国の諱(いみな)の慣習にちょっと似ていますよね。レヴィ=ストロースは少々罪悪感を感じながらも女の子たちが仲たがいするように仕向けて村の子供たち全員の名前を知ることに成功したとユーモラスに書いています。この作戦は大人相手には使えなかったようですが。
他にも、各地のインディオの道具や楽器などを手に入れるための物々交換用のプレゼント選びの成功談や失敗談(在庫処分の釣り針を安くまとめ買いしてアマゾンに持って行ったが、サイズが合わず、長期間持ち歩く羽目になった、等)、アマゾン奥地への信じられないほど骨の折れる旅。
旅ごはんもエキゾチック。
―ウイスキーでフランベしたハチドリの串焼き
―カイマン(ワニ)のしっぽのグリル
―ウイスキーでフランベしたオウムのロースト
―シャクケイ('jacu' たぶん、キジの仲間)とアサイーベリーのシチュー
―アカハシホウカンチョウ('mutum' キジの仲間)とヤシのつぼみのシチュー、ブラジルナッツとコショウのソース添え
―ロースト・シャクケイのキャラメリゼ
もちろん、ジャングル遠征ではごちそうばかりでなく飢餓も経験し、その後に狩りで仕留めた野生の豚の肉をむさぼるように食べたことを回想し、
数多くの旅行者たちが野蛮人たちが粗野である証拠として語る暴食癖の真実を僕はその時理解した。これは彼らと同じ食生活をして飢餓の苦痛を経験した者でないと分からない。こういった状況で満腹になるまで食べることができると、単に腹がふくれたというのではなく、気分が高まるような至福の感覚が生まれるのだ。
と書いています。こんな感じに、彼は終始、インディオに同情的です。
ほかに印象的だったのは、インディオの神々は普段の生活の至る所に溶け込んでいて、神の存在に特別にかしこまったりすることがないということにレヴィ=ストロースがカルチャーショックを感じるところ。これは日本人には容易に理解できる心持ちですが、西洋人には異質なことなのだなとあらためて思いました。
彼は子供の頃、ユダヤ教の聖職者である祖父とシナゴーグ(教会)に住んでいたことがあり、居住部分から教会へ向かう通路を使う時は、いつも緊張感のようなものを感じていたということなので、聖なる空間と生活空間が分かれていないインディオの信仰の在り方が新鮮だったんですね。
それから、私が個人的に好きな部分は、本書の終盤、レヴィ=ストロースが「人類学者とは何か?」「人類学者をやっている自分は何なのか?」という哲学的な内省を書き連ねているところ。
――なぜ自分は体中を虫に刺され、痛みかけた肉を食べ、ジャングルの中、道なき道を行き、命の危険を冒しながら自分が理解できない言語を話す部族の調査に出かけるのか。なぜ自分の属する社会に背を向け、外国の僻地の、あと何十年もすれば消滅するだろう民族を研究するのか。
それは元々自分が未開社会に魅力を感じている人間だったからではないか。そうであれば、自分は「好感」という先入観を持っていることになる。人類学が科学であるためには特定の社会に肩入れしたり、自分の文明の価値観で他者の文明をジャッジしたりすることは避けなければならないが、それは良い悪いの絶対的な尺度を否定しなければならないということを意味するだろうか。例えば、食人などの行為を残虐とジャッジすることもいけないことなのか…。
そういうことが長々と書いてあります。
「歴史や社会を見ているこの自分は何者なのか?」という、主観や視座の自覚って大切ですよね。
ちょうど、島村さんが似たことをnoteに書いていらしたので、個人的にタイムリーだなぁと勝手に運命のように感じながら(自分の思い込みが怖い!)拝読しました。 『The Culture Map』(Erin Meyer著)という本の紹介をされている部分です。
誰かと接するときに何の先入観を持たずにすることはできない。私達はそれぞれ自分自身の感じ方・理解や視点・価値観・行動様式といったような枠組みを持っていて、それはやはり生まれ育った環境に影響されていることは間違いないだろう。だからカルチャーの違いに目を向けない人は、実際には、自分が自身の持つカルチャーの枠で見て話し判断していることを知らないままでいることになる。そこに目を向けるにはやはりカルチャーを意識するほうがよいのだ。
島村さんのnoteは飯テロ要注意です。音楽のアンテナの広さにもいつもびっくりです。
順番がぐちゃぐちゃですが最後にもう一つ、『悲しき熱帯』の最初の方に書いてあった(ような気がする)、観察されている対象が観察者を認識した時点でその対象の元の状態を観察することは不可能になるという人類学者のジレンマもとても印象に残った一文でした。異なる文明同士が一度、接触を持ってしまえば、もう互いを知らなかった頃のようには振舞えなくなります。これに関連すると思うのですが、彼が「仏教・キリスト教・イスラム教でなく、仏教・イスラム教・キリスト教の順番で生まれていれば良かったのに」と書いているところがあり、とても面白いと思いました。
さて、思いつくまま不格好な感想文をつづってしまいましたが、とりあえず初読の感想メモは以上です。時間をおいて再読したいと思っています。
余談ですが、ウィキペディアのレヴィ=ストロースのページにこんなことが載っています。
未開社会の婚姻規則の体系、無文字社会を贈与の問題や、記号学的立場から分析した。オーストラリア先住民(アボリジニ)と東南アジア・古代中国・インド・北東アジアの婚姻規則の体系を構造言語学のインスピレーションをもとにして統一的観点からの分析をし、博士論文となった1949年の『親族の基本構造』において自らの基本的立場を明らかにした。
この「構造」に、群論を使った数理的な解析を与えたのは、数学者のアンドレ・ヴェイユ(かのブルバキの結成メンバーであり、シモーヌ・ヴェイユの兄である)である。
「群論」って名前しか聞いたことがないのですが、親族構造を数理的に解析するってどんな感じなんでしょう?理解できる頭が欲しかった…。分かる人の脳を部分的に移植してもらえる技術とかできないんでしょうか。でも、こんな話を聞いたら「世界シミュレーション仮説」がますます現実味を帯びてくるような気がします。シミュレーション世界なのに現実味とはこれいかに…と自分にツッコみ。
ありがたくいただきます。
