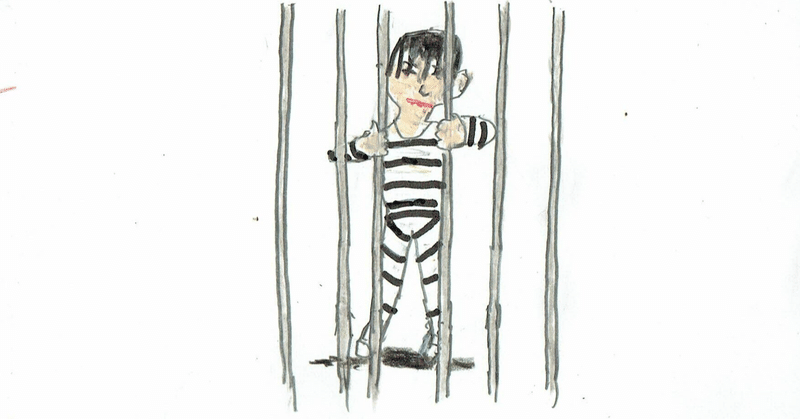
コンプライアンス体制を構築したはずなのに社内の違法行為が後を絶たない理由
おはようございます。弁護士の檜山洋子です。
社内のコンプライアンス体制を構築しているのに、また社内で法律違反が発生してしまった・・・体制の問題ではなく、その従業員個人の問題なのではないか、今回は運が悪かったと思ってその従業員を解雇して新しくいい人を雇用しよう!ということを繰り返している会社は少なくないと思います。
確かに、教育の不可能な程に遵法精神が欠如している人を間違って雇用してしまうと、どんなにいいコンプライアンス体制を構築してもなかなか有効に機能しないことはあります。
しかし、解雇しても解雇しても従業員の違法行為が繰り返されるときには、会社のコンプライアンス体制自体の有効性を再度確認することが必要です。
上に立つ者のコンプライアンスに対する意識は高いですか
まず、せっかくいい体制を構築したつもりになっている場合でも、組織の上に立つ者、つまり、社長は当然のことながら、その他の取締役や各部署の管理監督者らのコンプライアンスに対する意識が低いと、その下の者たちの遵法精神も自然と低いものになってきます。
会社の風土に逆らって異を唱えることは、新卒で入った従業員なら特に難しいことが予想されます。
まあ、そもそも、そのようなモラルの低い経営陣が、コンプライアンス体制を構築しようと思うこともあまりないでしょうから、現実的には、経営トップの問題というよりも、各部門における責任者の遵法精神の欠如が問題となることが殆どでしょう。
その場合には、管理者教育にコンプライアンス教育を組み入れ、考え方からしっかりと教育し直すことが必要です。
日々の業務を行うに当たっての明確な行動基準はありますか
せっかくいいコンプライアンス・マニュアルを作成しても、抽象的すぎるものや、難しい言葉が使用されたものだと、従業員はそのマニュアルに従って行動することが困難になります。
また、読む人によって違った意味に理解されるような不明瞭な書き方をしている場合も、明確な行動基準にはなり得ません。
誰が読んでもクリアで判りやすい文章のマニュアルを作成するようにしましょう。
コミュニケーションは取れていますか
経営トップが優れた遵法精神を持ち、明確でわかりやすいコンプライアンス・マニュアルを作成したにも関わらず、それが従業員の隅々にまで伝わらなければ何の意味もありません。
何度もくり返してトップの精神を伝えて理解を求め、コンプライアンス・マニュアルの内容を説明して実行に移すことを促進させる働きかけが必要です。
社内の上下左右のコミュニケーションをしっかり取ると共に、その中にコンプライアンスに関することも積極的に取り入れるようにしましょう。
定期的に見直していますか
また、コンプライアンス体制は、やりっ放しでは何の効果も出ません。
業務自体も働く人々の気持ちも日々変化していますから、その変化に合った体制になっているかをモニタリングすることが必要です。
そして、モニタリングした内容を現実の体制に反映し、必要な修正を随時行っていくようにしましょう。
結局一番大切なことは
コンプライアンス体制を構築することも、その体制に魂を入れることも、結局は、経営トップがコンプライアンス体制を構築しようという強い思いと実行力を持たなければ叶いません。
トップ自ら、強い信念と粘りをもって、繰り返し改善し実行していくことが大切です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
